薬物依存症は、薬物の使用をやめたいのにやめられない脳の病気です。専門的な治療と周囲のサポートで回復が可能です。一人で悩まずご相談ください。
自分の意志ではやめられない「病気」
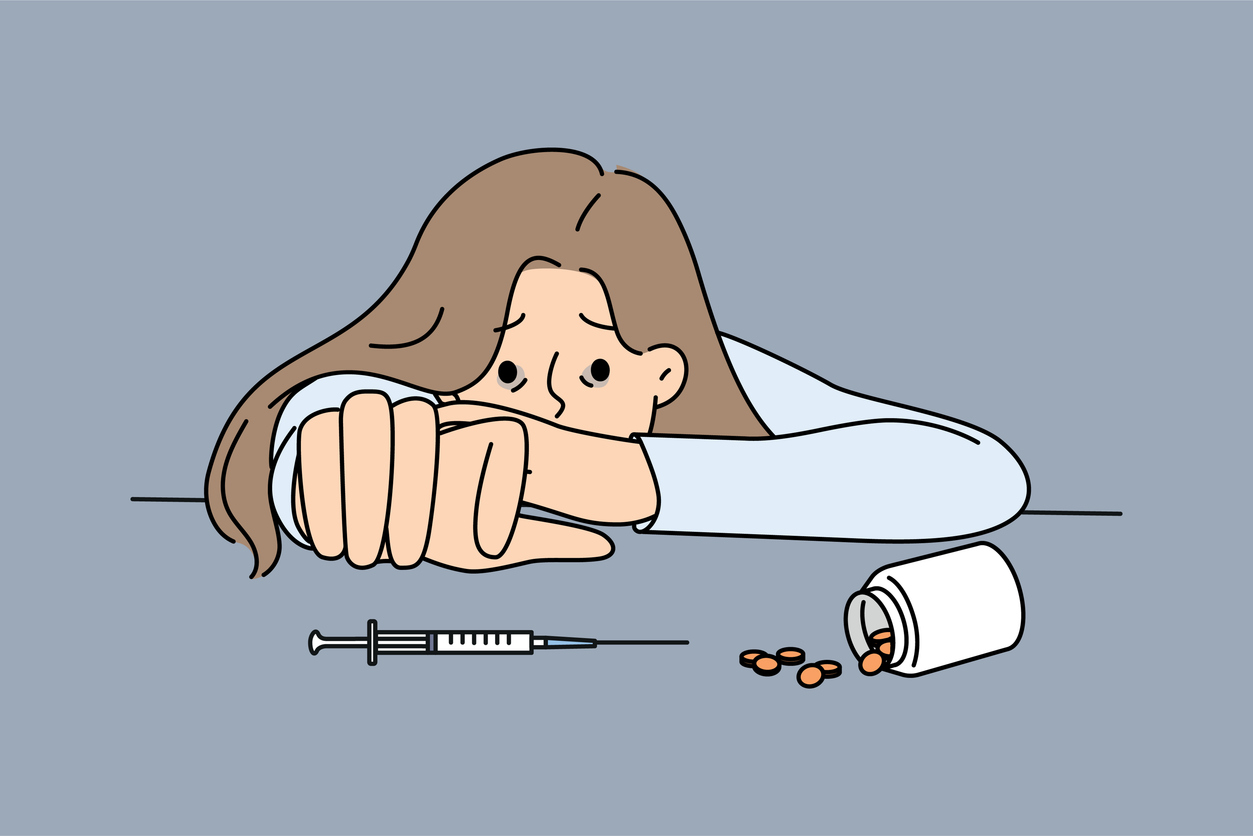
- やめようと思ってもやめられない
- 使用量や回数がどんどん増える
- 薬物中心の生活になる
- 薬が切れると不快な症状が出る
- 薬物のために大切な活動をやめる
- 心や体に問題が起きても使い続ける
- 薬物の入手に多くの時間を費やす
- 「やめる」「使いたい」で葛藤
1. この病気とは?
薬物依存症は「ダメ、ゼッタイ」だけでは解決しない脳の病気です
「薬物依存症」と聞くと、「意志が弱い」「自制心がない」「犯罪者」といった、少し怖いイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、薬物依存症(現在の診断名は「物質使用障害」)は、本人の性格や道徳心の問題ではなく、専門的な治療が必要な「病気」です。
例えるなら、脳の中に薬物への欲求を求める「暴走回路」ができてしまうようなものです。一度この回路ができてしまうと、自分の意志の力だけで薬物の使用をコントロールすることは非常に困難になります。「やめたい」と心から思っていても、「使いたい」という強い欲求(渇望)が湧き起こり、自分でも気づかないうちに再び使用してしまうのです。
この病気は、覚醒剤や大麻などの違法薬物だけでなく、睡眠薬や抗不安薬、咳止め薬、痛み止めなど、医師から処方された薬や市販薬でも起こり得ます。最初は不眠や不安、痛みを和らげるために使い始めた薬が、いつの間にかやめられなくなり、日常生活に支障をきたすケースは少なくありません。
大切なのは、「本人の意志が弱いからだ」と責めるのではなく、「治療が必要な病気なのだ」と正しく理解し、専門家と一緒に回復への道を歩み始めることです。一人やご家族だけで抱え込まず、まずは相談することが、回復への大きな一歩となります。

2. 主な症状
「おかしいな?」と思ったら注意したいサイン
薬物依存症の症状は、身体、精神、行動の様々な面に現れます。ご本人や周りの方が「もしかして?」と感じたときに、チェックしていただきたい代表的な症状をご紹介します。
精神的な症状
- 渇望(強い使用欲求):
薬物を使いたいという強い衝動に駆られます。「もう二度と使わない」と決心しても、ふとしたきっかけで欲求が再燃します。 - コントロール障害:
一度薬物を使い始めると、量や頻度を自分でコントロールできなくなります。「少しだけ」のつもりが、気づけば大量に使用してしまいます。 - 気分の変動:
イライラしやすくなったり、落ち込んだり、逆に妙に高揚したりと、感情の波が激しくなります。 - 幻覚・妄想:
特に覚醒剤などの精神刺激薬では、「誰かに悪口を言われている」「監視されている」といった幻覚や妄想が現れることがあります。これは薬物の直接的な作用によるもので、本人はそれを現実だと信じ込んでしまいます。
身体的な症状
- 耐性の形成:
薬物を繰り返し使用するうちに、これまでと同じ量では効果が得られにくくなり、より多くの量を求めるようになります。 - 離脱症状(禁断症状):
薬物の効果が体内から切れると、様々な不快な症状が現れます。原因となる薬物によって症状は異なりますが、例えば睡眠薬や抗不安薬では、不眠、不安、手の震え、発汗、けいれん発作などが起こります。オピオイド系鎮痛薬では、体の痛み、下痢、悪寒などもみられます。 - 身体合併症:
注射器の回し打ちによるHIVやC型肝炎などの感染症のリスクがあります。また、薬物の影響で栄養状態が悪化したり、生活が不規則になったりすることで、様々な体の不調をきたします。
行動や生活の変化
- 薬物中心の生活:
薬物を手に入れること、使用すること、その効果から回復することに多くの時間や労力を費やすようになります。 - 社会的役割の変化:
仕事の欠勤や失業、学業の断念、家庭内での役割を果たせなくなるなど、社会生活に大きな支障が出ます。 - 人間関係の変化:
これまで大切にしていた友人や家族との関係が悪化したり、薬物を使う仲間との付き合いを優先したりします。 - 金銭問題:
薬物を購入するために多額のお金が必要になり、借金をしたり、犯罪行為に手を染めてしまったりすることもあります。

3. 原因やきっかけ
依存症は「薬物」「人」「環境」の3つの輪が重なって起こります
薬物依存症は、特定の原因一つだけで発症するわけではありません。**「①薬物そのものが持つ依存性」「②ご本人の心身の状態」「③薬物をとりまく環境」**という3つの要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
1. 薬物の要因
薬物には、脳の報酬系と呼ばれる部分に作用し、快感や多幸感、あるいは不安や苦痛からの解放感をもたらす作用があります。この効果が強烈で、すぐに効果が現れ、作用時間が短い薬物ほど、精神的な依存(「またあの感覚を味わいたい」という欲求)が形成されやすいと言えます。また、使用を続けることで耐性(薬物が効きにくくなること)や身体依存(薬が切れると離脱症状が出ること)を生じやすい薬物も、依存を深刻化させる要因となります。
2. 人の要因
もともとの性格傾向(刺激を求めやすい、衝動的になりやすいなど)や、他の精神疾患(うつ病、不安障害、発達障害など)の存在が、依存症のリスクを高めることがあります。特に、生きづらさやストレスを抱えている人が、その苦痛を和らげるために薬物を使い始める「自己治療」のケースは少なくありません。また、過去の辛い体験(トラウマ)が背景にあることも指摘されています。
3. 環境の要因
薬物が手に入りやすい環境(違法薬物の売人とのつながり、複数の病院から薬をもらえる状況など)は、依存症の大きなリスクです。また、家庭や職場でのストレス、孤立感、周囲に薬物使用を勧める仲間がいることなども、依存症のきっかけや維持要因となります。特に、家族が依存症の問題を隠そうとしたり、本人の代わりに後始末をしたりすることで、結果的に本人の問題解決を遅らせてしまう「イネイブリング」という関わりも、回復を妨げる要因となります。
4. 診断の流れ
丁寧な問診から治療の第一歩が始まります
薬物依存症の診断は、主に問診によって行われます。身体疾患との区別や合併症の確認のために、血液検査や画像検査などを行うこともあります。
ステップ1:問診
医師がご本人やご家族から、以下のような内容を詳しくお伺いします。
- 使用している薬物の種類、量、頻度、期間
- 薬物を使用するきっかけや状況
- 薬物によって生活にどのような支障が出ているか(仕事、家庭、人間関係、健康など)
- やめようと試みた経験の有無
- 離脱症状の経験
- これまでの病歴や現在の健康状態
これらの情報を、DSM-5-TR や ICD-11 といった国際的な診断基準に照らし合わせて、診断を行います。DSM-5-TRでは、過去12ヶ月間に11項目のうち2項目以上が当てはまると「物質使用障害」と診断されます。
ステップ2:スクリーニングテスト
問診の補助として、DAST(薬物乱用スクリーニングテスト) などの質問票を用いることがあります。これにより、ご本人が抱える問題をより客観的に評価することができます。
ステップ3:各種検査
- 尿検査:
現在、体内に薬物が残っているかを確認します。 - 血液検査:
薬物の影響による肝機能障害や、注射の回し打ちによる感染症(HIV、B型・C型肝炎など)の有無を調べます。 - 画像検査(CT、MRIなど):
薬物による脳への影響や、他の身体疾患の可能性を調べるために行うことがあります。
診断は、一度で確定するとは限りません。治療を進める中で、他の精神疾患が合併していることがわかるなど、診断が見直されることもあります。大切なのは、ご自身の状況を正直に医師に伝え、一緒に治療方針を考えていくことです。
5. 主な治療法
回復の柱は「心理社会的治療」と「環境調整」です
薬物依存症の治療は、「もう二度と使わない」という本人の決意だけで成功するものではありません。専門的なアプローチを組み合わせた、包括的な治療が必要です。違法薬物の場合、治療の目標は「断薬」が唯一ですが、処方薬の場合は、医師の管理のもとで安全に減薬・中止を目指します。
心理社会的治療
これが治療の中心となります。様々なプログラムを通して、薬物を使わない生き方を学び、再発を防ぐスキルを身につけます。
- 認知行動療法(CBT):
薬物を使いたくなる状況(引き金)や、その時の自分の考え方・感情のパターンに気づき、薬物を使わない別の対処法(コーピングスキル)を身につける練習をします。 - SMARPP(スマープ:
深刻な薬物依存症者に対するリハビリテーションプログラム):日本の実情に合わせて開発された集団療法プログラムです。ワークブックを使い、依存症についての正しい知識、再発のサインへの気づき、渇望への対処法などを学びます。 - 動機づけ面接:
本人が「変わりたい」という気持ちを自ら引き出せるように、治療者が寄り添いながら対話を進める面接法です。 - 自助グループへの参加:
NA(ナルコティクス・アノニマス) や DARC(ダルク) といった、同じ問題を抱える仲間たちの集まりに参加します。そこでは、匿名で安心して自らの体験を語り、分かち合うことで、孤独感を和らげ、回復へのモチベーションを維持します。

環境調整と家族への支援
ご本人が回復に専念できるよう、環境を整えることも重要です。
- 家族への支援(CRAFTなど):
依存症は「家族の病」とも言われます。ご家族が依存症について正しく学び、本人への適切な接し方を身につけることで、家庭が回復を後押しする安全な場所になります。CRAFT(コミュニティ強化と家族トレーニング)は、ご家族が本人をうまく治療につなげるための具体的なコミュニケーションスキルを学ぶプログラムです。 - 入院治療:
離脱症状が非常に重い場合、心身の状態が悪化している場合、自殺のリスクが高い場合、あるいは自宅ではどうしても薬物との関係を断ち切れない場合などには、一時的に入院して完全に薬物を断つ環境で集中的な治療を行います。また、SMARPPを受けるためにそのまま3ヶ月間程度の入院を継続することが多いです(プログラムを全うした方が明らかに退院後の再使用のリスクが低下します)。
薬物療法
薬物依存症の治療において、薬物療法はあくまで補助的な役割です。
- 離脱症状の緩和:
離脱症状が辛い時期に、それを和らげるための薬を使用することがあります。 - 合併している精神疾患の治療:
うつ病や不安障害などを合併している場合、その治療薬が結果的に薬物への欲求を減らすことにつながる場合があります。 - 渇望を抑える薬:
オピオイド依存症に対しては、渇望を抑えたり、再使用した際の多幸感を減らしたりする薬(ナルトレキソンなど)があります。しかし、覚醒剤や大麻などの依存症に直接効く「特効薬」は、現在のところ開発されていません。

さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>
6. 回復や再発予防について
再発は失敗ではなく、回復の一部です
薬物依存症からの回復は、長い道のりです。薬をやめ続けていても、ふとしたきっかけで「使いたい」という渇望が湧き起こり、再び使用してしまうこと(スリップ)は珍しくありません。
大切なのは、スリップを「もうダメだ」という失敗と捉えるのではなく、「回復の過程の一部」と理解することです。なぜスリップしてしまったのかを冷静に振り返り、「次はどうすれば同じ状況を避けられるか」「渇望が起きたときに、どう対処すればよかったのか」を学び、次の回復への糧にすることが重要です。
再発しやすい状況を知っておく(HALT)
再発の引き金になりやすい状況として、その頭文字をとって「HALT(ハルト)」が知られています。
- Hungry(空腹)
- Angry(怒り)
- Lonely(孤独)
- Tired(疲れ)
お腹が空いている時、何かに腹を立てている時、孤独を感じる時、疲れている時は、判断力が鈍り、渇望に負けやすくなります。このような状態を自覚し、意識的に避ける工夫(例:孤独を感じたら自助グループの仲間に電話する)が再発予防につながります。
回復を支えるサポートシステム
回復の道を一人で歩き続けるのは困難です。治療者、家族、自助グループの仲間など、様々なサポートを活用することが不可欠です。
- 定期的な通院:
医師やカウンセラーと定期的に面談し、自分の状態を客観的に見つめ直す機会を持ちます。 - 自助グループへの継続参加:
回復し続けている仲間の姿は、大きな励みになります。オンラインミーティングも普及しており、参加しやすくなっています。 - 新しい楽しみや生きがいを見つける:
薬物を使っていた時間を、スポーツや趣味、ボランティア活動など、別の健康的で充実した活動に置き換えていくことも、回復を支える大きな力となります。
回復とは、単に薬物をやめることだけではありません。薬物を使わなくても、穏やかで充実した生活を送れるようになること、それが本当の意味での回復です。
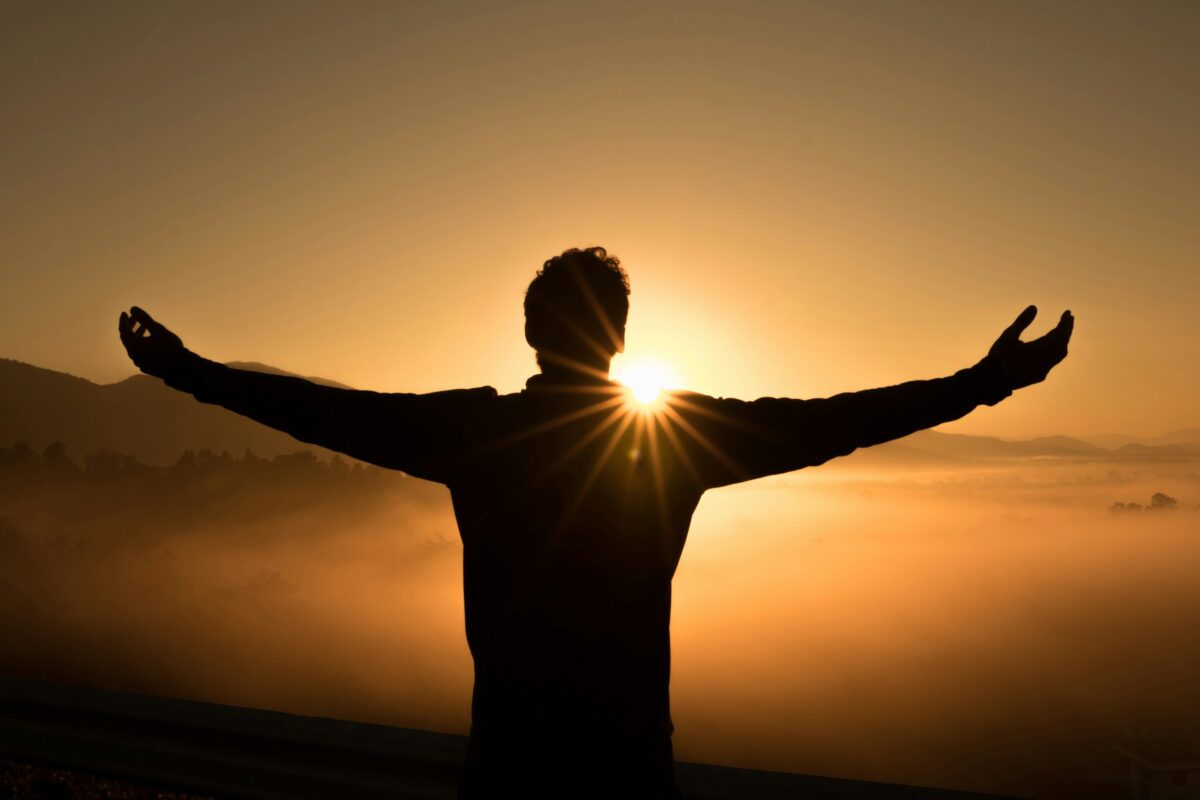
7. 患者への接し方(家族や同僚向け)
大切なのは「突き放さない」けれど「肩代わりしない」関わりです
ご家族や職場の同僚など、身近な人が薬物依存症かもしれないと気づいた時、どう接すればよいか戸惑うのは当然です。ご本人を追い詰めず、かつ、ご自身の生活も守るための関わり方のポイントを、具体的な言葉かけと共に解説します。
基本姿勢:病気を理解し、本人を責めない
まず最も大切なのは、依存症は本人の「意志の弱さ」や「だらしなさ」が原因ではなく、「病気」なのだと理解することです。
やってはいけない対応
- 叱責・説教:
「なぜやめられないんだ!」「あなたのせいで皆が迷惑している!」と感情的に責めるのは逆効果です。本人の罪悪感や孤立感を深め、さらに薬物に逃避させる原因になりかねません。 - 問題の肩代わり(イネイブリング):
本人が薬物を使ったことで生じた問題(借金の返済、会社への欠勤連絡など)を、周りが解決してしまうことです。一見、優しさに見えますが、本人が問題に直面する機会を奪い、結果的に依存を長引かせてしまいます。 - 監視・コントロール:
本人の行動を常に監視したり、無理やり薬を捨てさせたりしても、根本的な解決にはなりません。信頼関係を損ない、本人が隠れて使用するようになるだけです。
具体的な対応:I(アイ)メッセージで懸念を伝える
本人に気持ちを伝えるときは、主語を「あなた(You)」ではなく「私(I)」にする「I(アイ)メッセージ」を心がけましょう。「あなたは~すべきだ」という言い方は相手を追い詰めますが、「私は~と感じている」と伝えることで、相手も話を聞き入れやすくなります。
望ましい対応
- 懸念を伝える:
「(あなたが薬を使うと)私はとても心配だ」「(最近、体調が悪そうで)私はあなたのことが気がかりだ」 - 提案する:
「私と一緒に、一度専門の相談窓口に電話してみない?」「もしよかったら、私も一緒に病院についていくよ」 - 境界線を引く:
「薬物を買うためのお金は貸せない。でも、治療のための費用なら協力したい」「酔っている状態のあなたとは、大事な話はできない。落ち着いてから話そう」
違法薬物使用者への対応
ご本人が使用しているのが違法薬物だと知った場合、恐怖や混乱を感じるかもしれません。しかし、基本の対応は同じです。
- 通報義務について:
医師には麻薬中毒者を診断した場合の届出義務がありますが、ご家族や同僚に警察への通報義務はありません。本人の同意なく通報することは、信頼関係を決定的に破壊し、治療の機会を永遠に失わせる可能性があります。 - 自傷他害の危険がある場合:
薬物の影響で、明らかに自分や他人を傷つける危険が迫っている場合(暴れている、自殺をほのめかしているなど)は、ためらわずに警察(110番)や救急(119番)に連絡してください。これは通報ではなく、命を守るための緊急避難です。精神保健福祉法に基づき、警察官が専門医療機関へつなぐ制度もあります。
最も大切なのは、一人で抱え込まないことです。精神保健福祉センターや保健所、民間の支援団体など、ご家族や周囲の方が相談できる窓口があります。専門家の助言を得ながら、冷静に対応することが、ご本人にとってもご家族にとっても、回復への最も確実な道筋となります。

8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、薬物依存症(物質使用障害)でお悩みのご本人、そしてご家族をサポートするための体制を整えています。
医師による専門的な診療と助言
当院では、精神科専門医が丁寧に診察を行い、国際的な診断基準に基づいた的確な診断を行います。その上で、お一人お一人の状況に合わせて、回復に向けた治療計画を一緒に考えていきます。
- 薬物を使わない生き方のための助言・指導:
認知行動療法の考え方に基づき、薬物への渇望を乗り切るための具体的な対処法や、再発を予防するための生活習慣について、専門的な助言を行います。 - 合併している精神疾患の治療:
うつ病、不安障害、発達障害などが依存症の背景にある場合、それらの治療を並行して行うことで、結果的に依存症からの回復を大きく後押しします。 - 処方薬の調整・減薬サポート:
睡眠薬や抗不安薬などの処方薬依存でお困りの方には、安全に減薬・断薬ができるよう、専門的な知識に基づいて薬物調整をサポートします。 - ご家族からの相談:
ご本人への適切な接し方や、利用できる社会資源についてなど、ご家族が抱えるお悩みにも丁寧にお応えします。ご家族だけでご相談に来ていただくことも可能です。
各種機関との連携
薬物依存症は外来通院のみで回復することは非常に困難です。専門機関での入院治療を経て外来通院ができるようになるくらいのイメージです。また、そのためには、医療機関だけでなく、様々な社会資源との連携が不可欠です。当院は薬物依存症の専門機関ではありません。当院での治療が困難な場合は、必要に応じて以下の専門機関と連携し、包括的なサポートを提供します。
- 専門治療プログラム(SMARPPなど)実施機関への紹介
- 自助グループ(NA、DARCなど)に関する情報提供
- 精神保健福祉センターや保健所との連携
- 薬物依存症専門の入院施設を持つ医療機関への紹介
現在、当院では心理士によるカウンセリングは準備中ですが、医師による精神療法的な関わりの中で、ご本人の回復を力強くサポートいたします。一人で、あるいはご家族だけで悩まず、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

薬物依存症の専門病棟がある日本の医療機関
薬物依存症の専門的な入院治療が可能な医療機関は全国にありますが、数は限られています。以下に代表的な機関と、情報を探す際に役立つリンクを添付します。症状が重く、生活に深刻な支障が生じているような、入院が必要な方は、下記の医療機関に直接相談することをお勧めします。
- 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター病院(東京都小平市)
- 薬物依存症の専門病棟があり、研究に基づいた最先端の治療を提供しています。
- https://www.ncnp.go.jp/hospital/
- 都道府県立精神保健福祉センター・精神科医療センター
- 多くの都道府県で、薬物依存症の専門外来や相談窓口、専門病棟を設置しています。代表的なものとして以下があります。
- 東京都立松沢病院(東京都世田谷区):薬物依存症専門外来(AP外来)や入院プログラムが充実しています。
- 神奈川県立精神医療センター(神奈川県横浜市):アルコール・薬物依存症の専門治療で長い歴史と実績があります。
- 特定非営利活動法人 全国薬物依存症者家族会連合会(全国家族会)
- 家族の立場から、全国の相談先や医療機関の情報を提供しています。
- https://www.yakkaren.com/
- 一般財団法人 日本ダルク
- リハビリ施設であるダルクは医療機関ではありませんが、各地域の専門医療機関と密接に連携しています。お近くのダルクに相談することで、適切な医療機関の情報を得られる場合があります。
- http://darc-ic.com/
※受診や入院の可否は、各機関の状況やご本人の状態によって異なりますので、必ず事前に各医療機関にお問い合わせください。
さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



