幻覚や妄想などの症状により、現実との区別がつきにくくなる脳の病気です。お薬と専門家によるサポートで回復を目指せます。一人で抱え込まず、ご相談ください。
思考や感情のまとまりが難しくなる脳の機能的な病気
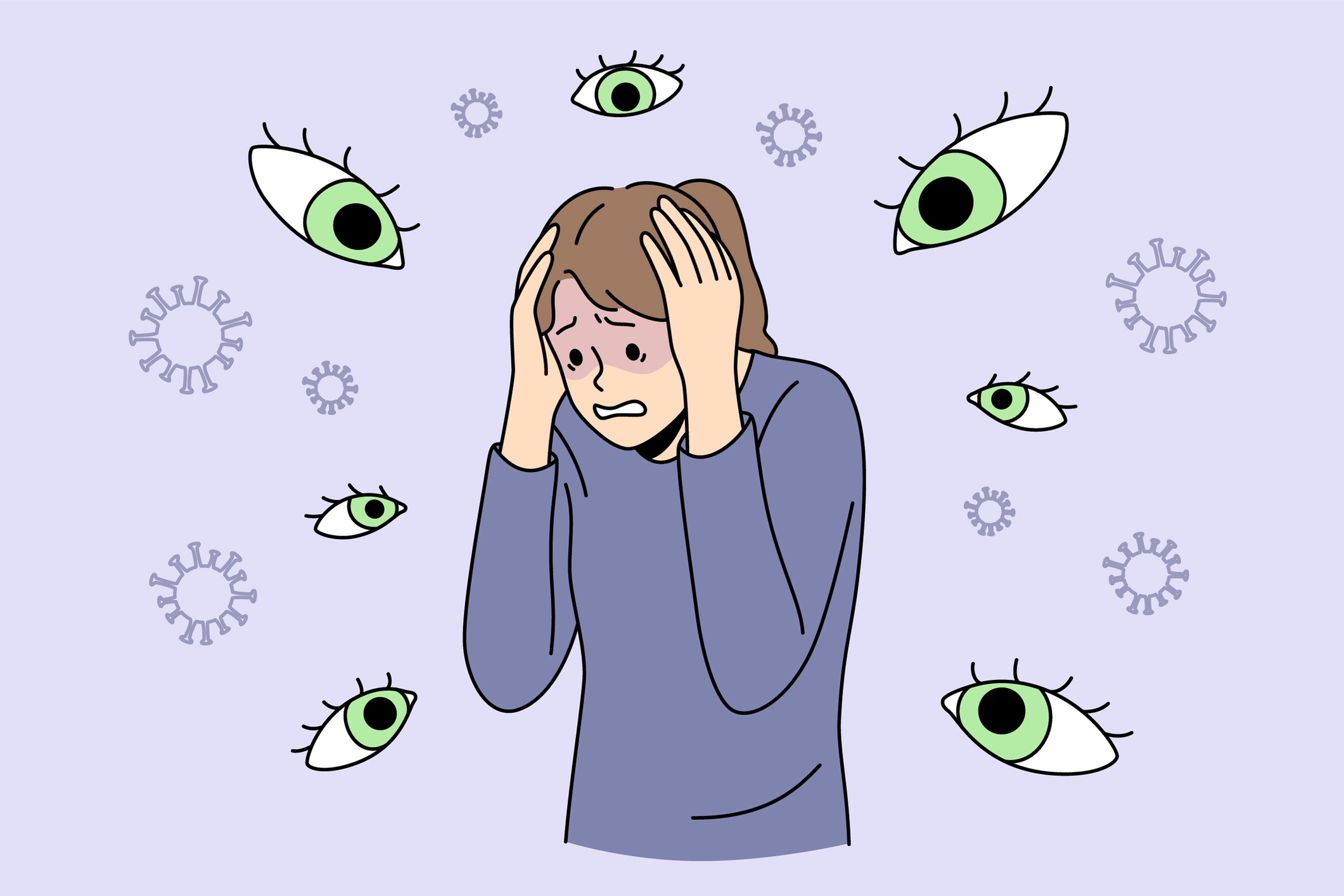
- 幻覚(幻聴)
- 被害妄想
- 人に見られている気がする
- 思考の混乱
- 意欲の低下
- 感情の平板化
- 引きこもり
- 認知機能の低下
- 興奮や苛立ち
- 不眠
統合失調症
-難解な精神疾患をわかりやすく解説-
「誰かに悪口を言われている気がする」「考えがまとまらない」…もしかしたら、それは統合失調症のサインかもしれません。統合失調症は、約100人に1人がかかるといわれる、決して珍しくない脳の病気です。考えや気持ちをまとめ、現実を正しく認識する「統合」する機能がうまくいかなくなる(失調する)ことから、この名前がつけられました。
かつては「精神分裂病」と呼ばれていましたが、病気への誤解を招きやすいことから2002年に「統合失調症」へと名称が変更されました。適切な治療とサポートによって、多くの患者さんが回復し、自分らしい生活を取り戻しています。このページでは、統合失調症とはどのような病気なのか、症状や原因、そして回復への道のりについて、分かりやすく解説していきます。

1. 統合失調症はどんな病気?
統合失調症は、考えや気持ち、行動をうまくまとめることが難しくなる「脳の機能障害」です。脳内の情報をやり取りする神経伝達物質(特にドーパミンなど)のバランスが崩れることが関係していると考えられています。
決して「性格の問題」や「心の弱さ」が原因ではありません。誰もがかかる可能性のある病気であり、高血圧や糖尿病のように、お薬や専門家のサポートによって症状をコントロールし、回復していくことが可能です。
たとえるなら、脳という司令塔のコンピューターが、ウイルスに感染して一時的にうまく作動しなくなった状態に似ています。外部からの情報(現実)と、自分の内部からの情報(自分の考え)をうまく統合処理できなくなり、混乱が生じてしまうのです。しかし、適切な「ウイルス対策ソフト」(治療)を使えば、コンピューターは再び正常に動き出すことができます。
2. 主な症状
統合失調症の症状は、大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けられます。これらすべての症状が一度に出るわけではなく、時期によって目立つ症状が異なります。
- 陽性症状:
本来ないはずのものが出現する 健康な時にはなかった状態が、まるで「プラス」されたように現れる症状です。急性期に目立ちやすく、お薬の効果が出やすいのが特徴です。- 幻覚・幻聴:
現実にはないものをあるように感じることです。特に、自分の悪口や噂、命令するような声が聞こえる「幻聴」が多くみられます。 - 妄想:
どう考えても現実的ではないことを、強く信じ込んでしまう状態です。 「誰かに狙われている」(被害妄想)、「街ですれ違う人が皆自分のことを見ている」(注察妄想)などが代表的です。 - 思考の混乱:
考えにまとまりがなくなり、話が飛んだり、会話のつじつまが合わなくなったりします。
- 幻覚・幻聴:
- 陰性症状:
本来あるはずのものが失われる 感情や意欲といった、ごく自然な心の働きが「マイナス」されたように失われてしまう症状です。急性期を過ぎた後、長く続くことがあります。- 感情の平板化:
喜怒哀楽の表現が乏しくなり、表情が硬くなります。 - 意欲の低下:
何かをする気力がなくなり、一日中ごろごろして過ごしたり、身の回りのことに関心がなくなったりします。 - 引きこもり:
人との交流を避け、自分の世界に閉じこもりがちになります。
- 感情の平板化:
- 認知機能障害:
生活のしづらさにつながる 情報を処理したり、記憶したり、注意を集中したりといった、社会生活を送る上で大切な機能が低下する症状です。- 注意・集中力の低下:
集中力が続かず、話の内容が頭に入らなかったり、仕事や勉強でのミスが増えたりします。 - 記憶力の低下:
新しいことを覚えたり、過去の出来事を思い出したりすることが苦手になります。 - 実行機能の障害:
物事の段取りを考え、計画的に行動することが難しくなります。
- 注意・集中力の低下:

3. 原因やきっかけ
統合失調症のはっきりとした原因はまだわかっていませんが、一つの原因で発症するのではなく、いくつかの要因が重なり合って発症すると考えられています。これを「脆弱性(ぜいじゃくせい)・ストレスモデル」と呼びます。
| 要因 | 内容 | 具体例 |
| 生物学的な脆弱性 | もともと持っている、ストレスに対する脳の敏感さや情報処理の特性。 遺伝的な要因も関係しますが、遺伝だけで決まるわけではありません。 | ・脳の神経伝達物質(ドーパミンなど)のバランスの乱れやすさ ・脳の発達段階でのわずかな形態的・機能的な特徴 |
| 心理・社会的なストレス | 発症の引き金となる環境的な要因。 | ・持続的なストレス: 家庭や職場での人間関係の悩み ・突発的なライフイベント: 進学、就職、結婚、失恋、近親者の死など |
生まれつきコップの大きさが人それぞれ違うように、ストレスを受け止める器の大きさには個人差があります。もともとストレスに敏感な「脆弱性」という器を持っている人が、そこに進学や就職、人間関係の悩みといった「ストレス」という水が注がれ、器から水があふれてしまった時に発症する、というイメージです。
4. 診断の流れ
精神科の診断は、血液検査や画像検査のように数値で「異常」を示すことが難しいため、専門医による丁寧な問診が最も重要になります。
- ご本人・ご家族からの聞き取り(問診):
- いつから、どのような症状で困っているか
- 症状によって日常生活にどのような支障が出ているか
- これまでの生活の様子や、大きな環境の変化はなかったか
- ご家族から見たご本人の様子の変化
- 国際的な診断基準との照らし合わせ:
医師は、問診で得られた情報を、米国精神医学会の「DSM-5-TR」やWHO(世界保健機関)の「ICD-11」といった国際的な診断基準に照らし合わせて、慎重に診断を行います。 - 他の病気の除外:
薬物(覚醒剤など)の使用や、甲状腺機能亢進症などの身体疾患が原因で似たような症状が出ることがあるため、必要に応じて血液検査や頭部CT・MRIなどの画像検査を行い、他の病気の可能性がないかを確認します。
5. 主な治療法
統合失調症の治療は、「薬物療法」と「心理社会的療法」を組み合わせた包括的なアプローチが基本となります。これらを車の両輪のようにバランスよく進めることで、症状を安定させ、再発を防ぎ、その人らしい生活を取り戻すことを目指します。
1.薬物療法
- 脳の神経伝達物質のバランスを整える抗精神病薬が中心となります。
- 近年では副作用が少なく、陰性症状や認知機能障害にも効果が期待できる非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)が主流です。
- 急性期の激しい症状を抑えるだけでなく、症状が安定した後の再発を予防するためにも、お薬を継続して飲み続けることが非常に重要です。
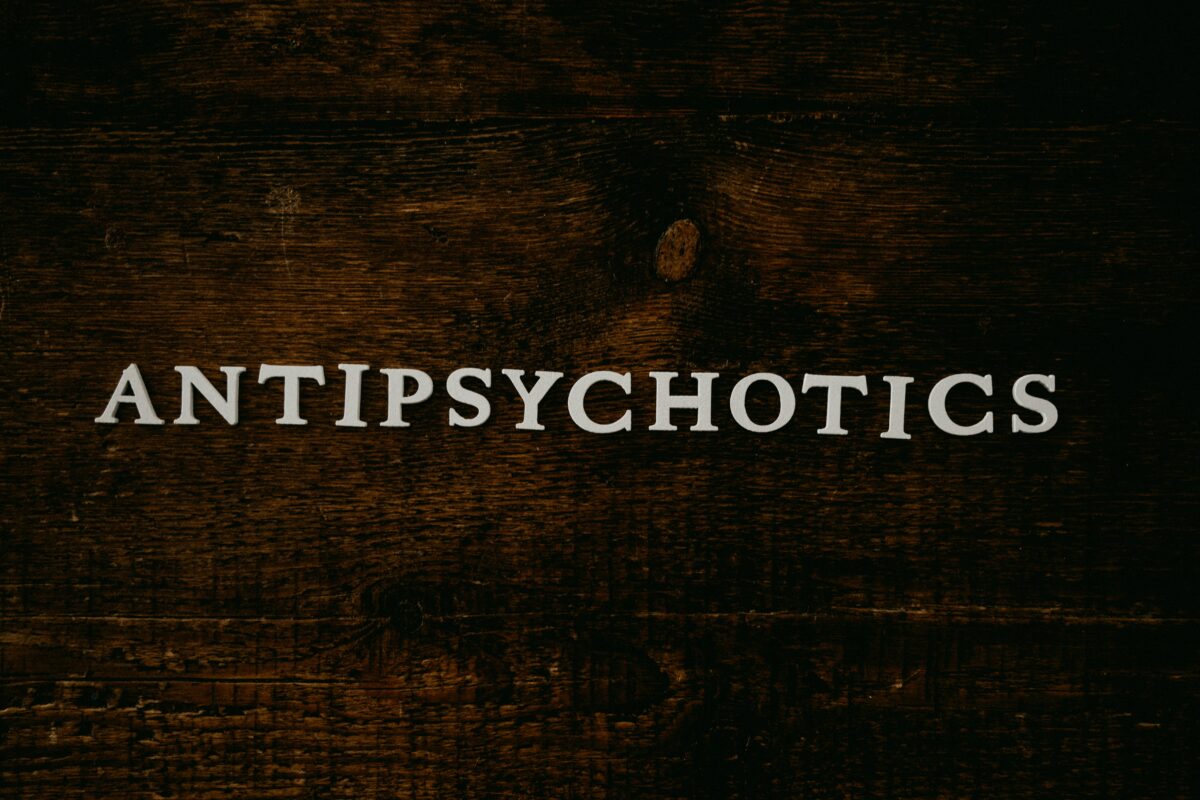
さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>
2.心理社会的療法
- お薬だけでなく、精神科医や心理士、精神保健福祉士、作業療法士などの専門家によるサポートも回復に不可欠です。
- 病気や薬について正しく理解する心理教育、ストレスへの対処法を学ぶ認知行動療法、対人関係の練習を行うSST(社会生活技能訓練)、日中の活動の場としてのデイケアなど、様々なプログラムがあります。

6. 回復や再発予防について
統合失調症は、急性期、消耗期(休息期)、回復期という段階を経て回復していきます。症状の波はありますが、焦らずに治療を続けることが大切です。
- 急性期(発症直後):
幻覚や妄想といった陽性症状が激しく現れる時期です。不安や混乱が強く、ご本人は大変な苦しさを感じています。まずはゆっくりと休養をとり、お薬で症状を和らげることが最優先です。 - 消耗期(休息期):
激しい症状が治まると、心身ともにエネルギーを使い果たした状態になります。意欲がなくなり、眠ってばかりいることもありますが、これは回復のために必要な休息期間です。焦らずにゆっくりと休める環境を整えましょう。 - 回復期:
少しずつ元気が出てきて、身の回りのことや将来のことに関心が向くようになります。この時期に、病気について学んだり、ストレスへの対処法を身につけたり、デイケアなどで少しずつ活動の幅を広げていくことが、再発予防と社会復帰につながります。

統合失調症は再発しやすい病気ですが、再発のサインに早く気づき、適切に対処することで、症状の悪化を防ぐことができます。
<再発のサインの例>
- 眠れなくなる、昼夜逆転する
- イライラしやすくなる、焦りを感じる
- 音や光に敏感になる
- 食欲がなくなる
- 人との交流を避けるようになる
このような変化が見られたら、無理をせず、早めに主治医に相談することが大切です。お薬の量を自己判断で減らしたり中断したりすることは、再発の大きな原因となりますので、必ず主治医の指示に従ってください。
7. 患者さんへの接し方
ご家族や職場の同僚など、周りの方の理解とサポートは、患者さんの回復にとって大きな力となります。ここでは、患者さんと接する上での大切なポイントを、具体的な理由や会話例と共にご紹介します。
【基本的な心構え】
- 病気を理解し、味方であることを伝える
- 理由: 患者さんは、幻覚や妄想の世界に混乱し、「誰にも理解してもらえない」という強い孤立感や不安を抱えています。「あなたの味方だよ」という安心感のあるメッセージが、治療への第一歩となります。
- 良い対応例: 「つらそうだね。一人で抱え込まないで、いつでも話を聞くよ」「病気のことはよく分からないけど、あなたの力になりたいと思ってる」
- 避けるべき対応: 「気のせいだよ」「考えすぎだ」と症状を否定する。
- 批判や説教、励ましを避ける
- 理由: 意欲の低下や引きこもりは、病気の症状によるもので、本人の怠けや甘えではありません。批判されたり、「頑張れ」と励まされたりすると、できない自分を責めてしまい、かえって追い詰められてしまいます。
- 良い対応例: まずは本人のペースでゆっくり休めるように見守る。「何か手伝えることはある?」と、具体的なサポートを提案する。
- 避けるべき対応: 「いつまで寝てるんだ」「しっかりしろ」と叱咤する。「頑張ればできる」と根性論で励ます。
【具体的な対応のヒント】
| 困りごと | 理由と背景 | 対応のヒントと会話例 |
| 幻覚や妄想について話す | 患者さんにとって、幻覚や妄想は「現実」です。 否定されると、「この人も自分のことを分かってくれない」と心を閉ざしてしまいます。 | まずは気持ちを受け止める: 「そうか、そんな声が聞こえるんだね。 それは怖いね/つらいね」と、話の内容ではなく、その時の感情に寄り添います。 肯定も否定もしない: 「私には聞こえないけど、あなたには聞こえているんだね」と、事実関係には触れず、本人の体験として受け止める姿勢が大切です。 |
| 会話がかみ合わない・独り言が多い | 思考の混乱や、幻聴との対話が原因です。 本人は一生懸命伝えようとしていますが、考えがまとまりにくくなっています。 | シンプルで分かりやすい言葉で話す: 一度に多くの情報を伝えず、「ご飯にする?」「お風呂に入る?」のように、短く具体的な言葉で、穏やかに話しかけます。 独り言はそっと見守る: 無理に会話を続けようとせず、本人が落ち着けるように距離をとり、見守りましょう。 |
| 引きこもっている・何もしない | 陰性症状による意欲の低下が原因です。 心身のエネルギーが枯渇している状態で、無理に何かをさせようとすると、本人を追い詰めてしまいます。 | 焦らず、ゆっくり休ませる: 「今はエネルギーを充電する大切な時期」と理解し、安心して休める環境を整えましょう。 小さなことから誘ってみる: 少し元気が出てきたら、「一緒にお茶を飲まない?」「少しだけ散歩に行かない?」など、負担の少ないことから誘ってみましょう。 断られても、責めずに「そっか、また今度誘うね」と伝えることが大切です。 |
| お薬を飲みたがらない | 「自分は病気ではない」という病識の欠如や、「薬で操られる」といった妄想、副作用への不安などが原因として考えられます。 | まずは理由を聞く: 頭ごなしに叱るのではなく、「どうしてお薬を飲みたくないの?」と、本人の気持ちや考えを尋ねましょう。 医師に相談するよう促す: 「お薬のことで心配なことがあるなら、次の診察で先生に相談してみようか」と、専門家への橋渡しをしましょう。 副作用がつらい場合は、お薬の変更で改善することもあります。 |
8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、統合失調症の患者さんとそのご家族が、安心して治療に取り組めるようサポートいたします。
- 専門医による丁寧な診断と治療:
統合失調症の臨床経験の豊富な日本精神神経学会専門医が、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な薬物療法と治療計画をご提案します。 - 医師による助言と指導:
薬物療法だけでなく、日常生活の送り方やストレスへの対処法などについて、医師が丁寧に助言・指導を行います。ご家族からのご相談にも応じ、患者さんへの接し方などについて一緒に考えていきます。 - 各種支援制度のご紹介:
症状によって仕事や生活に支障が出た場合、自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳、障害年金などの公的な支援制度を利用できる場合があります。精神保健福祉士が、これらの制度の利用についてのご相談に応じ、手続きをサポートします。

※現在、心理士によるカウンセリングは準備中でが、今後、カウンセリング部門も導入予定です。また、入院や精密検査などをご希望の方には、連携する他の専門機関をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



