発達障害は生まれつきの脳機能の偏りによる特性です。ご自身の特性を理解し、あなたらしく過ごせるよう、具体的な症状や周りの接し方をわかりやすく解説します。
生まれ持った脳の個性が輝くために

- 対人関係の難しさ
- 強いこだわり
- 不注意・忘れっぽさ
- 落ち着きのなさ
- 特定の感覚の過敏さ・鈍感さ
- 物事の段取りの苦手さ
1. 発達障害とは?
「うちの子、ちょっと変わってる?」「仕事のミスが多くて、人間関係がうまくいかない…」そんな風に感じたことはありませんか?もしかしたら、それは「発達障害」という、生まれ持った脳の働きの個性によるものかもしれません。
発達障害は、けっして育て方や本人の努力不足が原因ではありません 。生まれつきの脳機能の発達に偏りがあるために、行動や感情のコントロール、対人関係、学習などに困難さが生じる状態です 。この特性は一人ひとり異なり、まるで虹の色がなだらかに変化するように、様々なグラデーションがあるため「スペクトラム」と呼ばれます 。
特に代表的なのが、「自閉スペクトラム症(ASD)」と「注意欠如・多動症(ADHD)」です。以前はこの二つは同時に診断されることはありませんでしたが、現在では併存することが広く知られています 。大切なのは、「〇〇障害」という診断名にこだわることよりも、ご自身やお子さんがどのような特性を持っているのかを正しく理解し、その個性に合わせた環境を整えていくことです 。
大人の発達障害
子どもの頃は目立たなかった特性が、就職や結婚など、環境が大きく変わり、より複雑な対人関係や臨機応変な対応が求められるようになって初めて表面化することがあります 。これが「大人の発達障害」です。周囲に理解されず、「変わった人」「仕事ができない人」と誤解されたり、ご自身でも「なぜ自分だけうまくいかないんだろう」と悩み、うつ病や不安障害などの二次障害につながることも少なくありません 。

2. 主な症状
ASDとADHDの主な症状を解説します。どちらか一方だけが当てはまることもあれば、両方の特性を併せ持つこともあります。
自閉スペクトラム症(ASD)の主な症状
ASDの特性は、大きく分けて「対人関係やコミュニケーションの難しさ」と「特定の物事への強いこだわり」の2つです 。
対人関係やコミュニケーションの難しさ
- 相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取るのが苦手で、「空気が読めない」と言われることがある 。
- 冗談や皮肉、曖昧な表現を文字通りに受け取ってしまうことがある 。
- 視線を合わせ続けるのが苦手だったり、逆に相手をじっと見つめすぎたりする 。
- 会話のキャッチボールが苦手で、一方的に自分の興味のあることばかり話してしまうことがある 。
- 集団での雑談など、明確な目的のない会話が苦痛に感じることがある。
特定の物事への強いこだわり・感覚の特性
- 特定の手順やルールに強くこだわり、予定が急に変わると混乱したり、不安になったりする 。
- 好きなことには時間を忘れて没頭する(過集中)が、興味のないことには集中しにくい 。
- くるくる回るものを見る、特定の音を聞くなど、同じ行動を繰り返すことで安心感を得る。
- 感覚の過敏さ(または鈍感さ)があり、特定の音、光、匂い、肌触りなどを非常に不快に感じたり(感覚過敏)、逆に痛みや暑さ・寒さを感じにくかったりする(感覚鈍麻)ことがある 。偏食の原因が感覚過敏であることも多いです 。

注意欠如・多動症(ADHD)の主な症状
ADHDの特性は、「不注意」と「多動性・衝動性」の2つのタイプに分けられます 。
不注意
- 集中力が続かず、ケアレスミスが多い 。
- 忘れ物や失くし物が多い 。
- 話を聞いていないように見えたり、上の空になったりすることがある。
- 仕事や作業の段取りを立てるのが苦手で、後回しにしてしまう傾向がある 。
- 片付けが苦手で、部屋や机の上が散らかりやすい。
多動性・衝動性
- じっとしているのが苦手で、そわそわと体を動かしてしまう(子どもの場合、授業中に立ち歩くなど) 。
- おしゃべりが止まらなかったり、一方的に話し続けたりする 。
- 順番を待つのが苦手で、列に割り込んでしまうことがある 。
- 深く考えずに行動してしまい、思ったことをすぐに口に出してしまう 。
- 衝動的に買い物をしてしまうことがある。
大人になると、多動性は目立たなくなり、不注意の特性が残りやすいと言われています 。

その他の発達障害
限局性学習症(LD)は、知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」といった特定の能力の習得や使用に著しい困難を示す状態です 。
3. 原因やきっかけ
発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の偏りが原因であり、親の育て方やしつけ、愛情不足が原因ではありません 。脳の中でも、行動のコントロールやコミュニケーション、集中力などをつかさどる前頭前野という部分の働きが、定型発達の人とは異なると考えられています 。
遺伝的な要因も関与すると考えられていますが、特定の遺伝子だけで決まるわけではなく、様々な要因が複雑に絡み合って特性として現れるとされています 。
子どもの頃に特性が目立たなくても、大人になってから「気づく」きっかけとしては、以下のような環境の変化が挙げられます。
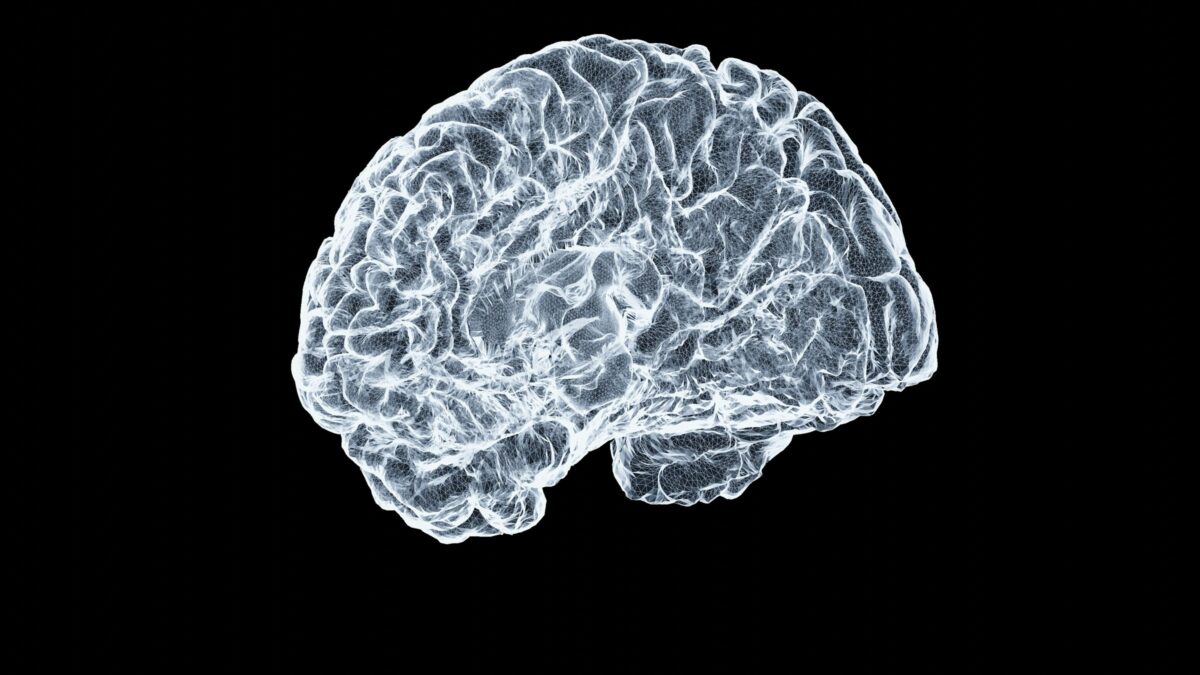
- 就職:
自分のペースで進められた学生時代と違い、職場ではチームワークやマルチタスク、臨機応変な対応、時間管理などが求められ、困難を感じやすくなる。 - 結婚・育児:
パートナーとの密なコミュニケーションや、子どもの世話など、自分のペースだけでは進められない場面が増え、ストレスを感じやすくなる。
これらの環境の変化が、それまで無意識の努力でカバーしてきた特性を表面化させ、ご自身や周囲が「発達障害かもしれない」と気づくきっかけとなるのです 。
4. 診断の流れ
「発達障害かもしれない」と思ったら、まずは専門の医療機関に相談することが第一歩です。診断は、ご自身の特性を理解し、適切なサポートを受けるための大切な手がかりとなります。
1. 問診
まず、医師がご本人やご家族から、現在困っていること、子どもの頃の様子(通知表や母子手帳なども参考にします)、学校生活や職場での様子などを詳しくお伺いします 。成人の診断であっても、幼少期の情報が非常に重要になります 。
ご本人の視点だけでなく、ご家族や職場の同僚など、客観的に見ている方からの情報も診断の助けになります。
2. 心理検査
診断の補助や治療・サポートの参考にするため、専門的な知識のある心理士による心理検査を行います。
- 知能検査(WAIS-IVなど):
得意なことと苦手なことの差(認知の偏り)を客観的に評価します 。けっして知能の高低を測るだけのものではありません。 - 質問紙検査(AQ、CAARSなど):
発達障害の特性の有無や程度を評価するためのスクリーニング検査です 。
※重要:あくまでも診断の補助情報として利用するためであり、心理検査の結果で発達障害の診断がつくわけではありません(診断はあくまでも診断基準で決まります)。
3. 総合的な診断
問診や心理検査の結果、生育歴などを総合的に検討し、国際的な診断基準であるDSM-5-TRなどに基づいて、医師が診断を行います 。
診断は、あくまでご自身の特性を理解するための一つのツールです 。診断によってご自身を責めたり、悲観したりする必要は全くありません。むしろ、苦手さの原因がわかり、具体的な対策を立てやすくなるというメリットがあります。

5. 主な治療法
発達障害の特性そのものをなくす「根本治療」の薬は、現在のところASDにはありません 。ADHDには症状を緩和する治療薬があります 。治療の目標は、症状を完全になくすことではなく、ご自身の特性と上手につきあいながら、日常生活や社会生活での困難を減らしていくことです 。
心理社会的治療
ご自身の特性を理解し、具体的な対処法を学ぶことで、生きづらさを軽減していきます。
- 心理教育:
医師や心理士から、発達障害の特性や対処法について学びます。なぜ今まで困難を感じていたのかが理解でき、自己肯定感を取り戻すことにつながります。 - 環境調整:
刺激の少ない環境を整えたり、指示を視覚的にわかりやすく伝えたりすることで、困難を減らします。- 例:口頭での指示が苦手な方には、メモや図で伝える。雑音が苦手な方には、パーテーションのある席やイヤーマフの使用を検討する。
- ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST):
対人関係を円滑にするためのコミュニケーションの技術を、ロールプレイングなどを通じて具体的に学びます。 - 認知行動療法:
物事の捉え方や考え方の癖に気づき、より柔軟な考え方ができるように練習します。二次障害であるうつ病や不安障害にも有効です。

薬物療法
ADHDの不注意や多動性・衝動性といった中核症状に対しては、薬物療法が有効な場合があります。薬を使うことで、脳内の神経伝達物質(ドパミンやノルアドレナリン)のバランスが整い、症状が緩和され、集中しやすくなったり、落ち着いて行動しやすくなったりします 。
ASDの特性そのものを改善する薬はありませんが、イライラや攻撃性、気分の落ち込み、強いこだわりなど、二次的に現れる症状に対して、薬を使用することで気持ちが安定し、穏やかに過ごせるようになることがあります 。
薬物療法は、あくまで治療の選択肢の一つであり、心理社会的治療と補助的に組み合わせて行うことが効果的です 。医師とよく相談し、ご自身に合った治療法を見つけていきましょう。
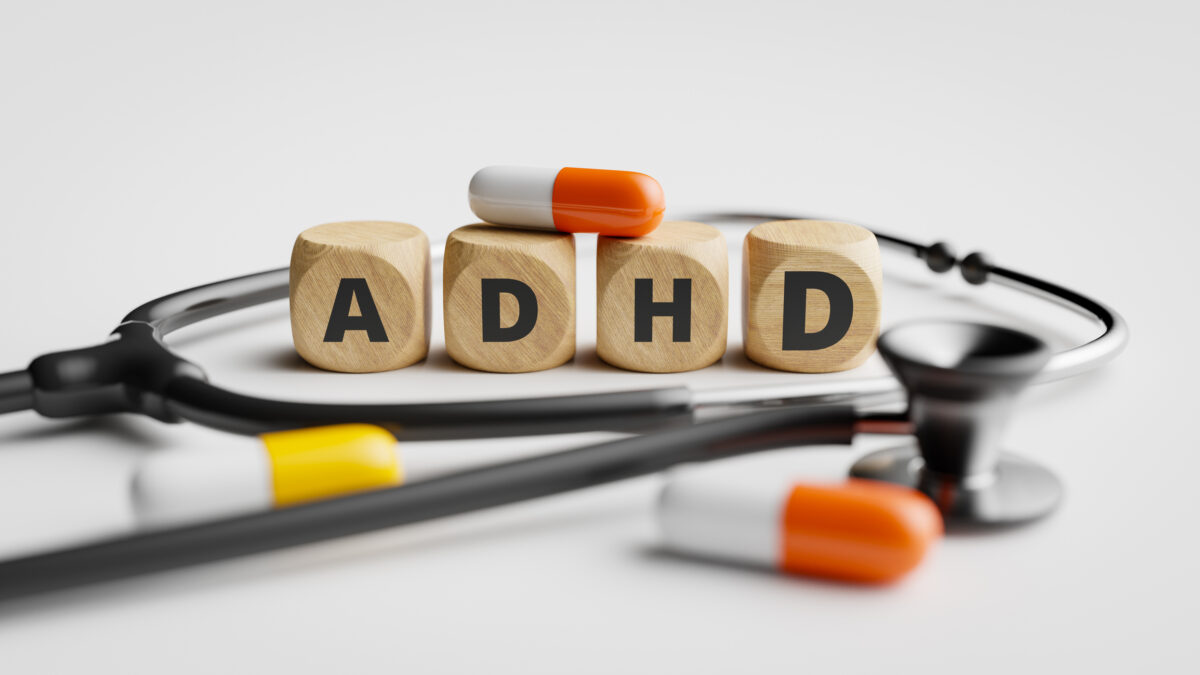
さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>
6. 回復や再発予防について
発達障害は「治る」というより「特性と上手につきあっていく」という視点が大切です。ご自身の得意なこと・苦手なことを理解し(自己理解)、周囲の人にも特性を伝えて協力を求めること(合理的配慮)、そして自分に合った環境を整えることで、困難は大きく軽減できます。
再発予防のポイント
二次障害であるうつ病や不安障害の再発を防ぐためには、ストレス管理が重要です。
- ストレスサインに気づく:
イライラ、不眠、食欲不振など、自分なりのストレスのサインを知り、早めに対処する。 - 休息を意識する:
好きなことに没頭しすぎたり(過集中)、頑張りすぎたりした後は、意識的に休息をとる。 - 完璧を目指さない:
「まあ、いいか」を心がけ、完璧主義を手放す。 - 相談できる場所を持つ:
家族や友人、主治医、カウンセラーなど、困った時に相談できる人や場所を確保しておく。
発達障害の特性は、裏を返せば素晴らしい個性や才能にもなり得ます。強いこだわりは探究心や専門性に、多動性は行動力や好奇心につながります。ご自身の特性をポジティブな力に変えていくことで、あなたらしい人生を歩むことができるのです。
7. 患者さんへの接し方
ご本人だけでなく、周りの人が発達障害の特性を理解し、適切に関わることで、ご本人の安心感につながり、能力を発揮しやすくなります。ここでは、ご家庭、学校、職場での具体的な接し方のポイントを、理由とともに解説します。
ご家族の方へ
ご家庭は、ご本人にとって最も安心できる場所であることが大切です。
| 対応策 | 具体的な接し方 | なぜ、そうするのか?(理由) |
|---|---|---|
| 1. 肯定的な言葉で具体的に褒める | 「ダメじゃない」「普通にしなさい」ではなく、「〇〇ができたね」「〇〇してくれて助かるよ」と伝える。 | 否定的な言葉は自己肯定感を下げてしまいます。 何が良くて、何がダメなのかを具体的に伝えることで、本人は次にとるべき行動を学びやすくなります。 |
| 2. 指示は短く、具体的に、一つずつ | 「ちゃんと片付けて」ではなく、「まず、机の上にある本を本棚に戻してね」と伝える。 | 曖昧な指示や一度に多くの指示は、混乱の原因になります。 何をすべきかを明確に、一つずつ伝えることで、行動に移しやすくなります 。 |
| 3. 変更は早めに、視覚的に伝える | 急な予定変更は避け、変更がある場合は、カレンダーやメモなど目に見える形で早めに伝える。 | 見通しが立つと安心できるのがASDの特性です 。 視覚的な情報は、口頭での説明よりも記憶に残りやすく、パニックを防ぐことにつながります。 |
| 4. 感覚の過敏さ・鈍感さに配慮する | 本人が嫌がる音や光、触覚などを無理強いしない。 静かで落ち着ける「クールダウンスペース」を用意する。 | 感覚の特性は、本人のわがままではありません。 不快な刺激は、心身の大きな負担になります 。 安心して過ごせる環境が、情緒の安定につながります。 |
| 5. 失敗を責めずに、一緒に工夫を考える | 忘れ物をした時に「また忘れたの?」と責めるのではなく、「どうしたら忘れにくくなるかな?玄関にメモを貼ってみる?」と一緒に考える。 | 失敗を責められる経験が続くと、挑戦する意欲を失ってしまいます。 「忘れてしまう」という特性を前提に、具体的な対策を一緒に考えることで、本人の主体性を育てます。 |
学校の先生方へ
学校は、多くの子どもにとって初めての社会生活の場です。一人ひとりの特性に合わせた配慮が、子どもの成長と自信につながります。
| 対応策 | 具体的な接し方 | なぜ、そうするのか?(理由) |
|---|---|---|
| 1. 席の配置を工夫する | 刺激の少ない教卓の前や壁際の席にする。 集中したい時にはパーテーションを使う。 | ADHDの特性がある子どもは、視覚や聴覚の刺激で集中が途切れやすいです 。 物理的に刺激を減らすことで、授業に集中しやすくなります。 |
| 2. 指示やルールの視覚化 | 一日のスケジュールや授業のルール、課題の手順などを、板書やプリントで具体的に示す。 | 口頭での指示は聞き逃したり、忘れたりしがちです。 目で見て確認できる情報は、ASDやADHDの特性を持つ子どもにとって、見通しを持って安心して行動するための重要な手がかりになります 。 |
| 3. 休憩やクールダウンの許可 | パニックになりそうな時や、集中が切れた時に、一時的に教室の外の静かな場所で休むことを許可する。 | 感覚過敏や強い不安を感じた時に、その場から離れて気持ちを落ち着ける時間と場所が必要です。 無理強いはパニックを悪化させるだけです。 |
| 4. 得意なことを活かす役割を与える | 特定の分野に強い興味を持つ子には、その知識を活かせる係活動をお願いするなど、得意なことで活躍できる場を作る。 | 苦手なことへの配慮だけでなく、得意なことを認め、伸ばす関わりが自己肯定感を育みます。 「自分はクラスの役に立っている」という感覚が、学校生活への意欲につながります。 |
| 5. 「チームとしての学校」での連携 | 担任の先生一人で抱え込まず、特別支援教育コーディネーターやスクールカウンセラー、管理職など、学校全体で情報を共有し、連携して支援体制を築く 。 | 発達障害の支援には、多角的な視点が必要です。 家庭や医療機関とも連携し、「個別の教育支援計画」などを活用して、一貫した支援を行うことが子どもの安定した成長につながります 。 |
職場の上司・同僚の方へ
職場で能力を発揮するためには、本人の努力だけでなく、職場の理解と「合理的配慮」が不可欠です。産業保健の視点からも、働きやすい環境づくりは企業全体の生産性向上につながります。
| 対応策 | 具体的な接し方 | なぜ、そうするのか?(理由) |
|---|---|---|
| 1. 業務指示の明確化・具体化 | 「いい感じにやっといて」のような曖昧な指示は避け、「この資料を、この手順で、〇時までに作成してください」と具体的に伝える。 メールやチャットなど、後から確認できる形で指示を出すことも有効。 | 曖昧な指示は、何をどこまでやれば良いのかわからず、混乱や不安、作業の遅れにつながります 。 具体的な指示は、仕事の質を高め、ミスを防ぎます。 |
| 2. タスク管理のサポート | 複数の業務が重なる場合は、優先順位を一緒に確認する。 To-Doリストやスケジュール管理ツールの活用を促す。 | ADHDの特性がある人は、多くのタスクを同時に管理するのが苦手な場合があります 。 優先順位を明確にすることで、計画的に仕事を進めやすくなります。 |
| 3. 得意・不得意を考慮した業務分担 | 本人の特性を理解し、できるだけ得意な業務を任せる。 例えば、ルーティンワークが得意なASDの人にはデータ入力などを、アイデア豊富なADHDの人には企画会議への参加を促すなど。 | 誰にでも得意・不得意はあります。 本人の能力が最も発揮できる業務を任せることは、本人のやりがいと企業の生産性の両方を高めることにつながります(適材適所)。 |
| 4. 暗黙のルールや職場の常識の言語化 | 「会議では意見がなくても何か発言するのが望ましい」「〇〇さんには先に相談するのが慣例」など、言葉にされないルールを具体的に伝える。 | ASDの特性がある人は、その場の雰囲気や暗黙のルールを察するのが苦手な場合があります 。 言語化して伝えることで、人間関係のトラブルを未然に防ぐことができます。 |
| 5. 定期的な1on1ミーティングの設定 | 雑談が苦手な人も多いため、業務として相談の時間(1on1ミーティング)を設ける。 困っていること、配慮してほしいことなどを安心して話せる場を作る。 | 困っていても自分から言い出せないことがあります。 定期的に話を聞く機会を設けることで、問題を早期に発見し、孤立を防ぎ、職場定着につながります。 これは産業保健の観点からも重要です。 |

8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、発達障害の特性でお悩みの方々が、安心して自分らしい生活を送れるよう、一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。
- 専門医による丁寧な診断と治療:
国際的な診断基準に基づき、問診や心理検査を丁寧に行い、総合的に診断します(エビデンスがない上に高額な怪しい検査はしません)。その上で、ご本人の特性や希望に合わせ、薬物療法や心理社会的治療を組み合わせた最適な治療プランをご提案します。 - 医師による助言と指導:
ご自身の特性とのつきあい方、ストレス管理、ご家族や職場との関わり方など、日常生活での具体的な工夫について、医師が専門的な視点から助言・指導を行います。 - 連携によるサポート:
必要に応じて、地域の就労支援機関や福祉サービス、教育機関などと連携し、ご本人が社会の中で力を発揮できるようサポートします。 - カウンセリングの準備:
現在、臨床心理士によるカウンセリングや、より専門的な心理社会的プログラムの提供を準備しております。準備が整い次第、ホームページ等でお知らせいたします。
「もしかしたら…」と感じたら、一人で悩まず、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



