摂食障害は、食事の量や食べ方を自分でコントロールできなくなり、心と体に深刻な影響が及ぶ病気です。体重や体型への強いこだわりが特徴で、専門的な治療が必要です。
食事と体重への強いこだわりが心身を蝕む病気
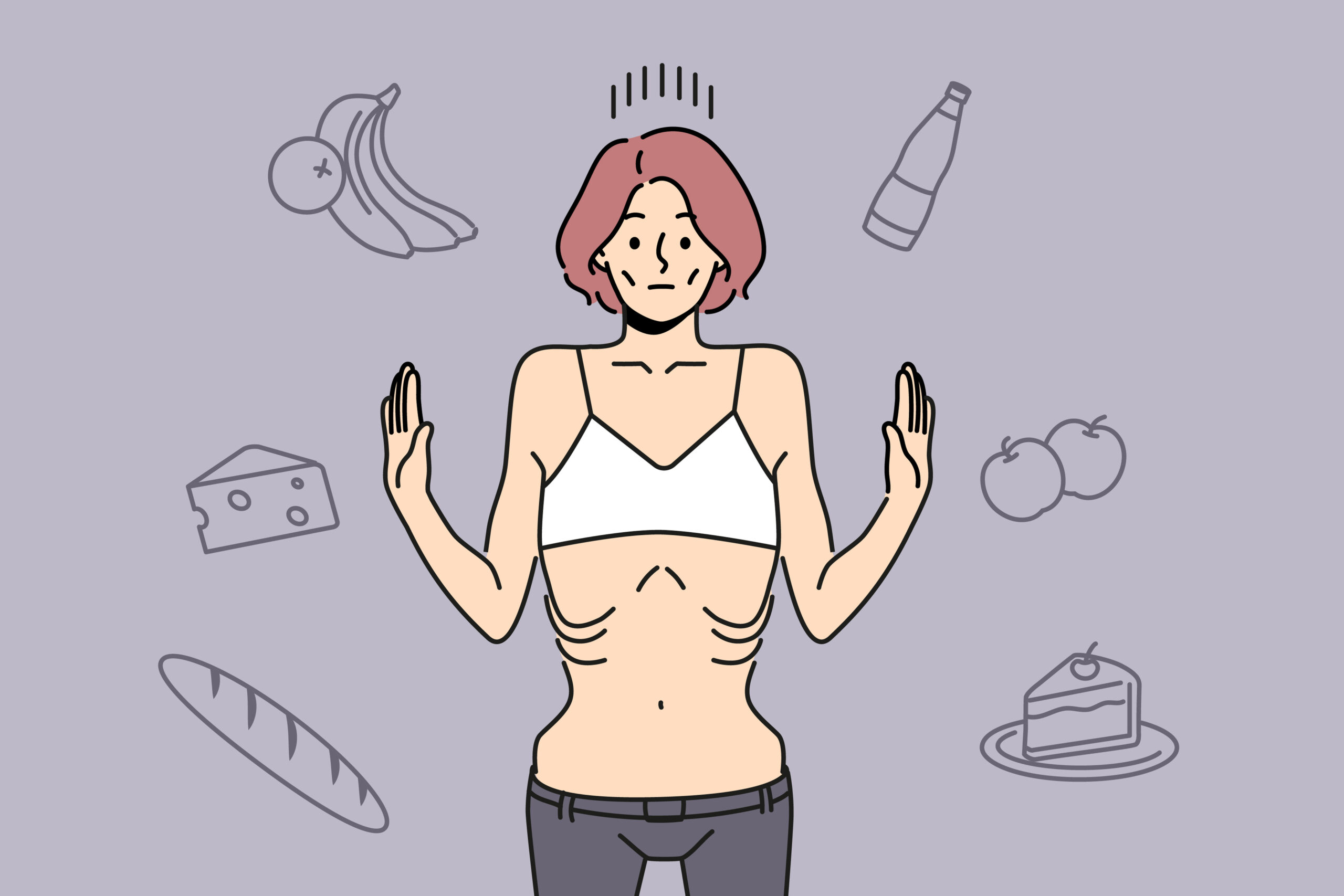
- 極端な食事制限をする
- 隠れて大量に食べる
- 食べた後に自分で吐く
- 下剤や利尿剤の不適切な使用
- 体重や体型に過度にこだわる
- 著しい低体重
- 疲れやすさや気分の落ち込み
- 月経が止まる
1. 摂食障害とは?
摂食障害は、単なる「わがまま」や「ダイエットのしすぎ」ではなく、こころとからだの両方に深刻な影響を及ぼす治療が必要な病気です。食事や体重、体型のことにとらわれすぎてしまい、自分で食べ方をコントロールできなくなってしまう状態を指します。
この病気は、大きく分けていくつかのタイプがあります。
- 神経性やせ症(拒食症):
体重が標準よりかなり低いにもかかわらず、「自分は太っている」と感じ、食べることを極端に避けるタイプです。 - 神経性過食症(過食症):
短時間に大量に食べてしまう「むちゃ食い」と、その後に体重増加を防ぐために自分で吐いたり(自己誘発性嘔吐)、下剤を使ったりする「代償行動」を繰り返すタイプです。 - 過食性障害:
「むちゃ食い」はしますが、神経性過食症のような代償行動は伴わないタイプです。 - 回避・制限性食物摂取症(ARFID):
体型や体重へのこだわりはないものの、食べ物の見た目や味、におい、食感などが原因で、食べられるものが極端に少ないタイプです。栄養不足や成長の遅れが問題になります。
摂食障害は、若い女性に多いイメージがあるかもしれませんが、男性や幅広い年齢層の方にも見られる病気です。表面的な食行動の問題の裏には、自己肯定感の低さ、完璧主義、対人関係の悩みなど、様々な心の苦しさが隠れていることが少なくありません。適切な治療を受ければ、必ず回復への道筋は見つかります。一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。

2. 主な症状
摂食障害の症状は、こころ、からだ、行動の3つの側面に現れます。ご自身やご家族に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
こころの症状
- 体重や体型への強いこだわり:
体重計のわずかな変化に一喜一憂し、鏡で自分の体を何度もチェックしてしまいます。 - 食べ物への強いとらわれ:
常にカロリー計算をしたり、食べ物のことばかり考えたりします。 - 「太ること」への極端な恐怖:
少しでも食べると太ってしまうのではないかという強い不安を感じます。 - 自己評価の低さ:
自分の価値を体重や体型で判断してしまいがちです。「痩せていない自分には価値がない」と思い込んでしまいます。 - 気分の落ち込みや不安感:
イライラしやすくなったり、急に涙が出たり、人付き合いを避けるようになったりします。

からだの症状
摂食障害は、栄養不足や不適切な行動によって、命に関わるような深刻な身体合併症を引き起こすことがあります。
| 症状の種類 | 具体的な症状 |
| 低体重によるもの | 無月経、低体温、脈が遅くなる(徐脈)、低血圧、骨粗しょう症、髪が抜ける、産毛が濃くなる |
| 嘔吐や下剤乱用によるもの | 電解質異常(低カリウム血症など)、不整脈、心停止のリスク、唾液腺の腫れ、歯が溶ける(酸蝕歯)、逆流性食道炎 |
| むちゃ食いによるもの | 胃拡張、急性膵炎、肝機能障害、血糖値の乱れ |
行動の変化
- 食事を極端に制限したり、特定の食品しか食べなくなったりする。
- 食事の時間をずらしたり、誰かと一緒に食事するのを避けたりする。
- 食後にすぐにトイレに行くことが多い(嘔吐のため)。
- 隠れて大量に食べる「隠れ食い」をする。
- 過度な運動を自分に課す。
3. 原因やきっかけ
摂食障害は、一つの原因で発症するわけではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
- 心理的な要因:
完璧主義で真面目な性格、自分に自信が持てない、ストレスにうまく対処できない、といった心の特性が関係することがあります。「痩せることで自信を得たい」「自分の感情をコントロールしたい」という気持ちが、食行動の異常につながることがあります。 - 社会・文化的な要因:
「痩せていることが美しい」という社会的なプレッシャーや、SNSなどで目にする理想化された体型のイメージなどが、痩せたいという願望を過剰に強めてしまうことがあります。 - 生物学的な要因:
遺伝的な要因や、食欲や気分をコントロールする脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスの乱れが関与している可能性も指摘されています。 - 家庭環境や人間関係:
家族との関係や学校・職場でのストレス、つらい体験(いじめや虐待など)が発症の引き金になることもあります。
これらの要因が組み合わさり、ダイエットなどの「痩せるための行動」をきっかけに、摂食障害の悪循環にはまり込んでしまうのです。
4. 診断の流れ
「もしかして摂食障害かも?」と思ったら、まずは専門の医療機関に相談することが大切です。診断は以下のような流れで進められます。
- 問診(お話を聞くこと):
医師が患者さんの現在の食生活、体重の変動、心や体のつらさ、生活の状況などについて、丁寧にお話を伺います。ご家族からお話を伺うこともあります。 - 身体的な診察:
体重や身長の測定(BMIの計算)、血圧、脈拍、体温などを測り、体の状態を評価します。 - 血液検査など:
栄養状態や、嘔吐・下剤乱用による電解質の異常など、身体合併症の有無を調べるために血液検査や心電図検査などを行うことがあります。 - 心理検査:
必要に応じて、質問紙などを用いて、心理的な特性やストレスの状態などを評価することもあります。

これらの情報をもとに、国際的な診断基準(DSM-5-TRやICD-11)に照らし合わせて総合的に診断します。大切なのは、診断名を確定することだけでなく、患者さん一人ひとりが抱える苦しさを理解し、その人に合った治療方針を一緒に考えていくことです。
5. 主な治療法
摂食障害の治療は、「こころ」と「からだ」の両面からのアプローチが不可欠です。治療のゴールは、単に体重を元に戻したり、異常な食行動をなくしたりすることだけではありません。患者さんが自分らしい生き方を取り戻し、健やかな毎日を送れるようになることを目指します。
心理社会的治療(カウンセリングなど)
治療の根幹となるものです。医師との対話を通じて、食や体重へのとらわれの背景にある考え方や感情の問題を扱っていきます。
- 認知行動療法(CBT):
摂食障害を維持させている考え方(認知)の偏りや行動のパターンに気づき、それをより現実的で健康的なものに変えていくことを目指す治療法です。食事記録をつけながら、自分の食行動を客観的に見つめ直すことから始めます。 - 対人関係療法(IPT):
対人関係のストレスが摂食障害の症状にどう影響しているかに焦点を当て、コミュニケーションのスキルを高めることで症状の改善を目指します。 - 家族療法:
特に未成年の患者さんの場合、ご家族にも治療に参加していただき、ご家族が患者さんを支える力を高めるお手伝いをします。

栄養療法
まずは、低栄養状態からの回復を目指します。管理栄養士などの専門家と相談しながら、規則正しくバランスの取れた食事を少しずつ摂れるようになることを目標にします。極端な食事制限ではなく、「安全に、安心して食べられるもの」から再開していきます。
薬物療法
摂食障害そのものに特効薬はありませんが、背景にあるうつ病や不安障害などの精神症状を和らげるために、抗うつ薬(特にSSRI)などが補助的に使われることがあります。
さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>
入院治療
外来治療だけでは回復が難しい場合や、身体的な危険が差し迫っている場合には、入院治療が必要になります。
入院が必要となる主なケース
- 極端な低体重:
標準体重の75%未満など、生命の危険がある場合(例:BMI 15 kg/m²未満)。 - 深刻な身体合併症:
不整脈、意識障害、重度の電解質異常(特に低カリウム血症)など、緊急の治療が必要な場合。 - 精神的な問題:
自殺のリスクが高い、重度のうつ状態を合併しているなど、安全の確保が必要な場合。 - 外来治療での改善が見られない:
外来での取り組みを続けても体重の減少が止まらない、または過食嘔吐が悪化する場合。


入院治療は、罰ではありません。24時間体制の医療チームに見守られた安全な環境で、心と体を休ませ、集中的に治療に取り組むための大切な選択肢です。
6. 回復や再発予防について
摂食障害からの回復は、一直線に進むとは限りません。良くなったり、少し後戻りしたりを繰り返しながら、時間をかけてゆっくりと進んでいくのが一般的です。焦らず、自分のペースで治療を続けることが何よりも大切です。
回復のサイン
- 体重や食事が、生活の中心ではなくなる。
- 食べ物をおいしいと感じられるようになる。
- 友人や家族と食事を楽しめるようになる。
- 体重以外のことに興味や関心が広がる。
- 自分の長所や短所を含めて、ありのままの自分を受け入れられるようになる。
再発を防ぐために
- ストレスへの対処法を身につける:
悩みを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、趣味などで気分転換したりする方法を見つけましょう。 - 生活リズムを整える:
規則正しい食事と十分な睡眠は、心の安定につながります。 - 完璧を目指さない:
「まあ、いいか」と思える心のゆとりを持つことも大切です。 - 無理なダイエットはしない:
自分の体を大切にし、健康的な食生活を心がけましょう。 - 調子が悪いと感じたら早めに相談する:
再発の兆候を感じたら、ためらわずに主治医に相談してください。
回復の道のりは決して平坦ではありませんが、あなたは一人ではありません。私たちが伴走者として、しっかりとサポートします。

7. 患者さんへの接し方(ご家族や周りの方へ)
ご家族や周りの方のサポートは、患者さんの回復にとって非常に重要です。しかし、どう接すれば良いか分からず、悩んでしまうことも多いでしょう。ここでは、具体的な接し方のポイントを「望ましい対応」と「避けるべき対応」に分けて、その理由とともに解説します。
まず心がけていただきたいこと
摂食障害は、本人の心の弱さやわがままが原因ではありません。脳と体が飢餓状態に陥り、正常な判断ができなくなっている「病気の状態」なのだと理解することが第一歩です。ご本人を責めるのではなく、「病気」と「本人」を切り離して考え、「病気と闘っている本人を支える」という姿勢が大切です。
具体的な対応のポイント
| 望ましい対応 | 避けるべき対応 | |
| 食事・体重について | 食事や体重の話題を避ける。 理由: これらの話題は本人の不安やこだわりを刺激し、症状を悪化させる一番の原因になります。 「食卓は楽しい時間」という本来の役割を取り戻すことを目指しましょう。 | 「食べなさい」「痩せすぎだよ」「太った?」など、食事や体型に関するコメントをする。 理由: 本人は誰よりもそのことを気にしています。 善意からの言葉でも、強いプレッシャーや批判と受け取られ、かえって症状が悪化します。 |
| 会話の仕方 | 本人の気持ちに寄り添い、話を聴くことに徹する。 「つらいんだね」「頑張っているんだね」と、感情を受け止める言葉をかけましょう。 本人が話したくない時は、無理に聞き出さず、静かにそばにいるだけでも支えになります。 理由: 本人は孤独感や罪悪感を抱えています。 無条件に味方でいてくれる存在がいることは、何よりの安心につながります。 | 叱咤激励したり、正論で説得しようとしたりする。 「もっとしっかりしなさい」「なぜ食べられないの?」といった言葉は、本人を追い詰めるだけです。 理由: 本人も「食べなければいけない」ことは頭では分かっています。 それができないから病気なのです。 正論は「自分はダメな人間だ」という自己否定を強めてしまいます。 |
| 本人への評価 | 体重や食事内容に関わらず、本人の存在そのものを肯定する。 「あなたがいてくれるだけで嬉しい」というメッセージを伝えましょう。 本人ができたこと(治療に通えた、悩みを話してくれた等)を具体的に認めると良いでしょう。 理由: 自己肯定感の低さが病気の根底にあります。 ありのままの自分に価値があると感じられることが、回復へのエネルギーになります。 | 「体重が増えたから偉いね」と褒める。 理由: これは「痩せたらダメだ」というメッセージになり、本人の「痩せ=善、太る=悪」という価値観を強めてしまいます。 体重の増減で評価するのは避けましょう。 |
| 病気との向き合い方 | 病気については専門家に任せ、ご家族は「休息と安心の場」を提供することに専念する。 ご家族が治療者になろうとすると、関係がぎくしゃくしてしまいます。 一緒にテレビを観る、散歩するなど、病気と関係ない時間を大切にしましょう。 理由: 家庭が治療の場になると、本人は心が休まりません。 家庭を安全地帯にすることが、本人が外で治療に取り組むための土台となります。 | 食べさせようと躍起になったり、隠れ食いを監視したりする。 理由: こうした行動は、本人との信頼関係を損ない、症状を隠そうとする行動をエスカレートさせます。 本人をコントロールしようとするのではなく、本人の力を信じて見守る姿勢が大切です。 |
| ご家族自身のケア | ご家族自身も、自分の時間を大切にし、休息をとる。 支援者(家族会など)や専門家に相談し、悩みを分かち合いましょう。 理由: ご家族が疲弊してしまうと、共倒れになりかねません。 ご家族が心身ともに健康でいることが、結果的に本人への一番のサポートになります。 | 一人で抱え込み、すべてを自分の責任だと感じてしまう。 理由: 摂食障害は誰のせいでもありません。 自分を責めることは、ご自身の心を追い詰めるだけでなく、その苦しさが本人にも伝わってしまいます。 |

8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、摂食障害に悩む患者さんとそのご家族に寄り添い、一人ひとりの状況に合わせた治療を提供します。
- 専門医による丁寧な診察と治療計画:
摂食障害の治療経験が豊富な医師が、患者さんのお話をじっくりと伺い、心と体の状態を正確に評価します。その上で、ご本人と相談しながら、最適な治療の目標と計画を一緒に立てていきます。 - 薬物療法の検討:
摂食障害に伴う気分の落ち込み、不安、不眠などの症状に対して、必要に応じて薬物療法を検討し、つらい症状の緩和を図ります。 - 医師による助言・指導:
治療の核となる精神療法的なアプローチとして、医師が認知行動療法や対人関係療法の考え方に基づいた面接を行い、回復への道をサポートします。ご家族からのご相談にも応じ、ご家庭での適切な関わり方について助言します。 - 連携体制:
高度の身体管理や入院治療が必要と判断した場合は、速やかに適切な専門医療機関へご紹介できる連携体制を整えています。
(現在、当院では心理士によるカウンセリングは準備中ですが、医師が精神療法的なアプローチを積極的に行っています。)
摂食障害は回復できる病気です。一人で悩み続けずに、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



