薬物依存症は、薬物の使用をやめたいのにやめられない脳の病気です。専門的な治療と周囲のサポートで回復が可能です。一人で悩まずご相談ください。
自分の意志ではやめられない「病気」
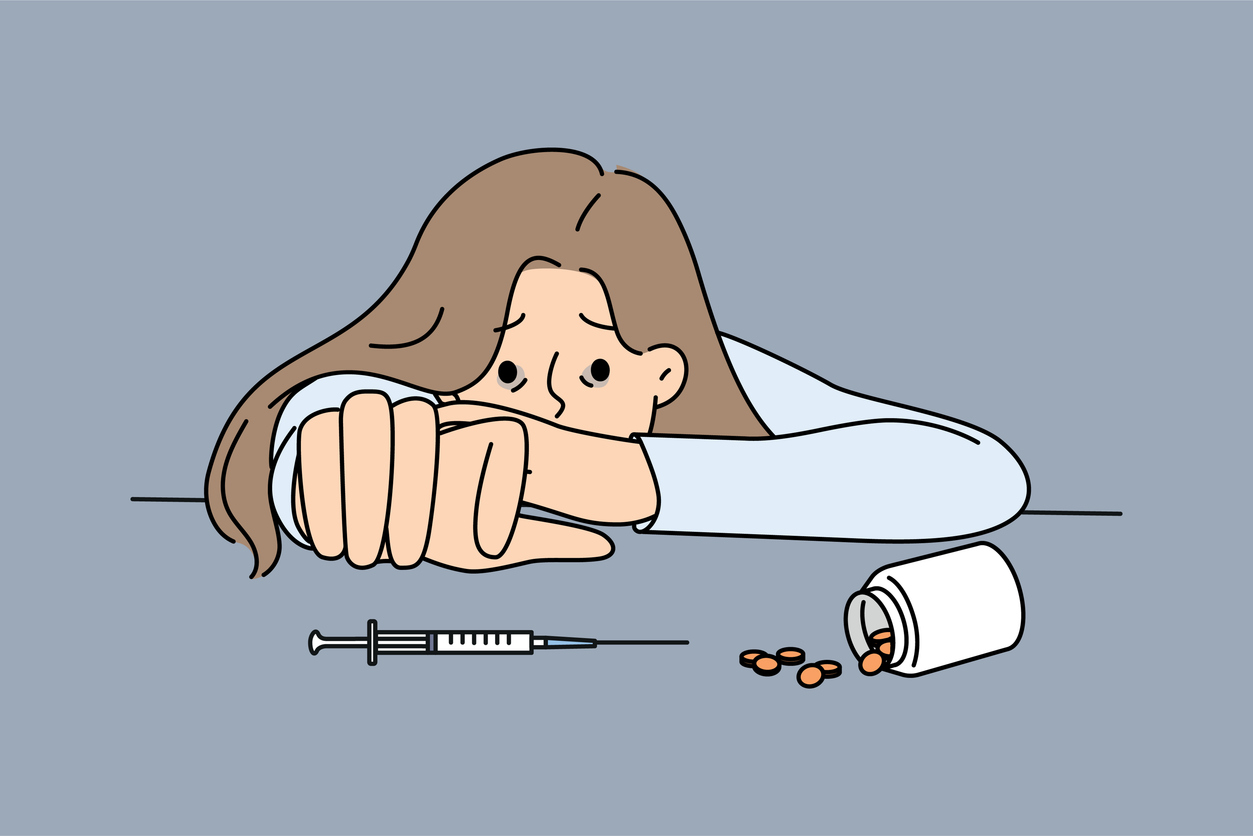
- やめようと思ってもやめられない
- 使用量や回数がどんどん増える
- 薬物中心の生活になる
- 薬が切れると不快な症状が出る
- 薬物のために大切な活動をやめる
- 心や体に問題が起きても使い続ける
- 薬物の入手に多くの時間を費やす
- 「やめる」「使いたい」で葛藤
【1】疾患概念・定義(DSM-5-TR / ICD-11)
物質関連障害および嗜癖性障害群は、精神作用物質の使用や特定の反復行動によって生じる、行動、認知、身体症状を特徴とする一連の障害群である。
DSM-5-TRでは、「物質関連障害および嗜癖性障害群(Substance-Related and Addictive Disorders)」として一つの大分類にまとめられている。これはさらに以下の2つのグループに分けられる。
- 物質使用障害(Substance Use Disorders):
特定の物質を問題があると知りながらも使用を続けてしまう状態で、認知、行動、生理学的症状の複合体である。診断は、「制御障害」「社会的障害」「危険な使用」「薬理学的基準(耐性、離脱)」の4カテゴリーに分類される11項目中、過去12ヶ月で2項目以上を満たすことでなされる。重症度は、軽度(2-3項目)、中等度(4-5項目)、重度(6項目以上)に分類される。 - 物質誘発性障害(Substance-Induced Disorders):
物質の摂取や離脱の直接的な影響によって生じる精神症状を指す。これには、物質中毒、物質離脱のほか、物質・医薬品誘発性精神疾患(精神病性障害、双極性および関連障害群、抑うつ障害群など)が含まれる。
ICD-11では、「物質使用症または嗜癖行動症(Disorders due to substance use or addictive behaviours)」という章に分類される。DSM-5-TRと同様に、物質使用による障害と、ギャンブルやゲームなどの行動による障害(嗜癖行動症)が同じカテゴリーに含まれる点が特徴である。
- 物質使用の有害なパターン(Harmful pattern of substance use):
身体的または精神的な健康に実質的な害をもたらす物質使用のパターンを指す。 - 物質依存症(Substance dependence):
物質使用のコントロール障害、生理学的特徴(耐性、離脱)、物質使用が他の活動より優先されることなどを特徴とする。
用語の比較として、DSM-IV-TRまでは「乱用」と「依存」が区別されていたが、DSM-5ではこれらの区別が信頼性に乏しいことから「物質使用障害」という単一の診断名に統合された。ICDにおいても同様の傾向が見られる。
【2】疫学(国内外、有病率、性差、発症年齢)
国内の状況 日本の薬物事犯検挙者数は、覚醒剤が依然として最も多いが、近年は大麻事犯の検挙者数が急増し、有機溶剤を上回っている。
一般人口における薬物使用の生涯経験率(2015年調査、15~64歳)は以下の通りである。
- いずれかの違法薬物:2.4%(約223万人)
- 有機溶剤:1.5%
- 大麻:1.0%
- 覚醒剤:0.5%
- 危険ドラッグ:0.3%
精神科医療施設を受診した患者の主たる薬物(令和4年度調査)は、覚醒剤が49.7%と最も多く、次いで睡眠薬・抗不安薬(17.6%)、市販薬(11.1%)、大麻(6.3%)と続く。処方薬や市販薬の乱用・依存が大きな割合を占めている点が特徴であり、特にベンゾジアゼピン系薬剤の乱用は増加傾向にある。処方薬依存は女性に多く、犯罪歴が少ない傾向がある。
国際的な状況 米国では、オピオイド系鎮痛薬の過剰処方が社会問題化しており、オピオイド依存症が深刻な公衆衛生上の危機となっている。これに対し、日本では医療用麻薬による依存症の発生率は0.19%と比較的低い。
【3】病因・病態生理(神経生物学・心理社会的要因)
物質使用障害の発症には、生物学的、心理的、社会的要因が相互に作用する(生物・心理・社会モデル)。
神経生物学的要因
- 脳内報酬系:
全ての依存性薬物は、最終的に中脳辺縁系ドパミン神経系を活性化させ、側坐核でのドパミン放出を促進することで「快」の情動を生じさせ、強化学習(オペラント条件付け)を通じて薬物探索行動を強化する。 - 耐性(Tolerance):
薬物の反復摂取により、受容体のダウンレギュレーションや代謝酵素の誘導などが起こり、同じ効果を得るためにより多くの薬物量が必要となる。 - 離脱(Withdrawal):
薬物連用により恒常性が変化した状態で薬物が急激に消失すると、自律神経系の反跳現象などにより不快な心身症状(離脱症状)が出現する。 - 渇望(Craving):
薬物に関連する刺激(場所、人、物)に曝露されることで、扁桃体や前頭前野などが賦活され、強い使用欲求が生じる。これは再発の最も大きな要因の一つである。
心理社会的要因
- 精神疾患の合併:
物質使用障害患者の約半数に他の精神疾患が合併しており、特にうつ病、双極性障害、不安障害、ADHD、PTSDなどが高率に見られる。症状緩和のための自己治療として薬物使用が始まるケースも多い。 - トラウマ体験:
児童期の虐待やネグレクトなどのトラウマ体験は、物質使用障害の強力なリスクファクターである。特に女性ではその関連が強い。 - 発達障害:
ADHDなどの発達障害を持つ人は、その特性(衝動性、報酬系への感受性など)から物質使用障害のリスクが高いとされる。 - 社会的孤立・ストレス:
経済的困窮、孤独、社会的サポートの欠如なども発症・維持の要因となる。
【4】臨床症状・経過(典型例・非典型例)
臨床症状は使用する物質の薬理作用によって異なる。
中枢神経刺激薬(覚醒剤、コカインなど)
- 精神症状:
多幸感、覚醒レベルの上昇、多弁、活動性の亢進。慢性的な使用により、幻覚(特に幻聴)、被害妄想、注察妄想といった統合失調症様の精神病症状(覚醒剤精神病)を呈する。 - 身体症状:
交感神経刺激作用により、頻脈、血圧上昇、発汗、瞳孔散大。 - 離脱症状:
倦怠感、過眠、抑うつ、無気力。 - 逆耐性(感作):
精神病症状は一度生じると、少量の再使用やストレスで容易に再燃する(フラッシュバック現象)。
中枢神経抑制薬(ベンゾジアゼピン系、バルビツール酸系など)
- 精神症状:
脱抑制、多幸感、眠気、判断力低下。高用量では記憶障害(前向性健忘)や錯乱状態を呈することがある。 - 身体症状:
構音障害、運動失調、呼吸抑制(過量摂取で致死的)。 - 離脱症状:
不安、焦燥、不眠、振戦、発汗、けいれん発作、せん妄など。作用時間の短い薬剤ほど離脱症状は急激で重篤となりやすい。
オピオイド(ヘロイン、医療用麻薬など)
- 精神症状:
強烈な多幸感、鎮静、無気力。 - 身体症状:
縮瞳、呼吸抑制、便秘、嘔気。 - 離脱症状:
流涙、鼻汁、あくび、悪寒、筋肉痛、下痢、嘔吐、不眠、強い渇望など、インフルエンザ様の激しい症状を呈する。
大麻(カンナビノイド)
- 精神症状:
多幸感、リラックス、感覚変容(知覚が鋭敏になる)、思考の解体、時間感覚の歪み。高用量ではパニック発作や精神病症状を誘発することがある。長期使用は統合失調症発症のリスクを高める可能性が指摘されている。 - アモティベーション症候群:
長期大量使用者に見られる、無気力、意欲低下、感情鈍麻を特徴とする状態。
【5】鑑別診断と評価尺度
鑑別診断
- 精神疾患:
統合失調症、双極性障害、うつ病、不安障害などとの鑑別が重要である。特に、物質誘発性精神病性障害と統合失調症との鑑別は、断薬後の症状の遷延の有無が鍵となる(通常、前者では1ヶ月以内に症状は改善する)。 - 身体疾患:
甲状腺機能亢進症、てんかん、頭部外傷などが、物質使用障害と類似の症状を呈することがあるため、身体的評価は必須である。
評価尺度
- DAST (Drug Abuse Screening Test):
薬物乱用問題をスクリーニングするための自記式質問票。簡便で臨床場面で有用性が高い。スコアに応じて問題の程度を評価する。 - SDS (Severity of Dependence Scale):
依存の重症度を評価する5項目の自記式尺度。精神依存に焦点を当てている。 - ASI (Addiction Severity Index):
薬物問題だけでなく、身体的健康、雇用、法律、家族関係など多岐にわたる領域の問題を半構造化面接で評価する包括的な尺度。
【6】検査(心理検査・画像・血液)
- 心理検査:
合併する精神疾患や発達障害の評価のために、WAISなどの知能検査や人格検査、ADHDの評価尺度(ASRS)、自閉スペクトラム症の評価尺度(AQ-J)などが用いられることがある。 - 画像検査:
脳の器質的疾患を除外するために頭部CTやMRIが用いられる。研究レベルでは、PETやfMRIを用いて、報酬系の賦活やドーパミンD2受容体の密度などが研究されている。 - 血液・尿検査:
薬物スクリーニング、肝機能や腎機能の評価、感染症(HIV、HBV、HCV)のスクリーニングは必須である。
【7】治療(薬物療法、心理社会的介入、入院適応)
治療の基本は、断薬(あるいは管理下での減薬)を維持し、再発を防ぎ、社会復帰を支援することである。
心理社会的介入
- 動機づけ面接法(Motivational Interviewing):
治療への動機が低い患者に対し、共感的・受容的な態度で両価性(変わりたい気持ちと変わりたくない気持ち)を探り、本人の内発的な変化への動機を高める。 - 認知行動療法(CBT):
薬物使用につながる状況(高リスク状況)、自動思考、感情をモニタリングし、渇望への対処スキルや問題解決スキル、コミュニケーションスキルなどを訓練する。 - SMARPP(Systematic Methamphetamine Relapse Prevention Program):
認知行動療法をベースにした、日本の覚醒剤依存症者向けに開発された構造化された集団療法プログラム。 - 条件付けマネジメント(Contingency Management):
断薬の維持など、望ましい行動に対して報酬(金券など)を与えることで行動変容を促す。 - 家族療法・家族介入:
依存症を個人の問題ではなく家族システムの問題と捉え、家族内のコミュニケーションパターンや役割を修正する。CRAFT(Community Reinforcement and Family Training)は、家族が本人を治療に繋げるためのスキルを学ぶ効果的なプログラムである。 - 自助グループ:
NA(ナルコティクス・アノニマス)やDARC(薬物依存症リハビリテーションセンター)など、当事者同士のピアサポートが回復に不可欠な役割を果たす。
薬物療法
薬物療法はあくまで補助的であり、心理社会的治療と組み合わせて行う。
- 離脱症状の治療:
ベンゾジアゼピン系薬物の離脱には、作用時間の長い同系統の薬剤に置換し漸減する方法が用いられる。 - 合併精神疾患の治療:
うつ病に対するSSRIなど、合併症の治療が物質使用の低減につながることがある。 - 渇望抑制・再発防止:
- オピオイド依存:
拮抗薬であるナルトレキソンや、部分作動薬であるブプレノルフィンが渇望や再発の防止に有効である。維持療法としてメサドンが用いられる国もある。 - 覚醒剤・コカイン・大麻依存:
現時点で特異的な治療薬として承認されているものはない。研究レベルでは様々な薬剤が試みられている。
- オピオイド依存:
入院適応
- 重篤な離脱症状(せん妄、けいれん)が予想される場合。
- 深刻な精神症状(重度の精神病症状、強い自殺念慮)を伴う場合。
- 重篤な身体合併症があり、医学的管理が必要な場合。
- 外来治療では断薬の維持が困難で、環境の構造化が必要な場合。
- 自傷他害の恐れが切迫している場合は、精神保健福祉法に基づく非自発入院(措置入院など)の対象となることがある。
【8】予後・再発予防(機能予後含む)
薬物依存症は再発しやすい慢性疾患である。治療後1年以内の再発率は高いが、治療と自助グループへの参加を継続することで、長期的な断薬と安定した生活を送ることは十分に可能である。
- 機能予後:
長期的な断薬が維持できれば、多くの患者は就労し、家庭生活を営むことが可能となる。しかし、薬物使用による認知機能への影響や、犯罪歴などが社会復帰の障壁となることもある。 - 再発予防:
回復は一直線ではなく、スリップ(一回の再使用)やリラップス(本格的な再発)を繰り返しながら進むことが多い。- HALT:
「Hungry(空腹)」「Angry(怒り)」「Lonely(孤独)」「Tired(疲れ)」は再発の危険信号であり、これらの状態を避けるセルフケアが重要である。 - コーピングスキル:
ストレスや渇望に薬物以外の方法で対処するスキル(運動、趣味、相談など)を身につける。 - 環境調整:
薬物を使っていた仲間や場所から離れる。 - サポートネットワーク:
治療者、家族、自助グループの仲間など、相談できる相手を持つことが回復を支える。
- HALT:
【9】最新研究動向(過去5年)
- 神経科学的研究:
fMRIやPETを用いた研究により、渇望や意思決定における脳内ネットワーク(報酬系、実行機能系、情動制御系)の異常が解明されつつある。特に前頭前野の機能低下が、自己コントロール障害の基盤にあると考えられている。 - 遺伝学的研究:
ゲノムワイド関連解析(GWAS)により、依存症のリスクに関連する複数の遺伝子多型が同定されつつあるが、個々の影響は小さい。 - 治療法の開発:
- 薬物療法:
覚醒剤依存症などに対する治療薬開発が進められており、グルタミン酸系やGABA系に作用する薬剤が有望視されている。 - 神経刺激療法:
経頭蓋磁気刺激法(TMS)などが、渇望を低減させる治療法として研究されている。 - デジタルセラピューティクス:
スマートフォンアプリを用いた認知行動療法など、新しい形の介入も試みられている。
- 薬物療法:
- ハームリダクション:
薬物使用による健康被害や社会的損害を最小限に抑えるという観点から、安全な注射針の提供プログラムや、過量摂取に対するナロキソン配布などが国際的に広がっている。
【10】国内外ガイドライン比較
国内外の主要なガイドライン(APA、NICE、日本精神神経学会など)は、いずれも薬物依存症(物質使用障害)の治療において、心理社会的治療が中心であり、薬物療法は補助的役割であるという点で一致している。
- 初期介入:
動機づけ面接法による治療動機の向上が推奨されている。 - 中核的治療:
認知行動療法、条件付けマネジメントが強く推奨されている。 - 家族介入:
CRAFTなど、エビデンスのある家族支援プログラムの実施が推奨される。 - 自助グループ:
NAなど12ステッププログラムに基づく自助グループへの参加が強く推奨されている。 - 薬物療法:
オピオイド依存に対するナルトレキソンやブプレノルフィンは強く推奨されるが、他の物質使用障害に対する薬物療法の推奨度は低い。 - 日本の特徴:
SMARPPやCRAFT-Jなど、日本の文化や医療システムに合わせて改良・開発されたプログラムが実践されている。海外と比較して、自助グループから派生した民間のリハビリテーション施設(DARCなど)が、回復において大きな役割を担っている。
【11】参考文献
- 『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』日本精神神経学会 (日本語版用語監修), 髙橋三郎, 大野裕 (監訳), 医学書院, 2023.
- 『精神科研修ノート第3版』永井良三 (シリーズ総監修), 笠井清登 (編集), 診断と治療社, 2021.
- 『カプラン臨床精神医学テキスト第3版』井上令一 (監訳), MEDSI, 2017.
- 『精神診療プラチナマニュアル第3版』松崎朝樹 (著), MEDSI, 2020.
- 『こころの健康が見える vol.1』メディックメディア, 2021.
- 『今日の精神疾患治療指針 第2版』樋口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸 (編集), 医学書院, 2016.
- American Psychiatric Association: APA Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients With Alcohol Use Disorder. 2018.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Drug misuse in over 16s: psychosocial interventions (CG51). 2007.
- 松本俊彦, 他. 全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査. 令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金分担研究報告書. 2023.
- 世界保健機関(WHO). ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision. 2019.
2




