体の痛みが続くのに検査では異常なし。それは身体症状症かもしれません。こころの不調が体に現れるこの病気のサインと回復への道筋を解説。
こころと体の警報システム、身体症状症の理解と対処
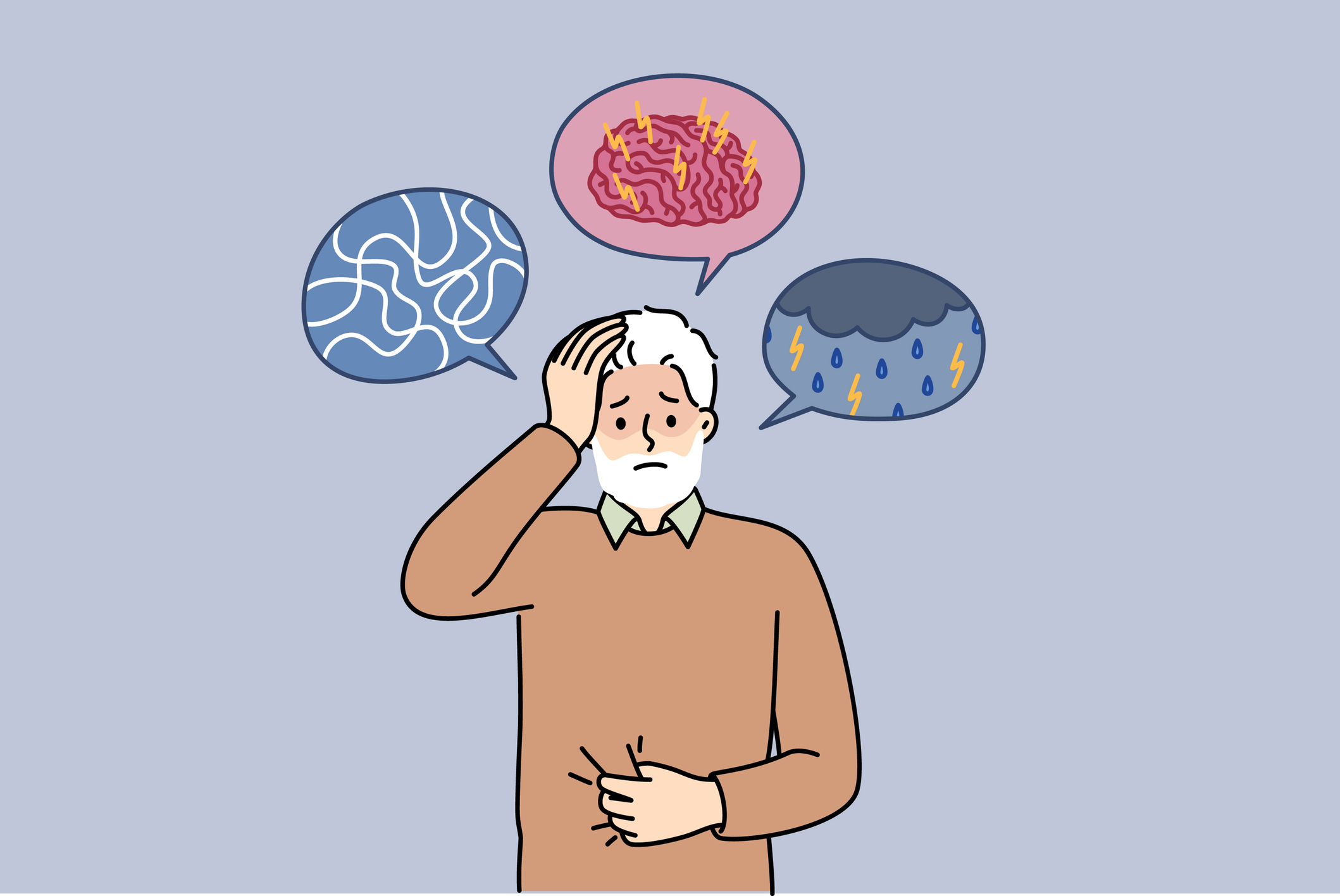
- 多彩な身体の痛み(頭痛、腹痛、腰痛など)
- 感覚の異常(しびれや、感覚が鈍くなる)
- 消化器系の不調(吐き気、下痢、便秘など)
- 全身の倦怠感
- 健康への過剰な不安
- 頻繁な医療機関の受診
【1】疾患概念・定義(DSM-5-TR / ICD-11)
身体症状症(Somatic Symptom Disorder: SSD)は、DSM-5で導入された診断カテゴリーであり、DSM-IV-TRにおける身体化障害、鑑別不能の身体表現性障害、心気症、疼痛性障害の多くを統合・再編したものである 。その本質は、1つ以上の苦痛を伴う身体症状と、その症状に対して向けられる過剰または不適応な思考、感情、行動によって特徴づけられる 。
DSM-5における最大の変更点は、「医学的に説明できない身体症状」という要件が必須ではなくなったことである 。これにより、悪性腫瘍や自己免疫疾患といった明確な身体疾患を持つ患者であっても、その症状に対する心理社会的苦痛や機能障害が、臨床的に見て過剰である場合にはSSDと診断されうる 。この変更は、精神と身体を分断して捉える心身二元論からの脱却を意図したものであり、プライマリケア医や各科専門医と精神科医とのリエゾン・コンサルテーションの重要性を強調するものである 。
患者の「とらわれ」が病態の中核にあり、身体症状そのものよりも、それに対する認知・感情・行動面の不適応な反応が診断の決め手となる 。この「とらわれ」は、患者自身が精神医学的問題を認識しておらず、身体疾患であると確信しているため、ドクターショッピングや不必要な検査・治療の要求につながりやすい 。
ICD-11では、「身体的苦痛症(Bodily Distress Disorder)」という診断名が用いられ、DSM-5のSSDとほぼ同義の概念として扱われている 。これもまた、苦痛を伴う身体症状と、それに関連した過剰な注意や破局的思考、回避行動などを診断要件としている。
【2】疫学(国内外、有病率、性差、発症年齢)
身体症状症の疫学データはまだ限定的であるが、いくつかの調査からその概観が明らかになっている。
- 一般人口における有病率:
欧米の研究では、一般成人の5~7%と推定されている 。これは精神疾患の中でも比較的頻度の高いものであることを示唆している。 - プライマリケアにおける有病率:
一般内科などプライマリケアの現場では、有病率はさらに高く、10~20%に達すると報告されている 。これは、身体的な愁訴を主訴とする患者の中に、多くのSSD患者が含まれていることを意味する。 - 性差:
女性は男性に比べて身体愁訴を報告する傾向が強く、結果としてSSDの有病率も女性の方が高いとされている 。 - 発症年齢:
特定の発症年齢はないが、多くは30歳以前に発症するとされる 。
日本における大規模な疫学調査は今後の課題であるが、社会的・経済的影響は甚大であると推測される。米国ではSSD患者の医療費は非SSD患者の2倍にのぼるとの報告があり 、本邦においても、不必要な医療費の増大や就労困難による経済的損失は計り知れない 。
【3】病因・病態生理(神経生物学・心理社会的要因)
SSDの病因は単一ではなく、生物・心理・社会的な要因が相互作用する多因子モデルで理解されている 。
神経生物学的要因
- 痛覚過敏と中枢性感作:
患者は痛みの閾値が低く、通常では痛みとして感じない刺激を痛みとして知覚する傾向がある(アロディニア)。これは、脊髄後角や視床、大脳皮質などにおける痛覚情報処理システムの中枢性感作が関与している可能性が示唆されている。 - 自律神経系の機能不全:
ストレスに対する自律神経系の反応異常が、動悸、発汗、消化器症状などの多彩な身体症状に関与していると考えられる。 - HPA系の機能異常:
視床下部-下垂体-副腎皮質(HPA)系の活動亢進が、ストレス脆弱性と関連し、身体症状の発現や遷延化に関与する可能性がある。
心理社会的要因
- 認知・行動的要因:
- 破局的思考:
身体感覚を破局的に解釈する認知スタイルが、不安を増幅させ、症状を悪化させる 。 - 症状への選択的注意:
身体感覚へ過剰に注意を向けることで、些細な変化を増幅して知覚する。 - 疾病利得:
症状があることで、嫌な義務や責任を回避できたり、周囲からの関心や同情を得られたりすることが、無意識的に症状を維持させている場合がある 。
- 破局的思考:
- 発達的・環境的要因:
- 幼少期の逆境体験:
身体的・性的虐待やネグレクトなどの経験は、長期的なストレス反応系(HPA系など)の変化を引き起こし、成人後のストレス脆弱性を高めるリスク因子である 。 - 学習:
親が病気がちで、身体の不調に過度に注意を払う家庭環境で育った場合、身体愁訴をコミュニケーションの手段として学習することがある(社会的学習理論) 。
- 幼少期の逆境体験:
- パーソナリティ:
神経症的傾向(否定的感情)が強いパーソナリティは、SSDの強力なリスク因子である 。また、感情の認知や言語化が困難なアレキシサイミアの傾向も関連が指摘されている 。
【4】臨床症状・経過(典型例・非典型例)
SSDの臨床像は極めて多彩であるが、中心となるのは単一または複数の身体症状と、それに伴う過剰な心理的反応である。
典型的な臨床像
愁訴は多岐にわたり、特定の器官系に限局しないことが多い。疼痛が最も一般的であるが、倦怠感、消化器症状、心血管系症状、神経学的症状など、複数の訴えが同時に存在し、時間とともに症状の種類や部位が変化することもある 。患者は症状の原因を身体疾患にあると固く信じており、心理社会的要因の関与についての
病識は乏しいことが多い 。陰性所見を繰り返し説明されても納得せず、医師の説明を「真剣に取り合ってくれない」と解釈し、不信感を募らせ、
ドクターショッピングに至る 。結果として、多くの不必要な検査や、時には侵襲的な治療を受け、医原性の合併症を引き起こすリスクもある 。
経過
経過は慢性的で、症状が変動しながら数年以上にわたって持続することが多い 。完全な寛解は少ないとされるが、適切な治療により、症状にとらわれることなく社会生活を送れるようになることは十分に可能である。心理社会的ストレスによって症状が悪化する傾向が顕著である 。
特定の臨床タイプ
- 疼痛が主症状のもの(旧:疼痛性障害):
診断基準B(過剰な思考・感情・行動)を満たし、かつ愁訴の中心が疼痛である場合に特定される 。 - 持続性:
重篤な症状、著しい機能障害、6ヶ月以上の長期にわたる持続期間によって特徴づけられる場合に特定される 。
【5】診断基準と鑑別診断(評価尺度含む)
DSM-5-TR 診断基準
SSDの診断は、DSM-5-TRの診断基準に沿って行われる 。
- 1つまたはそれ以上の、苦痛を伴うか、または日常生活に意味のある混乱を引き起こす身体症状。
- 身体症状またはそれに伴う健康への懸念に関連した、以下のうち少なくとも1つによって顕在化する過度な思考、感情、または行動:
(1) 自分の症状の深刻さについての、不釣り合いかつ持続する思考。
(2) 健康または症状についての持続する強い不安。
(3) これらの症状または健康への懸念に費やされる過度の時間と労力。 - いずれか1つの身体症状が持続的に存在しているわけではないかもしれないが、症状のある状態は持続している(典型的には6カ月以上)。
重症度は、基準Bの項目を満たす数(軽症:1つ、中等症:2つ以上)および身体愁訴の数(重度:中等症の基準に加え、複数の身体愁訴、または1つの非常に重度な身体症状)によって特定される 。
鑑別診断
- 他の精神疾患:
- 病気不安症:
身体症状は存在しないか、ごく軽度であり、重篤な疾患にかかることへの恐怖や観念が中心である 。SSDでは、身体症状そのものの苦痛が前景に出る。 - うつ病・不安症:
身体症状はうつ病やパニック症でも一般的であるが、これらの疾患では気分の落ち込みやパニック発作が中心的な病像を形成する。ただし、併存は非常に多い 。 - 転換性障害(機能性神経症状症):
症状は随意運動または感覚機能の変容や喪失に限局する 。 - 妄想性障害 身体型:
症状に関する信念が妄想的な確信度を持つが、SSDのように多彩な愁訴やドクターショッピングを伴うことは少ない。 - 作為症・詐病:
症状が意図的に産生されている点で鑑別される 。
- 病気不安症:
- 身体疾患:
多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、内分泌疾患、潜在的な悪性腫瘍など、多彩な非特異的症状を呈する身体疾患は常に鑑別に含める必要がある 。
評価尺度
診断や重症度評価の補助として、以下のような評価尺度が用いられることがある。
- PHQ-15 (Patient Health Questionnaire-15):
15項目の身体症状について、その重症度を評価する自己記入式質問票。 - SSS-8 (Somatic Symptom Scale-8):
身体症状の負担感を評価する8項目の尺度。
【6】検査(心理検査・画像・血液)
SSDに特異的な生物学的マーカーは存在しない 。検査の主な目的は、症状の原因となりうる身体疾患を鑑別・除外することにある。
- 身体的検査:
詳細な病歴聴取と身体診察に加え、症状に応じた血液検査、尿検査、画像検査(CT, MRIなど)、生理機能検査(心電図、脳波など)が適宜行われる。心療内科では、消化管運動機能検査など、自律神経機能や器官の機能を評価する専門的な検査が行われることもある 。 - 心理検査:
パーソナリティ特性や認知スタイル、併存する精神症状を評価するために、MMPI(ミネソタ多面人格目録)、SCT(文章完成法テスト)、不安・抑うつ尺度などが補助的に用いられることがあるが、診断の決め手にはならない 。
【7】治療(薬物療法、心理社会的介入、入院適応)
治療の基本方針は、支持的な治療関係を基盤に、心理社会的介入と薬物療法を組み合わせることである 。不必要な検査や治療を避け、症状への「とらわれ」を緩和し、機能回復を目指す。
心理社会的介入
- 認知行動療法(CBT):
最もエビデンスレベルの高い治療法である 。身体感覚に対する破局的思考の修正、回避行動の低減、ストレス対処スキルの向上などを通して、症状の悪循環を断ち切る。ICT(情報通信技術)を用いた遠隔CBTや、セルフヘルプ型のインターネットCBT(iCBT)の有効性も示されている 。 - 支持的精神療法:
定期的な診察の中で、患者の訴えを共感的に傾聴し、その苦痛を承認することで、安心感を提供し治療関係を構築する。症状が心理的ストレスと関連している可能性について、時期を見計らって丁寧に心理教育を行う。 - 集団精神療法:
同様の悩みを持つ他の患者との交流を通じて、孤立感を和らげ、新たな対処法を学ぶ機会となる 。
薬物療法
薬物療法は補助的な位置づけであり、主に併存するうつ病や不安症の治療、あるいは疼痛の緩和を目的として用いられる 。
- 抗うつ薬(SSRI, SNRI):
第一選択薬となる。不安や抑うつの改善に加え、下行性疼痛抑制系を賦活することによる鎮痛効果も期待できる。 - 三環系抗うつ薬:
特にアミトリプチリンなどは神経因性疼痛に対して有効性が示されているが、副作用の観点から使用には注意を要する。 - 抗不安薬:
ベンゾジアゼピン系薬物は、依存や乱用のリスクから長期使用は避けるべきである 。 - その他:
症状に応じて、少量の抗精神病薬や、α2δリガンド(プレガバリンなど)、漢方薬が用いられることがある 。
入院適応
通常は外来治療が中心となるが、以下のような場合には入院が考慮される。
- 重度の抑うつ状態や希死念慮を伴う場合。
- 身体的な消耗が著しく、外来での管理が困難な場合。
- 診断が不確実で、詳細な検査や観察が必要な場合。
- 不適切な多剤併用からの離脱(薬物調整)が必要な場合。
【8】予後・再発予防(機能予後含む)
SSDの予後は、一般的に慢性的であり、症状が完全に消失することは少ないとされる 。しかし、約3分の1から半数の患者は有意な改善を示すとの報告もある 。
予後良好因子
高い社会経済状態、治療に反応する不安やうつ病の併存、急性の発症、パーソナリティ障害の不在、重篤な身体疾患がないことなどが挙げられる 。
機能予後
症状の重症度だけでなく、それに対する患者の認知や対処スタイルに大きく左右される。適切な治療により、症状は残存しても、それに振り回されることなく学業や就労、社会活動を維持することは可能である。
再発予防
CBTで習得したスキルの継続的な実践が不可欠である。特に、ストレスコーピング能力の向上、生活リズムの安定、破局的思考パターンへの早期の気づきと修正が重要となる。症状の増悪と心理社会的ストレスとの間には明確な関連があるため 、ストレス管理が長期的な安定の鍵となる。
【9】最新研究動向(2025年)と今後の展望
近年のSSD研究は、ICTの活用と神経科学的アプローチの2つの潮流が注目される(2024年時点)。
- デジタル・メンタルヘルス:
- ビデオ会議システムを利用した遠隔CBTの有効性と安全性が複数のランダム化比較試験で示されている 。これにより、地理的・身体的な制約から専門的治療へのアクセスが困難であった患者への治療提供が可能となりつつある。
- スマートフォンアプリやウェブサイトを利用したセルフヘルプ型iCBTプログラムの開発も進んでおり、低強度介入としての有効性が検証されている 。これらのプログラムは、治療への導入や再発予防ツールとしての活用が期待される。
- 神経科学的アプローチ:
- 機能的脳画像研究(fMRIなど):
安静時脳機能ネットワーク解析などにより、SSD患者では、顕著性ネットワーク(salience network)やデフォルトモードネットワーク(default mode network)の結合異常が報告されている。これは、身体内部感覚への過剰な注意と、自己関連情報の処理異常という病態生理を支持するものである。 - 予測的符号化(Predictive Coding)理論:
脳は外部からの感覚入力と内部の予測モデルを常に比較し、その誤差(予測誤差)を最小化するように働いているとする理論。SSDでは、身体内部感覚に関する予測モデル(思い込み)の比重が過度に大きくなり、実際の感覚入力との間に大きな誤差が生じ、それが症状として知覚されるという仮説が提唱されている。このモデルは、CBTによる認知変容の神経基盤を説明するものとして注目されている。
- 機能的脳画像研究(fMRIなど):
今後の展望
これらのデジタル技術と神経科学的知見を統合し、より個別化された治療法の開発が期待される。例えば、特定の脳機能ネットワークの活動パターンに基づいて、最適なCBTのモジュールを選択したり、ニューロフィードバックなどの技法を組み合わせたりする試みが考えられる。また、依然としてエビデンスが不足している本邦での大規模な疫学研究と臨床研究の推進が急務である 。
【10】国内外ガイドライン比較
SSDに関する主要な治療ガイドラインは、その基本的な推奨事項において多くの共通点を持つ。
| ガイドライン(発行年) | 主な推奨事項 | 特徴 |
| 米国精神医学会 (APA) Practice Guideline for Somatic Symptom and Related Disorders (2014) | ・診断は身体症状だけでなく、心理的・行動的特徴に基づいて行う。 ・プライマリケア医との連携が不可欠。 ・第一選択の心理療法はCBT。 ・薬物療法は併存症(うつ病、不安症)の治療が主目的。 抗うつ薬(SSRI/SNRI)を推奨。 | 精神科医だけでなく、プライマリケア医向けの推奨を重視。 定期的な診察による関係構築の重要性を強調。 |
| 英国国立医療技術評価機構 (NICE) Medically unexplained symptoms (2018年草案) | ・ステップトケアモデルを推奨。 ・低強度介入として、ガイド付きセルフヘルプCBT。 ・高強度介入として、個人CBTまたは集団CBT。 ・薬物療法は第一選択ではなく、CBTが無効な場合や併存症がある場合に限定。 | 費用対効果を重視したステップトケアモデルを明確に提示。 薬物療法の位置づけを心理療法より下位に置いている点が特徴的。 |
| 日本心身医学会 心身症診断・治療ガイドライン (2006) | ・(SSDという診断名はないが)身体表現性障害の項目で、CBT、精神分析的精神療法、薬物療法(抗うつ薬、抗不安薬)などを紹介。 ・多職種連携による全人的医療を推奨。 | 日本の保険診療の実態に合わせた記述。 薬物療法と精神療法の併用を標準的なアプローチとして提示している。 |
比較の要点:
- CBTの推奨:
全てのガイドラインで、SSDに対する最もエビデンスのある心理療法としてCBTが第一に推奨されている。 - 薬物療法の位置づけ:
APAや日本のガイドラインでは、薬物療法(特に抗うつ薬)は心理療法と並行して用いられる標準的な治療選択肢の一つとされている。一方、NICEガイドラインでは、心理療法が優先され、薬物療法は二次的な選択肢と位置づけられている。 - 連携の重視:
いずれのガイドラインも、精神科医と身体科医との連携(リエゾン)の重要性を強調している。
【11】参考文献
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.).
- 永井 良三 (シリーズ総監修), 笠井 清登 (編集). (2021). 精神科研修ノート第3版. 診断と治療社.
- 井上 令一 (監修). (2016). カプラン臨床精神医学テキスト第3版. MEDSI.
- 松崎 朝樹 (著). (2021). 精神診療プラチナマニュアル第3版. MEDSI.
- 大武 陽一 (著). (2019). みんなの心療内科. 中外医学社.
- (2023). こころの健康が見える第1版. MEDIC MEDIA.
- 宮内 倫也. (2020). 「とらわれ」から考えるリエゾン的身体症状症. 医学界新聞.
- 関口 敦. (2023). 身体症状症及び関連症群―心身二元論からの脱却. 精神医学, 65(10), 1395-1402.
- Dimsdale, J. E., Creed, F., Escobar, J., et al. (2013). Somatic symptom disorder: an important change in DSM. Psychosomatics, 54(3), 223-228. (PMID: 23683628)
- Kurlansik, S. L., & Maffei, M. S. (2016). Somatic symptom disorder. American family physician, 93(1), 49–54.
- Kleinstäuber, M., Witthöft, M., & Hiller, W. (2019). Efficacy of cognitive behavioral therapy for medically unexplained symptoms: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 45, 1-15. (PMID: 24525091)
- Luyten, P., Van Houdenhove, B., Lemma, A., et al. (2022). A mentalization-based approach to the understanding and treatment of functional somatic disorders. Psychoanalytic Psychotherapy, 36(3), 217-241.
- Henningsen, P., Zipfel, S., & Herzog, W. (2018). Management of functional somatic syndromes. The Lancet, 369(9565), 946-955. (PMID: 17368156)
2




