体の痛みが続くのに検査では異常なし。それは身体症状症かもしれません。こころの不調が体に現れるこの病気のサインと回復への道筋を解説。
こころと体の警報システム、身体症状症の理解と対処
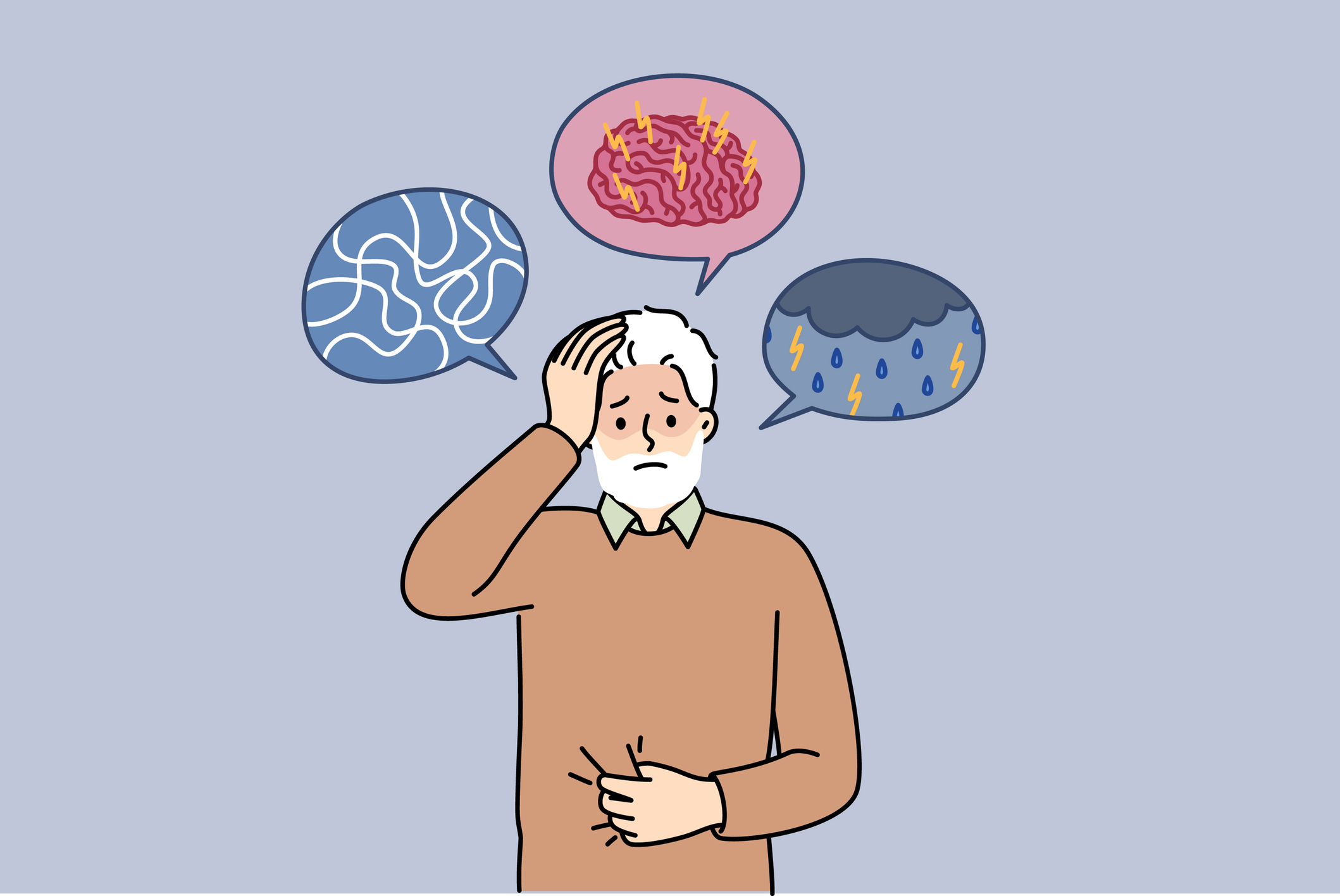
- 多彩な身体の痛み(頭痛、腹痛、腰痛など)
- 感覚の異常(しびれや、感覚が鈍くなる)
- 消化器系の不調(吐き気、下痢、便秘など)
- 全身の倦怠感
- 健康への過剰な不安
- 頻繁な医療機関の受診
1. 身体症状症とは?
こころと体の警報システム
私たちのこころと体は、まるで精密な警報システムのように連携しています。ストレスや心の負担が大きくなると、体は「これ以上は危険だよ」というサインとして、痛みや不快感といった様々なアラームを鳴らします。これが身体症状症の基本的なイメージです 。
例えば、大切なプレゼンの前にお腹が痛くなったり、人間関係の悩みで頭痛が続いたりするのは、多くの方が経験することでしょう。通常、これらの症状は原因となるストレスが去れば自然と和らぎます。
しかし、身体症状症の患者さんの場合、この警報システムが非常に敏感になりすぎて、本来なら気にならないような小さな体の変化にも過剰に反応してしまいます。そして、鳴り響くアラーム(身体症状)そのものに強く気を取られ、「自分は何か重い病気にかかっているに違いない」という思考の迷路にはまり込んでしまうのです。
「気のせい」ではありません
身体症状症の最もつらい点の一つは、周囲から「気のせいだ」「考えすぎだ」と誤解されがちなことです。ご本人にとっては、痛みやしびれ、倦怠感は紛れもない現実であり、耐えがたい苦痛です。しかし、病院で精密検査を受けても、その苦痛に見合うような医学的な異常が見つからないことがほとんどです 。
かつては「医学的に説明のつかない症状」であることが重視されていましたが、現在(DSM-5-TR)ではその考え方が変わりました 。
実際に胃潰瘍やがんなどの身体疾患があっても、その症状に対する不安や悩み、日常生活への影響が、医学的に見て過剰に大きい場合に、身体症状症と診断されることがあります 。これは、「体か、こころか」という二元論から脱却し、両者のつながりを一体として捉える現代の精神医学の流れを反映しています 。

身体症状症は身体的な症状が主訴(一番の悩み事)のため、最初に内科や整形外科などの身体科にかかることがほとんどです。そのため、身体症状から精神的な問題へアプローチする心療内科的な治療が主体となります。
心療内科について詳しく知りたい方はこちらへ
心療内科とは? >>
2. 主な症状
身体症状症の症状は、まさに「十人十色」で、体のあらゆる部分に現れる可能性があります。ここでは代表的な症状を挙げますが、これらが全てではありません。
| 症状のタイプ | 具体的な症状の例 |
| 痛みの症状 | 頭痛、腹痛、背中の痛み、関節痛、胸の痛み、手足の痛みなど、特定の部位や全身に広がる痛み |
| 消化器系の症状 | 吐き気、下痢、便秘、腹部の膨満感、食欲不振 |
| 神経系の症状 | しびれ、めまい、ふらつき、かすみ目、脱力感、喉の詰まり感(ヒステリー球) |
| 全身の症状 | 極度の疲労感、倦怠感、動悸、息切れ |
これらの身体症状に加えて、以下のような
心理面・行動面での特徴が強く現れます。これが身体症状症の核となる部分です 。
- 症状へのとらわれ:
自分の身体の感覚に常に注意が向き、一日中そのことばかり考えてしまう。 - 破局的な解釈:
些細な体の不調を、がんや難病といった「最悪の事態」の兆候だと捉えてしまう 。 - 過剰な健康不安:
自分の健康状態について、常に高いレベルの不安を抱えている 。 - 医療機関への過剰な依存:
一つの病院で「異常なし」と言われても納得できず、安心を求めて次から次へと病院を渡り歩く(ドクターショッピング) 。 - 日常生活への支障:
痛みや不調、あるいはそれに対する不安から、仕事や学業、家事などが手につかなくなり、社会的な活動を避けるようになる 。
3. 原因やきっかけ
身体症状症のはっきりとした原因はまだ解明されていませんが、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています 。
- 遺伝的・生物学的要因:
生まれつき痛みを感じやすい、不安を感じやすいといった体質的な要因が関係している可能性があります。痛みの刺激に対して脳が過敏に反応する傾向も指摘されています 。 - 心理的要因:
ネガティブな感情を抱きやすい性格(神経症的傾向)や、物事を悲観的に捉えやすい認知のクセがリスク因子として知られています 。また、感情を言葉で表現するのが苦手な「失感情症(アレキシサイミア)」 の傾向がある人は、言葉にできない感情が身体の症状として現れやすいと言われています。 - 過去の体験:
幼少期の虐待や、大きな病気・怪我の経験、大切な人との死別といったつらいライフイベントが、こころと体の警報システムを敏感にするきっかけとなることがあります 。 - 社会的・文化的要因:
ストレスの多い社会環境や、病気に対する過剰な情報なども、健康への不安を煽り、発症の一因となる可能性があります。
これらの要因が組み合わさり、何らかのストレス(例:仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家族の問題)が引き金となって、症状が本格的に現れることが多いようです 。
4. 診断の流れ
身体症状症の診断は、患者さんの「苦痛の物語」に丁寧に耳を傾けることから始まります。
- 詳細な問診:
どのような身体症状が、いつから、どのような状況で現れ、それによって日常生活にどれほどの支障が出ているかを詳しくお伺いします。症状に対するご自身の考えや感情(「重い病気ではないか」という不安など)についても共有していただきます 。 - 身体的な診察と検査の確認:
他の身体疾患が隠れていないかを確認することは非常に重要です。そのため、内科など他科で受けた検査結果を確認したり、必要に応じて追加の診察や検査を勧めたりすることがあります 。身体症状症の診断は、他の可能性を慎重に除外した上で行われます。 - 精神医学的評価:
身体症状だけでなく、うつ病や不安症など、他の精神疾患が併存していないかも評価します 。 - 診断基準との照らし合わせ:
最終的に、DSM-5-TRなどの国際的な診断基準に基づき、専門医が総合的に診断します 。診断のポイントは、身体症状そのものの有無だけでなく、その症状に対する患者さんの思考、感情、行動が過剰であったり不適切であったりすることで、著しい苦痛や機能障害が生じている点に置かれます 。
5. 主な治療法
身体症状症の治療のゴールは、症状を完全になくすことだけではありません。症状とうまく付き合いながら、それに振り回されずに、自分らしい生活を取り戻すことを目指します。治療の基本は、医師との信頼関係です。「この先生は自分の苦しみを真剣に受け止めてくれる」という安心感が、回復への第一歩となります 。
認知行動療法(CBT)
身体症状症の治療において、現在最も効果が期待されているのが認知行動療法(CBT)です 。CBTは、症状に対する「考え方のクセ(認知)」と「行動パターン」に焦点を当て、それらをより柔軟で現実的なものに変えていくことで、悪循環を断ち切ることを目指す心理療法です。
【CBTの具体的なステップと理由】
- 心理教育と悪循環の理解(なぜ必要か?)
- 理由:
まず、自分の身に起きていることのメカニズムを正しく知ることが、漠然とした不安を和らげる上で非常に重要です。身体症状症は「体の警報システムが誤作動を起こしている状態」であり、症状自体が命を脅かすものではないことを理解するだけで、不安が大きく軽減することがあります。 - 具体例:
「体の不調(きっかけ)→『大変な病気だ』(破局的思考)→不安・恐怖(感情)→体を過剰にチェックする、活動を避ける(行動)→体の感覚にさらに敏感になる→さらに不調を感じる」という悪循環のモデルを一緒に確認します。患者さん自身の体験に当てはめてみることで、「なるほど、自分もこのサイクルに陥っていたのか」と客観的に自分の状態を捉え直すことができます。
- 理由:
- 認知の再構成(考え方のクセを見直す)
- 理由:
私たちの感情や行動は、出来事そのものではなく、その出来事をどう「解釈」するかによって大きく左右されます。身体症状症の患者さんは、身体感覚を破局的に解釈するクセがついています。この認知のクセを修正することが、不安を和らげる鍵となります。 - 具体例:
- 患者さん:「昨日から背中が痛むんです。これは膵臓がんのサインに違いありません。」(破局的思考)
- 治療者:「背中が痛むと、重い病気ではないかと心配になりますよね。そのお気持ちはよく分かります。ところで、他に考えられる可能性はありますか?例えば、昨日何か重いものを持ったり、慣れない姿勢で作業をしたりしませんでしたか?」(他の可能性を探る)
- 患者さん:「そういえば、週末に庭の草むしりを長時間していました…。」
- 治療者:「なるほど。では、もし友人が同じ状況で『背中が痛い』と言ったら、なんとアドバイスしますか?」(客観的な視点を取り入れる)
- 患者さん:「うーん、『筋肉痛じゃない?少し様子を見たら?』って言うかもしれません。」
- このように対話を通して、「がんの可能性はゼロではないが、筋肉痛の可能性の方がずっと高い」という、より現実的でバランスの取れた考え方(適応的思考)を見つけていきます。
- 理由:
- 行動活性化と曝露療法(行動パターンを変える)
- 理由:
痛みや不安を恐れて活動を避けていると、ますます体力が落ち、気分も落ち込み、症状への注意が強まるという悪循環に陥ります。少しずつ安全な範囲で活動を再開し、「動いても大丈夫だった」という成功体験を積むことが、自信の回復と悪循環の打破につながります。 - 具体例:
- 目標設定:
「腹痛が怖いから」と散歩を避けている患者さんと、「まずは家の周りを5分だけ歩いてみる」という、達成可能な小さな目標を一緒に設定します。 - 曝露(エクスポージャー):
実際に散歩をしてもらい、その際の体の感覚や不安の強さを記録します。「少しお腹が張ったけど、痛みは出なかった」「思ったより大丈夫だった」という体験を振り返り、破局的思考が現実には起こらないことを確認します。 - 活動スケジューリング:
徐々に散歩の時間を延ばしたり、友人とお茶をするなど、これまで避けていたけれど本当は楽しみたい活動をスケジュールに組み込んでいきます。活動量が増えることで、症状へのとらわれが減り、生活の質が向上していきます。
- 目標設定:
- 理由:
近年では、ビデオ会議システムを用いた遠隔でのCBTも、対面と遜色ない効果があることが示されており、通院が困難な方にとっても治療の選択肢が広がっています 。

薬物療法
薬物療法は、CBTと並行して、あるいはCBTの効果を高めるための補助的な役割として行われることが多いです 。
- 抗うつ薬(SSRI、SNRIなど):
うつ病や不安症が併存している場合に特に有効です 。これらの薬は、気分の落ち込みや不安を和らげるだけでなく、痛みを感じる神経の働きを調整し、痛みを軽くする効果も期待できます。効果が出るまでには2週間以上かかることが一般的です 。 - その他の薬:
症状に応じて、抗不安薬や漢方薬などが補助的に用いられることもあります 。ただし、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は依存性の問題があるため、安易な長期使用は避けるべきです 。
薬はあくまで症状をコントロールし、CBTなどの心理療法に取り組みやすくするための「サポート役」と考えることが重要です 。
さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>
6. 回復や再発予防について
身体症状症は、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、時間をかけて回復していくことが多い病気です 。焦らず、一喜一憂せずに、治療を続けることが大切です。
【再発予防のポイント】
- ストレスマネジメント:
自分にとって何がストレスになるのかを理解し、その対処法を身につけることが最も重要です。リラクゼーション法(腹式呼吸、自律訓練法など)を日常に取り入れたり、趣味の時間を持ったりして、こころと体を休ませる習慣をつけましょう。 - 生活リズムの維持:
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、こころと体の警報システムを安定させる土台となります。 - 考え方のクセへの気づき:
CBTで学んだことを時々振り返り、「また破局的な考え方をしていないか?」と自分に問いかける習慣をつけましょう。 - 早期発見・早期対処:
「最近、体の不調が気になるな」「またあの考えにとらわれているな」と感じたら、それは再発のサインかもしれません。悪化する前に、早めに主治医に相談しましょう。
症状がなくなった後も、しばらくは定期的に通院し、安定した状態を維持していくことが、再発を防ぐ上で効果的です。
7. 患者への接し方
ご家族や職場の同僚など、周りの方のサポートは、患者さんの回復にとって非常に大きな力となります。しかし、どのように接すれば良いか戸惑うことも多いでしょう。ここでは、具体的な接し方のヒントをいくつかご紹介します。
まず心がけたい基本姿勢
- 病気を理解する:
「気のせい」「怠けている」といった誤解が、患者さんを最も傷つけ、孤立させます。まずは、身体症状症が、本人の意思ではコントロールできない「病気」であることを理解してください。 - 苦しみを傾聴し、共感する:
患者さんが症状のつらさを訴えたときは、「大変だね」「つらいね」と、まずはその苦しみを受け止めてあげてください。アドバイスや説教は必要ありません。ただ、安心して話せる相手がいるというだけで、患者さんの心は軽くなります。 - 症状ではなく「その人自身」に目を向ける:
会話が症状の話題ばかりになると、本人もますます症状にとらわれがちになります。体調の良い時には、趣味や好きな食べ物、楽しかった思い出など、病気以外の話題に触れ、その人らしい一面に関心を向けてあげてください。

具体的な声かけの例
| やめた方がよい声かけ(理由) | おすすめの声かけ(ポイント) |
| 「気にしすぎだよ」 「考えすぎじゃない?」 (症状を否定されると、理解されていないと感じてしまう) | 「そんなに痛むんだね。つらいね。」 (まずは苦痛に共感する) |
| 「また病院に行くの?この前も異常なかったでしょ?」 (本人は真剣に苦しんでおり、不安から行動している) | 「心配なんだね。先生には何て言われたの?」 (不安な気持ちを受け止め、冷静な対話を促す) |
| 「何か楽しいこと考えなよ」 「元気出して!」 (根性論では解決せず、できない自分を責めてしまう) | 「何か手伝えることはある?」 「少し一緒に散歩しない?」 (具体的な行動を、無理のない範囲で提案する) |
| 「いつになったら治るの?」 (プレッシャーを与え、焦らせてしまう) | 「今日は少し顔色が良いみたいだね」「焦らず、ゆっくりいこうね」 (小さな変化を認め、長い目で見守る姿勢を伝える) |
サポートする側のメンタルヘルスも大切に
患者さんを支えるご家族や同僚の方も、先が見えない状況に疲れやストレスを感じることがあります。一人で抱え込まず、クリニックの相談室や地域の支援機関、自助グループなどを利用し、ご自身の気持ちを話せる場所を持つことが大切です。サポートする側が心身ともに健康であることが、結果的に患者さんへの一番の支援につながります。
8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、身体症状症に悩む方々に対して、以下のようなサポートを提供しています。
- 専門医による診断と治療:
精神科の専門医が、患者さん一人ひとりの状態を丁寧に評価し、最新の知見に基づいた適切な診断と治療方針をご提案します。薬物療法についても、その必要性や副作用について十分に説明し、ご納得いただいた上で進めてまいります。 - 医師による助言と指導:
治療の主体は患者さんご自身です。私たちは、CBTの考え方に基づき、患者さんがご自身の力で症状に対処し、生活の質を向上させていくための具体的な助言や指導(心理教育)を積極的に行います。ご家族からのご相談にも応じ、患者さんを支えるためのアドバイスを提供します。 - リエゾン連携:
必要に応じて、かかりつけの内科など他科の先生方と連携(リエゾン)を取りながら、心身両面からの包括的な治療を目指します。
現在、臨床心理士によるカウンセリング(CBTを含む)は準備中ですが、医師による精神療法の中で、そのエッセンスを取り入れたサポートを行っております。体の不調が長引き、お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



