幻覚や妄想などの症状により、現実との区別がつきにくくなる脳の病気です。お薬と専門家によるサポートで回復を目指せます。一人で抱え込まず、ご相談ください。
思考や感情のまとまりが難しくなる脳の機能的な病気
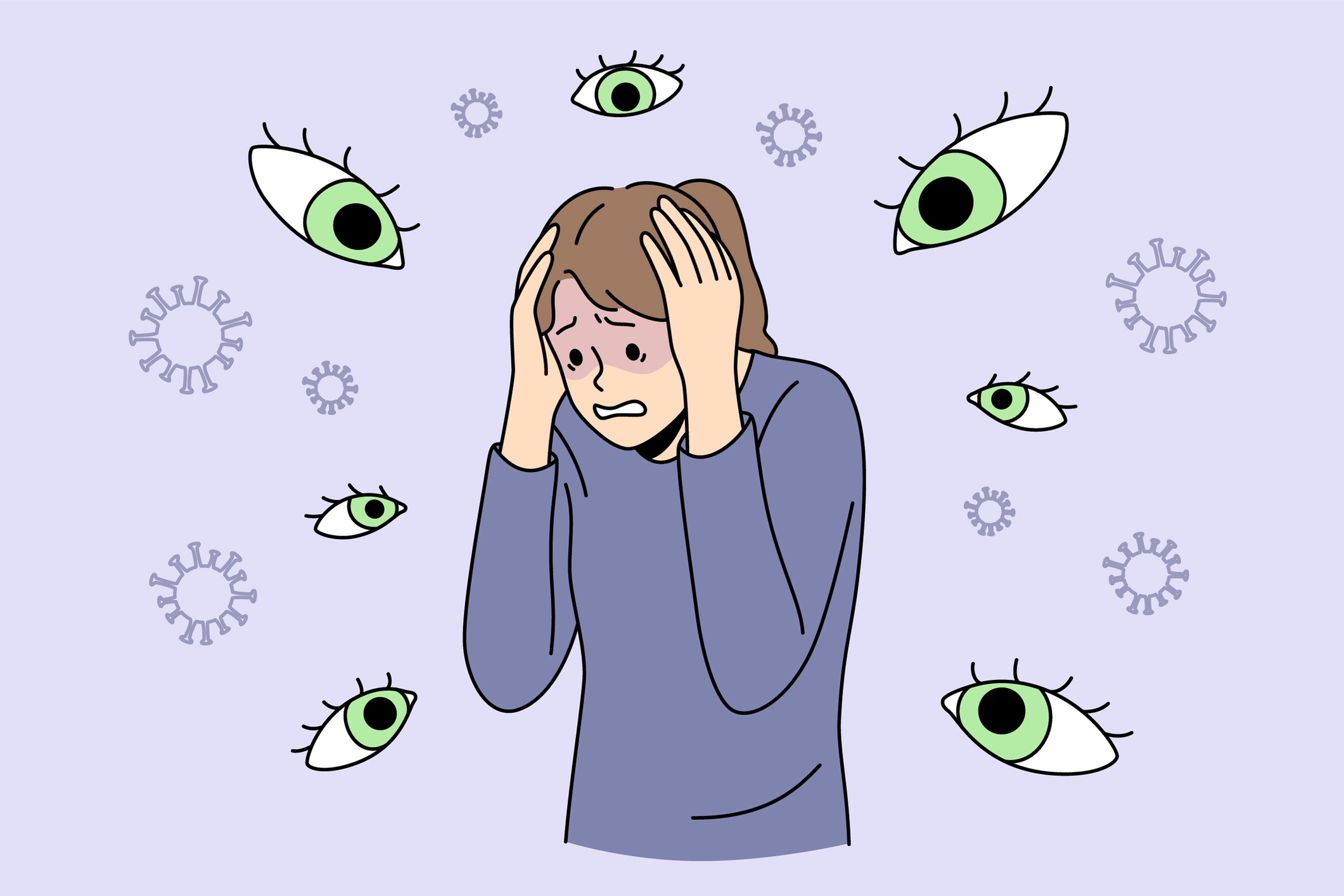
- 幻覚(幻聴)
- 被害妄想
- 人に見られている気がする
- 思考の混乱
- 意欲の低下
- 感情の平板化
- 引きこもり
- 認知機能の低下
- 興奮や苛立ち
- 不眠
【1】疾患概念・定義(DSM-5-TR / ICD-11)
統合失調症は、思考、知覚、感情、意欲、行動など多彩な精神機能の障害を呈する精神疾患である。その本態は、精神機能間の統合が失調した状態と考えられている。
DSM-5-TR
DSM-5-TRでは、統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害群に分類される。診断基準Aでは、以下の5つの症状領域のうち2つ以上(うち少なくとも1つは(1)妄想、(2)幻覚、(3)連合弛緩:まとまりのない発話のいずれか)が1ヵ月間ほとんど常に存在することを要求している。
- 妄想
- 幻覚
- まとまりのない発話
- ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
- 陰性症状(情動表出の減退や意欲欠如)
加えて、社会的・職業的機能の低下(基準B)と、障害の持続的な徴候が前駆期や残遺期を含めて少なくとも6ヵ月間存在すること(基準C)が必要である。また、統合失調感情障害および気分障害の除外(基準D)、物質または他の医学的疾患によるものではないこと(基準E)が求められる。
ICD-11
ICD-11においても、陽性症状、陰性症状、認知機能障害を主要な特徴とし、DSM-5-TRとおおむね同様の診断概念を採用している。
【2】疫学(国内外、有病率、性差、発症年齢)
| 項目 | データ | 出典 |
| 生涯有病率 | 約0.7%(約100人に1人弱) | (WHO) |
| 発症年齢 | 10代後半から30代前半に好発。 男性の方が女性より発症年齢のピークが早い傾向がある。 | (中根, 2007) |
| 性差 | 生涯有病率に大きな男女差はないとされる。 ただし、男性の方がやや早く発症し、陰性症状が目立ちやすい傾向がある。 女性は発症前の社会機能が良好で、全体的な予後も男性より良好とされる。 | (Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry) |
| 社会的影響 | WHOの調査では、障害調整生命年(DALY)において統合失調症は全疾患の中でも上位に位置し、特に先進国での経済的損失が大きい。 日本の精神科入院患者の約半数を占める。 | (厚生労働省患者調査, 2020) |
年齢と発症率
| 年齢(歳) | 男性 発症率(人口1万人対) | 女性 発症率(人口1万人対) |
| 10-14 | (データ不足) | (データ不足) |
| 15-19 | 6.3 | 2.6 |
| 20-24 | 3.9 | 4.4 |
| 25-29 | 4.0 | 1.9 |
| 30-34 | 1.7 | 1.0 |
| 35-39 | 1.0 | 0.9 |
| 40-44 | 1.1 | 0.9 |
| 45-49 | (データ不足) | 0.3 |
| 50-54 | (データ不足) | 0.3 |
出典:中根, 精神神経学雑誌, 2007:109(8)751-758
【3】病因・病態生理(神経生物学・心理社会的要因)
統合失調症は単一の病因による疾患ではなく、遺伝的素因と環境要因が複雑に相互作用する多因子疾患と考えられている。
神経生物学的要因
- 神経伝達物質仮説:
- ドーパミン仮説:
古典的な仮説で、中脳辺縁系ドーパミン経路の過活動が陽性症状に、中脳皮質系経路の機能低下が陰性症状や認知機能障害に関与するとされる。 - グルタミン酸仮説:
NMDA受容体の機能低下が、ドーパミン系の二次的な調節異常を介して症状を引き起こすとする仮説。 - セロトニン仮説:
5-HT2A受容体の関与が指摘されており、非定型抗精神病薬の作用機序の一部を説明する。 - ムスカリン受容体仮説:
近年、M1およびM4ムスカリン受容体を介した神経伝達調節の異常が注目されている。
- ドーパミン仮説:
- 神経発達障害仮説:
遺伝的脆弱性を背景に、周産期の感染症や合併症といった環境要因が脳の神経発達過程に影響を与え、思春期以降の脳の成熟過程で神経回路の脆弱性が顕在化し発症するという仮説。 - 脳構造・機能異常:
- 構造的異常:
側脳室・第三脳室の拡大、海馬や上前頭回などの灰白質体積の減少が報告されている。初回エピソード患者において進行性の脳体積減少が認められるとの報告もある。 - 機能的異常:
前頭前野の機能低下(hypofrontality)が特に知られている。
- 構造的異常:
心理社会的要因
都市環境での生育、移民、小児期の逆境体験(トラウマや虐待)、薬物乱用(特に大麻)などが発症リスクを高める環境要因として知られている。また、家族の感情表出(Expressed Emotion: EE)が高い環境(批判的、敵対的、情緒的に巻き込まれすぎ)は、再発率を高めることが示されている。
【4】臨床症状・経過(典型例・非典型例)
統合失調症の経過は、前駆期、急性期、消耗期、回復期(慢性期)に大別される。
| 病期 | 期間 | 主な症状と状態 |
| 前駆期 | 数ヶ月〜数年 | 不眠、集中困難、意欲低下、不安、抑うつ、引きこもりなど非特異的な症状が主体。 診断基準を満たさない軽度の陽性症状が出現することもある。 |
| 急性期 | 数週間〜数ヶ月 | 幻覚、妄想、興奮などの陽性症状が顕著となり、生活に著しい支障をきたす。 多くの場合、この時期に医療機関を受診し、診断・治療が開始される。 |
| 消耗期(休息期) | 急性期の後 | 急性期の混乱でエネルギーを消耗し、意欲低下、過眠、無気力といった陰性症状が前景に出る。 回復のための重要な休息期間。 |
| 回復期(慢性期) | 消耗期の後 | 陰性症状や認知機能障害が主体となるが、状態は比較的安定する。 再発のリスクを抱えながら、リハビリテーションを通じて社会機能の回復を目指す。 |
長期的な経過は多様であり、約半数は完全または軽度の障害を残して回復するとされるが、再燃と寛解を繰り返す例も多い。
【5】鑑別診断と評価尺度
診断は、DSM-5-TRまたはICD-11の診断基準に基づき、臨床症状と経過を総合的に評価して行われる。【1】で述べた基準に加え、他の精神疾患や身体疾患との鑑別が重要である。
評価尺度
症状の重症度や機能レベルを客観的に評価するために、以下の尺度などが用いられる。
| 評価尺度名 | 略称 | 評価対象 |
| 陽性・陰性症状評価尺度 | PANSS | 陽性症状、陰性症状、総合的精神病理の重症度 |
| 統合失調症認知機能簡易評価尺度 | BACS | 認知機能障害の評価 |
| 臨床全般印象評価尺度 | CGI | 疾患の全般的な重症度と治療による変化 |
| 機能の全体的評定尺度 | GAF | 心理的・社会的・職業的機能の全体的水準 |
鑑別診断
| 鑑別すべき疾患 | 鑑別のポイント |
| 身体疾患 | 甲状腺機能亢進症、自己免疫疾患(SLEなど)、脳炎、脳腫瘍、てんかん など。 身体診察、血液検査、画像検査が必須。 |
| 物質誘発性精神病性障害 | 覚醒剤、大麻、アルコールなどの使用・離脱。 薬物スクリーニング検査が有用。 |
| 双極性障害・うつ病(精神病症状を伴う) | 気分エピソード(躁・うつ)が精神病症状と独立して存在するか、どちらが優勢かを経時的に評価する。 |
| 統合失調感情障害 | 統合失調症の症状と気分エピソードが同時に存在し、かつ気分エピソードがない期間にも2週間以上の妄想・幻覚が存在する。 |
| 妄想性障害 | 奇異ではない妄想が主症状で、幻覚や陰性症状は目立たず、社会機能の低下も限定的。 |
| 発達障害(特に自閉スペクトラム症) | 社会的コミュニケーションの質的障害や限定された興味が幼少期から認められる。 鑑別が困難な場合も多い。 |
【6】検査(心理検査・画像・血液)
診断は臨床症状に基づいて行われるが、補助診断や鑑別診断、重症度評価のために以下の検査が行われることがある。
- 心理検査:
WAIS-IV(知能検査)、BACS(認知機能検査)、ロールシャッハ・テストなどが、認知機能やパーソナリティの評価に用いられる。 - 画像検査:
頭部CTやMRIは、脳腫瘍や脳血管障害など器質的疾患の除外のために必須である。研究レベルでは、fMRIやMRS、PETを用いた脳機能の研究が進んでいる。 - 脳波検査:
てんかんや意識障害との鑑別に有用。 - 血液検査:
身体疾患(甲状腺機能、肝・腎機能など)や薬物の影響を評価するために行われる。
【7】治療(薬物療法、心理社会的介入、入院適応)
薬物療法
抗精神病薬が治療の中心となる。急性期の陽性症状の改善、および寛解後の再発予防に不可欠である。原則として単剤投与が推奨される。
| 世代 | 薬剤の種類 | 特徴 | 主な副作用 |
| 第一世代(定型)抗精神病薬 | ハロペリドール クロルプロマジン など | 主にドーパミンD2受容体を遮断 陽性症状に有効 | 錐体外路症状(EPS)(パーキンソニズム、アカシジア、急性ジストニア) 遅発性ジスキネジア 高プロラクチン血症 |
| 第二世代(非定型)抗精神病薬 | リスペリドン オランザピン クエチアピン アリピプラゾール など | ドーパミンD2受容体とセロトニン5-HT2A受容体を遮断(SDA) 陽性症状に加え、陰性症状や認知機能障害にも一定の効果が期待される EPSが少ない | 代謝系副作用(体重増加、糖尿病、脂質異常症)、眠気、起立性低血圧など 薬剤により副作用プロファイルは異なる |
心理社会的介入
薬物療法と並行して行われ、機能的回復(リカバリー)を促進する。
- 心理教育:
患者・家族が疾患や治療について正しく理解し、主体的に治療に取り組めるよう支援する。 - 認知行動療法(CBT):
妄想や幻聴に対する認知の歪みを修正し、症状への対処能力を高める。 - 社会生活技能訓練(SST):
対人関係や問題解決など、社会生活に必要な具体的なスキルを練習する。 - 認知機能リハビリテーション:
注意力や記憶力などの認知機能を改善するための訓練を行う。 - 家族療法:
家族内のコミュニケーションを改善し、EEを低下させることで再発リスクを軽減する。 - デイケア・作業療法:
日中の活動の場を提供し、生活リズムの安定や対人交流の促進を図る。
入院適応
- 幻覚・妄想が著しく、現実検討能力が著しく損なわれている場合
- 興奮が激しく、自傷・他害のおそれがある場合
- 拒食や引きこもりにより生命・身体の危険が差し迫っている場合
- 診断や治療方針の決定のために集中的な観察が必要な場合
- 十分な休養がとれる環境が確保できない場合
【8】予後・再発予防(機能予後含む)
統合失調症の長期的な予後は個人差が大きい。Kraepelinが提唱した早発痴呆の概念では進行性の悪化が想定されたが、Bleulerは必ずしも悪化するとは限らないと指摘した。近年の長期予後研究では、約20-25%は良好な回復を示し、約50%は中等度の改善を示すが、残りの25-30%は転帰不良であるとされる。
良好な予後因子としては、急性の発症、発症年齢が高い、病前の社会適応が良好、明らかな誘因がある、家族のサポートがあることなどが挙げられる。一方、潜行性の発症、若年発症、病前の社会適応不良、陰性症状が前景に立つ、認知機能障害が重い、家族のEEが高いことなどは予後不良因子とされる。
再発予防が最も重要な課題であり、その鍵はアドヒアランスの維持である。症状が安定しても自己判断で服薬を中断すると、高い確率で再発する。持効性注射剤(LAI)は、服薬管理が困難な症例においてアドヒアランスを確保し、再発を予防する上で有用な選択肢である。
【9】最新研究動向(過去5年)と今後の展望(2025年時点)
- 新規治療薬の開発:
- ムスカリン受容体作動薬:
ドーパミン系を直接標的としない新しい作用機序の薬剤として、M1/M4ムスカリン受容体作動薬(例:KarXT/xanomeline-trospium)が注目されている。第3相臨床試験で陽性症状および陰性症状に対する有効性が示され、従来の抗精神病薬とは異なる副作用プロファイルを持つことから、新たな治療選択肢として期待されている。 - トレースアミン関連受容体1(TAAR1)作動薬:
TAAR1を介したドーパミン、セロトニン、グルタミン酸神経伝達の調節作用を持つ薬剤の研究が進んでいる。
- ムスカリン受容体作動薬:
- 客観的診断補助法の開発:
脳波(例:ミスマッチ陰性電位)、NIRS(近赤外線スペクトロスコピー)、血中バイオマーカーなどを用いた、診断や治療反応性予測のための客観的指標の開発研究が進行中である。 - 神経刺激療法の応用:
rTMS(反復経頭蓋磁気刺激法)による、薬物抵抗性の幻聴や陰性症状に対する治療応用が研究されている。特に、間欠的シータバースト刺激(iTBS)の有効性を示唆するメタ解析が報告されている。 - 病態研究:
- ゲノムワイド関連解析(GWAS)により、多数の疾患感受性遺伝子が同定され、免疫系やシナプス機能に関連する遺伝子の関与が示唆されている。
- 患者由来iPS細胞を用いた疾患モデルの作成により、神経発達段階の異常を分子レベルで解明する研究が進んでいる。
今後の展望
個別化医療の実現が大きな目標である。将来的には、バイオマーカーを用いて個々の患者の病態を評価し、最も効果的で副作用の少ない治療法を選択できるようになることが期待される。また、発症リスクが高い個人(at-risk mental state: ARMS)を同定し、発症そのものを予防する早期介入研究も重要な課題である。
【10】国内外ガイドライン比較
| ガイドライン | 発行元 | 特徴 |
| 統合失調症薬物治療ガイドライン | 日本神経精神薬理学会 | 日本の実臨床に即した薬物療法のアルゴリズムを提示。 単剤化・至適用量の遵守を推奨。 副作用モニタリングの重要性を強調。 |
| APA Practice Guideline for the Treatment of Schizophrenia | 米国精神医学会(APA) | 薬物療法と心理社会的療法を組み合わせた包括的治療を推奨。 エビデンスレベルに基づいた詳細な推奨事項を提示。 患者中心の共同意思決定(Shared Decision Making)を重視。 |
| NICE Guideline [Schizophrenia] | 英国国立医療技術評価機構(NICE) | 費用対効果の観点も重視。 CBTの早期導入を強く推奨。 家族介入の重要性を強調。 患者と家族への情報提供と支援を手厚く規定。 |
各国のガイドラインは、薬物療法と心理社会的療法の併用を推奨する点で共通しているが、推奨される治療の優先順位や介入のタイミングには若干の違いが見られる。日本のガイドラインは薬物療法に重点が置かれているが、APAやNICEではCBTや家族介入といった心理社会的介入の早期導入がより強く推奨される傾向にある。
【11】参考文献・引用論文
- 『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』日本精神神経学会 (日本語版用語監修), 髙橋三郎, 大野裕 (訳), 医学書院, 2023.
- 『精神科研修ノート 第3版』永井良三 (シリーズ総監修), 笠井清登 (編集), 診断と治療社, 2021.
- 『カプラン臨床精神医学テキスト DSM-5診断基準の臨床への展開 第3版』B.J.サドック, V.A.サドック, P.ルイス (著), 井上令一 (監修), メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2016.
- 『精神診療プラチナマニュアル 第3版』松崎朝樹 (著), メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2020.
- 『こころの病気 みかた・治し方』大野裕 (著), PHP研究所, 2016.
- 『こころの健康が見える』医療情報科学研究所 (編集), メディックメディア, 2024.
- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision. American Psychiatric Publishing, 2022.
- World Health Organization: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Revision. 2019.
- 中根允文: 発病・再発および経過に関わるライフイベント. 精神神経学雑誌, 109(8), 751-758, 2007.
- 上島国利: 向精神薬. 精神神経学雑誌, 109(6), 604-608, 2007.
- 大森哲郎: 臨床現場と臨床エビデンスとの近くて遠い距離. 精神神経学雑誌, 106(7), 923-927, 2004.
2




