怖い体験の後、その記憶が何度も蘇り、不安や緊張が続く病気です。眠れない、イライラするなどの症状があれば、一人で抱え込まずにご相談ください。
命の危険を感じる体験後に続く、心の傷の物語

- 記憶が突然よみがえる
- 悪夢を繰り返し見る
- 関連する場所や話題を避ける
- 常に神経が張り詰めている
- ささいなことで驚いてしまう
- 感情が麻痺したように感じる
- 自分や他人を過剰に責めてしまう
- イライラして怒りっぽくなる
1. PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?
PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)は、命の危険を感じたり、自分ではどうしようもない圧倒的な出来事(トラウマ)を体験した後に、心身にさまざまな不調が現れる病気です。
例えるなら、心に深い「怪我」を負った状態です。身体の怪我が治るのに時間が必要なように、心の怪我も回復には時間と適切な手当てが必要です。けがをした部分が、何かの拍子にズキズキ痛むように、PTSDの患者さんも、ふとした瞬間に辛い記憶が蘇り、苦しんでしまうのです。
この病気は、特別な人だけがなるわけではありません。誰にでも起こりうる病気であり、決して本人の「弱さ」や「気のもちよう」が原因ではありません。トラウマ体験によって脳のシステムが一時的にうまく働かなくなり、自分では感情や記憶のコントロールが難しくなってしまう状態なのです。大切なのは、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることです。
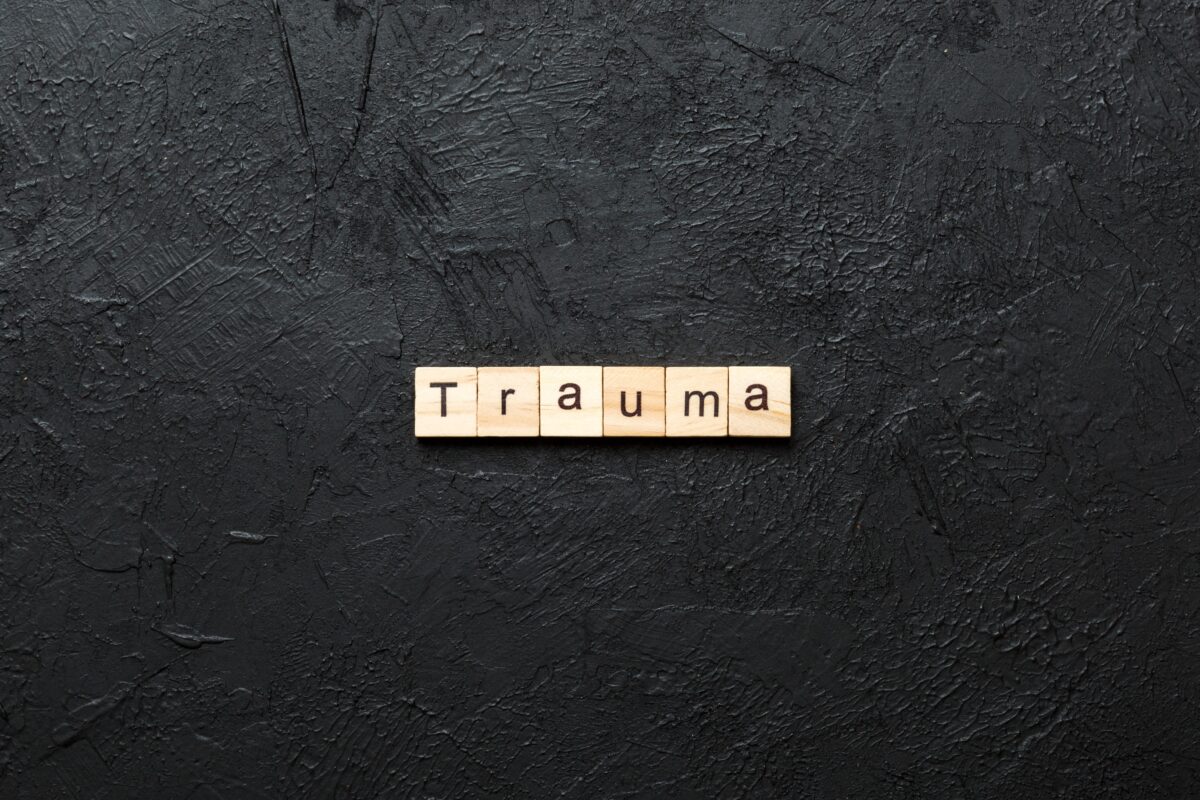
2. 主な症状
PTSDの症状は、大きく分けて4つのタイプがあります。これらの症状が1ヶ月以上続き、日常生活に支障が出ている場合に診断が考えられます。
侵入症状(再体験)
トラウマ体験が、自分の意思とは関係なく繰り返し思い出される症状です。「心の傷口が開いてしまう」ような状態と言えます。
- フラッシュバック:
まるで今、その出来事が再び起きているかのように、生々しく記憶が蘇ります。映像だけでなく、音や匂い、体の感覚を伴うこともあります。 - 悪夢:
トラウマ体験に関連した恐ろしい夢を繰り返し見ます。 - 苦痛な記憶:
出来事のことを思い出すと、強い精神的・身体的苦痛を感じます(動悸、冷や汗、震えなど)。

回避症状
辛い記憶を思い出させるような人、場所、物、会話などを無意識のうちに、あるいは意図的に避けるようになります。「痛む傷口に触れないようにかばう」行動に似ています。
- 内的回避:
トラウマについて考えたり、感じたりするのを避けます。 - 外的回避:
出来事を思い出すきっかけになる場所、人、物などを避けます。例えば、事故現場に近づけない、関連するニュースを見られないなどです。
認知と気分の陰性変化
物事の考え方や感じ方が、否定的な方向へ変わってしまう症状です。トラウマ体験によって「世界を見る色眼鏡が灰色になってしまった」ような状態です。
- 記憶の問題:
トラウマ体験の重要な部分を思い出せなくなります。 - 否定的な信念:
「自分はダメな人間だ」「誰も信用できない」といった、自分や他人、世界に対する過剰に否定的な考えにとらわれます。 - 感情の麻痺:
喜びや愛情といったポジティブな感情を感じにくくなります。 - 孤立感:
周りの人から孤立している、疎遠になっていると感じます。
覚醒度と反応性の著しい変化
常に神経が張り詰めていて、心と体がリラックスできない状態です。「いつ敵が襲ってくるかわからない」と常に警戒しているような状態です。
- 過剰な警戒心:
常に周りをキョロキョロと警戒してしまいます。 - 驚愕反応:
ささいな物音などに、過剰にビクッと驚きます。 - 集中困難:
注意を維持することが難しくなります。 - 睡眠障害:
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めるなどの症状が見られます。 - イライラと怒り: 些細なことでカッとなり、怒りを爆発させてしまうことがあります。

3. 原因やきっかけ
PTSDの直接的な原因は、強烈な恐怖や無力感を伴う「トラウマ体験」です。具体的には、以下のような出来事が挙げられます。
- 自然災害: 地震、津波、台風、洪水など
- 事故: 交通事故、火災、労災事故など
- 犯罪被害: 暴力、強盗、性的暴行、監禁など
- 虐待: 身体的・精神的・性的虐待、ネグレクト(育児放棄)
- 戦争や紛争: 兵士としての体験、紛争地域での生活
- その他: 大切な人の突然の死、重い病気の診断など
これらの出来事を直接体験するだけでなく、他人が体験するのを目撃したり、家族や親しい人が体験したことを聞いたりすることでも発症する可能性があります。 トラウマ体験をした人が全員PTSDになるわけではありません。しかし、それは本人の強さ・弱さの問題ではなく、体験の深刻さ、もともとの性格、周りのサポートの有無など、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
4. 診断の流れ
「もしかしてPTSDかもしれない」と感じたら、まずは専門の医療機関(精神科・心療内科)に相談することが第一歩です。
- 問診:
診断で最も大切なのは、医師による丁寧な問診です。- どのような出来事があったか:
無理に話す必要はありません。話せる範囲で、きっかけとなった出来事についてお伺いします。 - 現在の症状:
いつから、どのような症状で困っているかを詳しくお聞きします。「主な症状」で挙げたような内容について、具体的なエピソードを交えて教えていただけると、より正確な診断につながります。 - 生活への影響:
症状によって、仕事や学業、家庭生活にどのような支障が出ているかをお伺いします。 - これまでの経過:
症状が現れてから、どのように過ごしてきたか、他の病気の経験などについてもお聞きします。
- どのような出来事があったか:
- 心理検査:
必要に応じて、質問紙形式の心理検査(チェックリスト)などを行い、症状の重さや状態を客観的に評価することがあります。 - 診断:
問診や検査の結果を総合的に判断し、国際的な診断基準(DSM-5-TRなど)に基づいて診断を行います。PTSDの診断だけでなく、うつ病や不安症など、他の病気が隠れていないかも含めて慎重に判断します。
診断は、患者さんを型にはめるために行うのではありません。あなたの苦しみの正体を明らかにし、最適な治療法を見つけるための大切なプロセスです。
5. 主な治療法
PTSDの治療は、大きく分けて「心理療法」と「薬物療法」の2つの柱があります。どちらか一方だけでなく、両方を組み合わせて行うことが効果的です。治療の目標は、症状を和らげ、穏やかな日常生活を取り戻すことです。
心理療法(カウンセリング)
専門家との対話を通じて、トラウマ記憶との向き合い方を学び、考え方や感情のコントロール方法を身につけていく治療法です。PTSD治療の根幹をなすもので、特に「トラウマ焦点化心理療法」と呼ばれる、トラウマ記憶に焦点を当てた治療法が高い効果を示すことがわかっています。
- 持続エクスポージャー(PE)療法:
安全が保証された環境で、専門家のサポートのもと、避けてきたトラウマの記憶や状況にあえて向き合います。最初は辛いですが、繰り返すことで「思い出しても危険ではない」ことを脳が学習し、恐怖や不安が少しずつ和らいでいきます。 - 認知処理療法(CPT):
トラウマ体験によって生じた「自分は汚れている」「世の中は危険だ」といった、極端で偏った考え方(認知のゆがみ)に焦点を当て、より現実的でバランスの取れた考え方ができるようにサポートします。 - EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法):
専門家が指を左右に動かすのを眼で追いながら、トラウマの記憶を思い浮かべるという少し特徴的な治療法です。脳に適切な処理を促し、辛い記憶を「過去の出来事」として適切に整理する手助けをすると考えられています。

薬物療法
心理療法と並行して、お薬の力を借りることも有効です。お薬は、いわば「心の治癒力を高めるためのお守り」のようなものです。過敏になった神経を落ち着かせ、不安や落ち込みを和らげることで、患者さんが安心して心理療法に取り組める土台を作ります。
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬):
「抗うつ薬」の一種で、PTSD治療の第一選択薬です。脳内の神経伝達物質であるセロトニンのバランスを整えることで、不安、気分の落ち込み、衝動性などを改善する効果が期待できます。効果が出るまでに数週間かかることがありますが、継続して服用することが大切です。 - その他の薬:
悪夢がひどい場合にはそれを抑える薬、気分の波が激しい場合には気分を安定させる薬など、個々の症状に合わせてお薬が処方されることもあります。
注意が必要な薬:
ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、一時的に不安を和らげる効果がありますが、依存のリスクがあるため、PTSDの治療では長期的な使用は推奨されていません。
さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>

6. 回復や再発予防について
PTSDからの回復は、一直線の道のりではありません。良くなったり、少し後退したりを繰り返しながら、ゆっくりと進んでいきます。大切なのは、焦らず、ご自身のペースで治療を続けることです。
回復のために大切なこと
- 安心できる環境:
まずは、心と体を休ませ、安全だと感じられる環境を整えることが重要です。 - 治療への参加:
医師やカウンセラーを信頼し、治療に主体的に参加することが回復への近道です。わからないことや不安なことは、遠慮なく質問してください。 - 生活リズムを整える:
決まった時間に起き、食事をとり、適度な運動を心がけるなど、生活リズムを整えることは心の安定につながります。 - 自分を責めない:
症状が出るのは病気のせいで、あなたのせいではありません。「なぜ治らないんだ」と自分を責めないようにしましょう。
再発を予防するために
治療によって症状が落ち着いた後も、ストレスなどがきっかけで再発することがあります。再発を防ぎ、穏やかな状態を維持するためには、以下のことを心がけると良いでしょう。
- ストレス対処法を身につける:
音楽を聴く、散歩をする、深呼吸をするなど、自分なりのリラックス方法を見つけておきましょう。 - サポートシステムを持つ:
家族や友人、自助グループなど、困った時に話せる相手や場所を確保しておきましょう。 - 不調のサインに気づく:
「最近よく眠れない」「イライラすることが増えた」など、不調のサインに早めに気づき、必要であれば医療機関に相談することが大切です。 - 自己判断で薬をやめない:
症状が良くなったと感じても、自己判断で薬を中断すると、症状がぶり返すことがあります。お薬をやめる際は、必ず医師と相談してください。
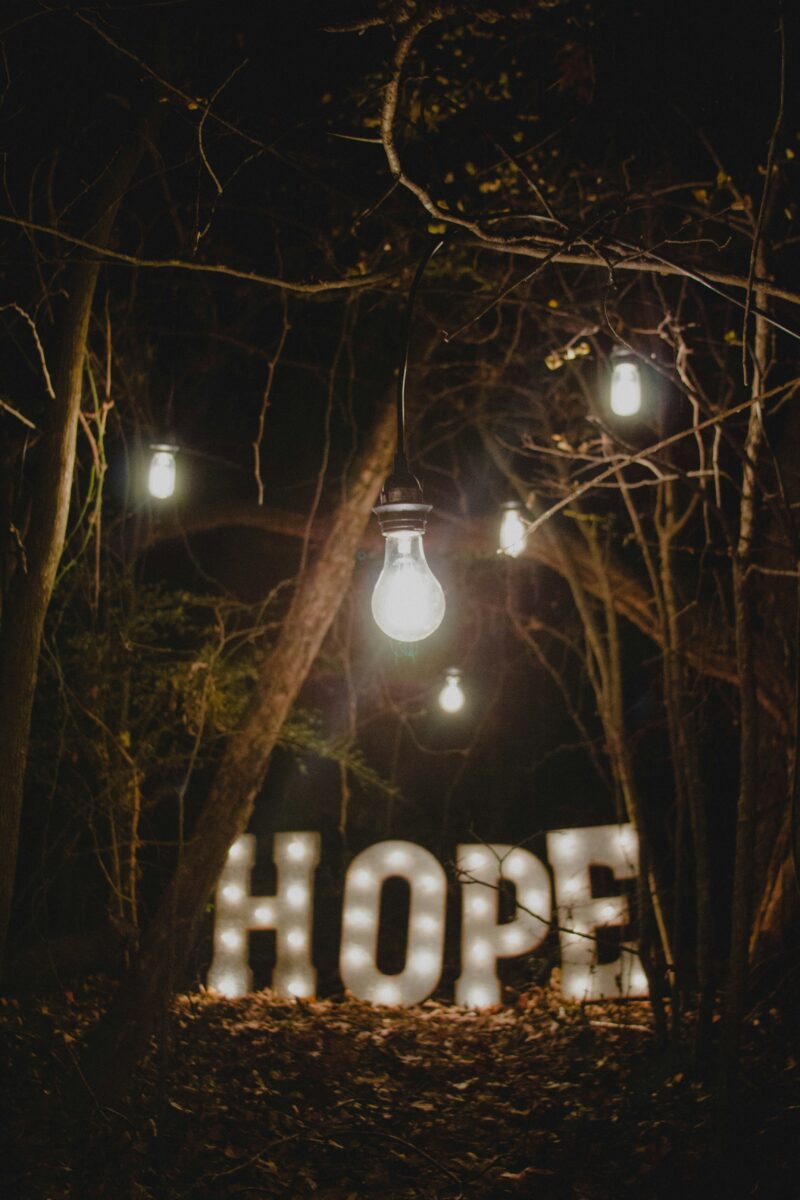
回復の道のりは一人ひとり違います。あなたのペースで、一歩一歩進んでいきましょう。
7. 患者さんへの接し方(家族や同僚向け)
ご家族や身近な方がPTSDと診断された時、どう接すれば良いか戸惑うのは当然のことです。ここでは、患者さんを支える上で大切な心構えと具体的な接し方について、理由も交えて詳しく解説します。
基本となる3つの心構え
| 心構え | なぜ? | どうすれば? |
|---|---|---|
| 安全な「基地」になることを目指す | PTSDの患者さんは、世界が危険な場所だと感じ、常に心と体が緊張状態にあります。 そんな中で、家族や同僚は「ここは安全だ」「この人の前では安心できる」と感じられる心の安全基地になることが、何よりも回復の助けになります。 | 穏やかな態度で、患者さんの存在そのものを肯定的に受け止める姿勢を見せましょう。 |
| 病気への理解を深める | イライラや引きこもり、突然の涙といった行動は、本人の性格が変わったのではなく、病気の症状です。 そのことを理解しているだけで、支える側の心の負担が軽くなり、冷静に対応できるようになります。 | 書籍や信頼できるウェブサイトで病気について学んだり、可能であれば医師の説明に同席したりして、正しい知識を得ましょう。 |
| 無理強いせず、本人のペースを尊重する | トラウマ体験は、患者さんにとってコントロールを失った圧倒的な経験です。 そのため、回復の過程では「自分で決める」「自分でコントロールできる」という感覚を取り戻すことが非常に重要になります。 良かれと思って無理強いすることは、その感覚を再び奪い、症状を悪化させる可能性があります。 | 何かを提案することはあっても、最終的な決定は本人に委ねましょう。 「こうすべきだ」ではなく、「こうしてみるのはどうかな?」というスタンスが大切です。 |

具体的な対応例:ご家族の場合
| 状況 | やってほしい対応(OKな例) | やってはいけない対応(NGな例) | 理由 |
| 患者さんがトラウマについて話そうとしている時 | 静かに、遮らずに耳を傾ける。 「話してくれてありがとう」 「それは辛かったね」 と気持ちに寄り添う。 | 「いつまで引きずっているんだ」「もっとポジティブに考えなよ」 「私の時なんて…」 と話を遮ったり、矮小化したりする。 | 患者さんは勇気を出して話しています。 内容を評価したり、自分の経験と比較したりせず、ただ「聞く」ことに徹することで、安心感と信頼感が生まれます。 |
| 何も話さず、引きこもっている時 | 「元気ないみたいだけど、何かあった?」 「話したくなったら、いつでも聞くからね」 と声をかけ、そっとしておく。 | 「いつまでもメソメソするな」 「無理にでも外に出なさい」 と無理やり部屋から出そうとする。 | 回避は症状の一つです。無理に行動させようとすると、かえって不安を強めます。 「あなたの味方だよ」というメッセージを伝えつつ、本人が動き出すのを待つ姿勢が大切です。 |
| ささいなことでイライラし、怒りをぶつけてきた時 | 「症状のせいなんだ」と理解し、冷静に受け止める。 「イライラしているんだね。 少し一人になろうか」と物理的に距離をとる。 | 「何なのその態度は!」と感情的に言い返す。 | 過覚醒症状によるもので、あなたへの個人的な攻撃ではありません。 感情で返すと悪循環に陥ります。 安全を確保し、嵐が過ぎ去るのを待つイメージで対応しましょう。 |
| フラッシュバックを起こしている時 | 「大丈夫だよ、ここは安全な家だよ」 「今、目の前に私が見える?」 と優しく声をかけ、現実に意識を戻す手伝いをする。 | パニックになって大声を出したり、体を強く揺さぶったりする。 | 患者さんは過去の恐怖を再体験しています。 まずは安心させることが最優先です。 五感に働きかけ(冷たいタオルを渡す、温かい飲み物を勧めるなど)、 意識を「今、ここ」に戻す手助けをします。 |
| 何かを過剰に怖がったり、避けたりする時 | 「怖かったんだね」とその気持ちを否定せず受け止める。 「もしできそうなら、一緒に行ってみる?」 と本人の意思を尊重しつつ提案する。 | 「大丈夫だから、行きなさい」 「そんなの気のせいだよ」 と恐怖心を否定し、無理に行動を促す。 | 恐怖心や回避行動を頭ごなしに否定されると、患者さんは「理解してもらえない」と心を閉ざしてしまいます。 まずは気持ちを受け止め、小さな一歩をサポートする姿勢が重要です。 |
支えるあなた自身のために(セルフケア) ご家族もまた、患者さんを支える中で大きなストレスを感じます。これを「二次受傷」と呼ぶこともあります。
- 一人で抱え込まない:
家族会や支援団体、専門家に相談し、悩みを共有しましょう。 - 自分の時間を持つ:
趣味の時間や友人と会う時間など、意識的に介護から離れる時間を作りましょう。 - 完璧を目指さない:
「自分が何とかしなければ」と背負いすぎないでください。専門家の力を借りながら、できる範囲でサポートすることが、結果的に長い目で見た支えになります。
具体的な対応例:職場の同僚・上司の場合
| 状況 | 望ましい対応 | 避けるべき対応 | 理由 |
| 本人から病気のことを打ち明けられた時 | 「話してくれてありがとう。プライバシーは守るよ」 「何か配慮が必要なことがあれば、無理のない範囲で教えてほしい」と伝える。 | 「え、そうなの?」と過剰に驚いたり、 「大丈夫?」と根掘り葉掘り聞いたり、他の同僚に話したりする。 | 信頼して打ち明けてくれた勇気に応え、安心感を与えることが大切です。 プライバシーの保護は絶対です。 |
| 仕事中に集中できていない、ぼーっとしている時 | 「少し疲れているみたいだね。休憩したら?」 「何か手伝えることはある?」とさりげなく声をかける。 | 「集中しろ!」 「またミスしてるぞ」と強く叱責する。 | 集中困難も症状の一つです。 本人が一番もどかしく感じています。 プレッシャーをかけるのではなく、現実的なサポートを申し出る方が効果的です。 |
| 特定の音や状況に過敏に反応している時 | (上司として)可能であれば、本人のトリガー(きっかけ)となる刺激が少ない席への移動や、業務内容の調整を検討する。 | 「気にしすぎだよ」 「我慢しろ」と個人の問題として片付ける。 | 職場環境の調整は、本人が安心して働くために非常に重要です。 合理的な配慮の範囲で、できることを探しましょう。 |
| 急な体調不良で休む連絡があった時 | 「わかりました。 お大事に」とシンプルに受け止める。 | 「またか」「仕事はどうするんだ」と嫌味を言ったり、休んだ理由を詳しく詮索したりする。 | PTSDの症状は波があります。 体調が悪い時は休むことが必要です。 安心して休める環境があることが、結果的に安定した就労につながります。 |
患者さんを特別扱いしすぎる必要はありません。一人の同僚として尊重し、病気の症状に対して少しの理解と配慮を示すことが、本人にとって大きな支えとなります。

8. 当院でできること
神楽坂メンタルクリニックでは、PTSDでお悩みの患者さん一人ひとりに寄り添い、専門的な立場から回復のお手伝いをいたします。
- 専門医による丁寧な診断:
PTSDの診断は、患者さんのお話を丁寧にお伺いすることから始まります。国際的な診断基準に基づき、他の疾患との鑑別も含めて慎重に診断を行います。 - エビデンスに基づいた薬物療法:
PTSD治療の第一選択薬であるSSRIを中心に、患者さんそれぞれの症状や状態に合わせて、最適な薬物療法を提案・調整いたします。お薬の効果や副作用について、分かりやすくご説明しますのでご安心ください。 - 医師による助言と指導:
治療を進めるにあたっての不安や悩み、日常生活で気をつけることなどについて、医師が親身に相談に応じ、具体的なアドバイスを行います。ご家族からのご相談にも対応いたします。 - 安心できる治療環境:
患者さんが安心して治療に専念できるよう、プライバシーに配慮し、温かく落ち着いた環境づくりを心がけています。
つらい記憶に一人で苦しんでいませんか。その苦しみは、決してあなたのせいではありません。当院と一緒に、穏やかな日常を取り戻すための一歩を踏み出してみませんか。どうぞお気軽にご相談ください。
※現在、当院では臨床心理士による専門的なカウンセリングや心理療法は準備中です。しかし、治療において心理的なサポートが必要不可欠であることは十分に認識しており、医師による精神療法的なアプローチや生活指導を通じて、患者さんの心のケアに努めてまいります。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。
1
2



