強迫症は、不合理とわかっていても特定の考え(強迫観念)や行動(強迫行為)を繰り返してしまう病気です。専門的な治療で改善が可能です。
「やめたいのに、やめられない」考えや行動に支配される病気
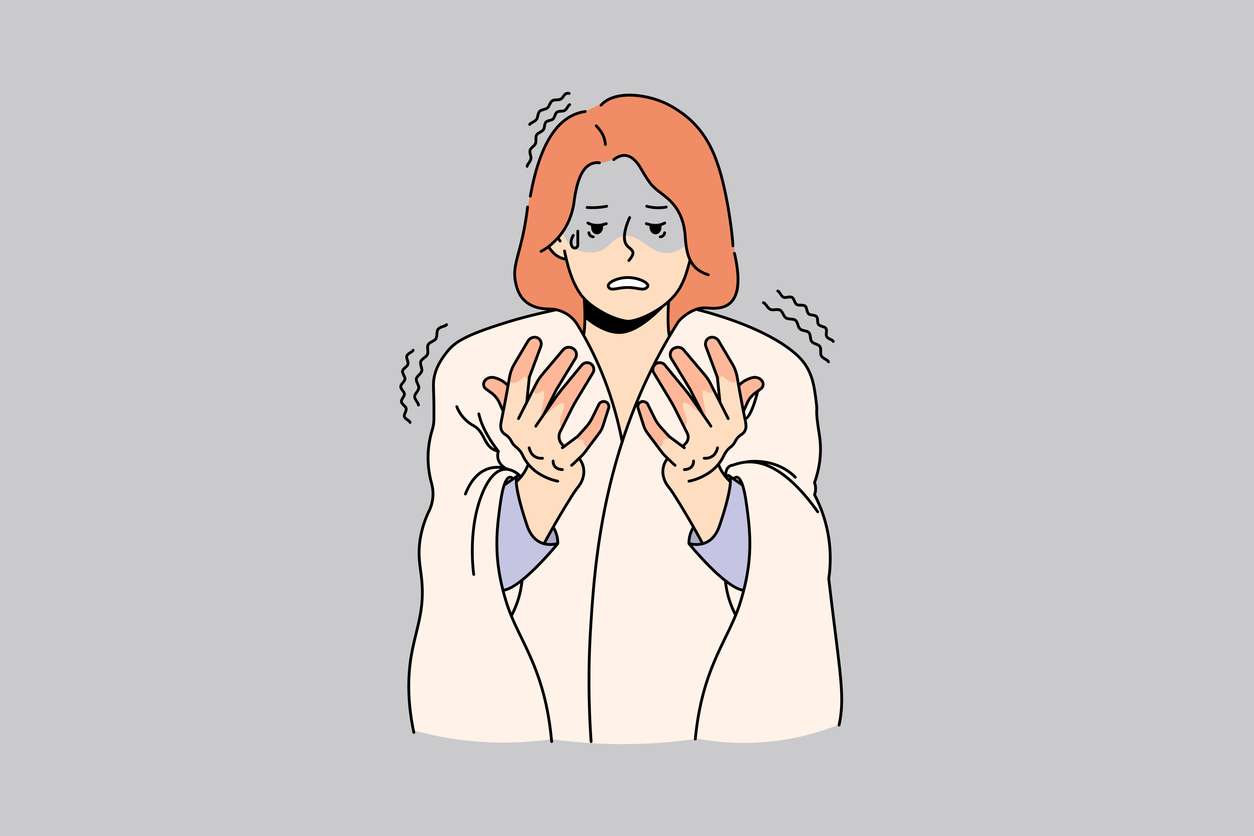
- 汚れが気になる
- 何度も確認する
- 左右対称にこだわる
- 数字にこだわる
- 物を溜め込む
- 縁起の悪いことを考える
- 鍵などをかけたか不安になる
- 誰かを傷つけないか心配
【1】疾患概念・定義(DSM-5-TR・ICD-11)
強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder: OCD)は、精神疾患の診断・統計マニュアル第5版改訂版(DSM-5-TR)および国際疾病分類第11回改訂版(ICD-11)において、「強迫症および関連症群/強迫スペクトラム症群」に分類される精神疾患である。その中核症状は、反復的かつ持続的で侵入的な思考、衝動、またはイメージである強迫観念(obsessions)と、それに応じて駆り立てられるように行われる繰り返しの行動または心の中の行為である強迫行為(compulsions)によって特徴づけられる。
DSM-5-TRにおける診断基準
- 強迫観念、強迫行為、またはその両方の存在
- 強迫観念:
- 1. 反復的で持続的な思考、衝動、またはイメージで、それはその障害の経過中の一時期には、侵入的で不適切なものとして体験され、たいていの人において著しい不安や苦痛の原因となる。
- 2. その人は、その思考、衝動、イメージを無視したり抑えつけようとしたり、または何か他の思考や行動(すなわち、強迫行為を行うこと)によって中和しようと試みる。
- 強迫行為:
- 1. 繰り返しの行動(例:手を洗う、順番に並べる、確認する)または心の中の行為(例:祈る、数える、声なく言葉を繰り返す)であり、その人は強迫観念に対して、または厳密に適用しなくてはならないある決まりに従って、それらの行為を行うよう駆り立てられているように感じている。
- 2. その行動または心の中の行為は、不安または苦痛を避ける、または緩和させること、またはいきいきと恐れている出来事や状況を避けることを目的としている。しかし、その行動または心の中の行為は、それによって中和したり避けたりしようとしていることとは現実的な意味でつながりをもっておらず、または明らかに過剰である。
- 強迫観念または強迫行為は時間を浪費させ(例:1日に1時間以上かかる)、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の低下を引き起こしている。
- その症状は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。
- その障害は、他の精神疾患の症状ではうまく説明されない。
特定せよ:
- 病識を伴う:
強迫症の信念が真実ではない、または真実ではないかもしれないと認識している。 - 病識が乏しい:
強迫症の信念がおそらく真実であると思っている。 - 病識の欠如/妄想性の信念:
強迫症の信念が真実であると完全に確信している。 - チック関連:
チック症の現在または既往歴がある。
ICD-11における診断基準 (6B20 Obsessive-compulsive disorder)
ICD-11では、DSM-5とほぼ同様の定義を採用しているが、症状の様相や病識の程度によってさらに細分類される。中核的特徴は、持続的な強迫観念または強迫行為、あるいはその両方が存在し、それらが個人の生活に重大な苦痛や機能障害をもたらすことである。病識の程度(Good to fair insight / Poor to absent insight)やチック障害の併存を特定する点がDSM-5-TRと共通している。
他の不安障害群との違い
OCDは「侵入思考とそれに対する儀式的行動」が中心であり、患者本人にとって自我違和的(ego-dystonic)である点が本質であり、不安障害は「過剰な不安や恐怖反応」と「回避行動」が中心であり、患者はそれをある程度現実的脅威として認知している点が本質的な違いである。
| 疾患 | 中核病態の違い | 認知的特徴の違い | 神経生物学的相違 |
|---|---|---|---|
| OCD | 強迫観念(obsessions):不合理で繰り返し侵入的に生じる思考・イメージ・衝動 強迫行為(compulsions):苦痛や不安を軽減するための反復的行動や心的儀式 患者は通常「自分の思考や行為が過剰・不合理」と自覚しており(病識あり)、「異常さの自覚を伴う自我違和的症状」が特徴。 | 「思考=行為(thought-action fusion)」の誤信念が関与。 例:「悪い考えを持つだけで罪になる」「考えただけで現実化する」。 | 皮質—線条体—視床回路(CSTC回路)の機能異常が中心。 |
| 不安障害群 | 中核は「将来の危険や脅威の予期」に基づく過剰な不安・恐怖反応。 回避行動や安全確保行動が主体であり、強迫的儀式行為のような形式的・定型的な行動パターンはみられない。 思考内容も「現実的脅威の誇張」であり、OCDのような不合理さへの自覚を伴う侵入思考とは質的に異なる。 | 危険予測のバイアスや不確実性に対する耐性低下。 例:「飛行機が墜落するかもしれない」「また発作が起きるかもしれない」。 | 扁桃体と前頭前野のネットワーク異常、過剰な恐怖条件づけが主体。 |
【2】疫学(有病率・性差・発症年齢)
OCDの疫学データは、診断基準の変遷や調査方法により幅があるが、概ね一貫した傾向が示されている。
- 有病率:
生涯有病率は世界的に1〜3%と推定されている(Kessler et al., 2005, PMID: 16024840)。日本での大規模な疫学調査(世界精神保健調査日本調査)でも、12ヵ月有病率は0.9%、生涯有病率は1.6%と報告されており、国際的なデータと大きな乖離はない(Kawakami et al., 2014, PMID: 24321764)。 - 性差:
成人では女性にやや多い傾向があるが、小児期〜思春期においては男性の方が早期に発症するため、有病率は男性に高い(Fineberg et al., 2013, PMID: 23668670)。 - 発症年齢:
平均発症年齢は19.5歳であり、約25%が14歳までに発症する。35歳以降の発症は比較的まれである。発症年齢には二峰性のピークがあり、一つは小児期後期〜思春期、もう一つは20代前半である(Ruscio et al., 2010, PMID: 19948259)。
OCDの有病率・発症年齢データ
| 項目 | データ | 出典 |
| 生涯有病率(世界) | 1-3% | Kessler et al., 2005 |
| 生涯有病率(日本) | 1.6% | Kawakami et al., 2014 |
| 12ヵ月有病率(日本) | 0.9% | Kawakami et al., 2014 |
| 平均発症年齢 | 19.5歳 | Ruscio et al., 2010 |
| 性差(成人) | 女性 > 男性 | Fineberg et al., 2013 |
| 性差(小児・思春期) | 男性 > 女性 | Fineberg et al., 2013 |
【3】病因・病態生理
OCDの病因は単一ではなく、遺伝的脆弱性を基盤として、神経生物学的、心理社会的な要因が相互作用する多因子モデルが提唱されている。
神経生物学的要因
CSTC回路の機能異常:
- 現在最も有力な仮説は、皮質-線条体-視床-皮質回路(Cortico-Striato-Thalamo-Cortical: CSTC)の機能異常である。この回路は、眼窩前頭皮質(OFC)、前部帯状回(ACC)、線条体(尾状核、被殻)、視床背内側核から構成される。
- 機能的画像研究(fMRI, PET)では、安静時および症状誘発課題時に、健常対照群と比較してOCD患者ではOFC、ACC、尾状核の活動が亢進していることが一貫して示されている(Menzies et al., 2008, PMID: 17999395)。
- この回路の過活動が、不適切な思考や行動への「ブレーキ」が効かなくなり、強迫観念や強迫行為として現れると考えられている。
神経伝達物質:
- セロトニン(5-HT)系:
SSRIがOCD治療に有効であるという臨床的エビデンスから、セロトニン系の機能不全が病態に関与していることは広く受け入れられている。 - ドパミン(DA)系:
SSRI抵抗性の症例に対してドパミンD2受容体拮抗薬(非定型抗精神病薬)の増強療法が有効な場合があること、チック関連OCDの存在から、基底核におけるドパミン系の関与も示唆されている。 - グルタミン酸系:
CSTC回路における主要な興奮性神経伝達物質であり、その機能異常が回路の過活動を引き起こす一因と考えられている。リルゾールやメマンチンなどのグルタミン酸作動薬の臨床試験も進行中である(Goodman et al., 2013, PMID: 23810265
遺伝的要因
OCD患者の第一度親族におけるOCDの発症リスクは、一般人口に比べて約4〜5倍高い。双生児研究では、一卵性双生児の一致率は二卵性双生児よりも有意に高く、遺伝率は成人で27-47%、小児では45-65%と推定されている(van Grootheest et al., 2005, PMID: 15924233)。
特定の単一遺伝子は見つかっていないが、セロトニンやグルタミン酸系の遺伝子多型が関連候補として研究されている。
心理社会的要因
学習理論では、Mowrerの二段階モデルが古典的である。すなわち、第一段階で中立的な刺激(例:ドアノブ)が不安喚起刺激(例:汚染の恐怖)と対になることで条件付けられ(古典的条件付け)、第二段階で強迫行為(例:手洗い)が不安を低減させるため、陰性強化によって維持される(オペラント条件付け)と説明される。
認知モデルでは、侵入思考に対する破局的な誤った解釈(例:「この考えが浮かんだということは、私はそれを実行する危険な人間だ」)が、思考を行為と同一視する「思考-行為融合(Thought-Action Fusion)」や、過剰な責任感などが症状の維持に関与するとされる。
【4】臨床症状・経過
OCDの症状は多彩であり、主要な症状次元(symptom dimension)に分類できる。
| 症状次元 | 主な強迫観念 | 主な強迫行為 |
| 汚染 (Contamination) | 細菌、汚れ、化学物質、体液などによる汚染の恐怖 | 過剰な手洗い、洗浄、汚れていると思うものを避ける |
| 責任/加害 (Responsibility for harm) | 自分の不注意で他者に危害を加えてしまう恐怖 | 繰り返し確認する (鍵、ガスの元栓、運転ルートなど) |
| 対称性/正確性 (Symmetry/Exactness) | 物事が「ちょうど良い」状態でないと落ち着かない感覚 | 物の配置を整える、動作を繰り返す、儀式的な行為 |
| 許容できない思考 (Unacceptable thoughts) | 攻撃的、性的、宗教的に禁忌とされる思考 | 精神的な儀式 (祈り、数唱)、打ち消しの思考、安心を求める |
| ためこみ (Hoarding) | DSM-5で「ためこみ症」として独立 |
経過
- 多くは慢性的な経過をたどり、症状は軽快と増悪を繰り返す。約15%が進行性の悪化を示し、寛解に至るのは約20%とされる(Koran, 2000)。
- 併存疾患は非常に多く、生涯にわたり何らかの他の精神疾患を併存する割合は90%に上る。最も多いのは不安症群(75.8%)、次いで気分障害(特にうつ病、63.3%)、衝動制御障害群、物質使用障害などである(Ruscio et al., 2010, PMID: 19948259)。うつ病の併存は、治療反応性や自殺リスクに影響するため特に注意が必要である。
【5】鑑別診断と評価尺度
評価尺度
診断はDSM-5-TRまたはICD-11の診断基準に基づき、臨床面接によって行う。症状の重症度評価には、半構造化面接であるYale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS)がゴールドスタンダードとして用いられる。Y-BOCSは、強迫観念と強迫行為について、費やす時間、妨害の程度、苦痛、抵抗、コントロールの5項目をそれぞれ評価し、合計点で重症度を判定する(0-7点:無症状、8-15点:軽症、16-23点:中等症、24-31点:重症、32-40点:最重症)。
鑑別診断
| 鑑別疾患 | 鑑別点 |
| 不安症群 | 全般不安症の心配は現実的な内容が多いが、OCDの強迫観念は非現実的・奇妙な内容を含むことが多い。 社交不安症の恐怖は他者からの否定的評価に限定される。 |
| うつ病 | 反芻は過去の出来事に関する抑うつ的な内容が中心であり、OCDのような中和行為を伴わない。 |
| 統合失調症スペクトラム障害 | 病識が欠如したOCDは妄想との鑑別が難しい。 統合失調症では、思考が自我異質的でなく、幻覚や他の陰性症状・認知機能障害を伴うことが多い。 |
| 身体醜形症 | こだわりが外見上の欠点に限定される。 |
| ためこみ症 | 物の価値に関わらず、捨てることへの持続的な困難が主症状であり、侵入的な強迫観念を必ずしも伴わない。 |
| 強迫性パーソナリティ障害 (OCPD) | OCPDの秩序や完璧主義へのこだわりは、自我親和的で、特定の強迫観念や強迫行為に結びつかない全般的な行動パターンである。 |
| チック症・トゥレット症 | チックは不随意運動であり、強迫行為のような目的性や複雑な思考を伴わない。 ただし、併存は多く、鑑別が困難な場合もある。 |
【6】検査(心理/画像/血液検査)
OCDに特異的な生物学的マーカーは確立されていないため、診断を目的とした検査はない。
- 心理検査:
- Y-BOCS: 重症度評価、治療効果判定に必須。
- Maudsley Obsessional-Compulsive Inventory (MOCI): 症状次元を評価する自己記入式質問紙。
- Padua Inventory (PI): 同上。
- 知能検査(WAISなど)やパーソナリティ検査(MMPIなど)は、併存疾患やパーソナリティ特性の評価、治療計画立案の補助として有用な場合がある。
- 画像検査:
研究レベルではfMRIやPETが病態解明に用いられるが、臨床診断での有用性は確立されていない。脳腫瘍や器質的疾患が疑われる非典型的な症例では、頭部CTやMRIが鑑別のために施行されることがある。 - 血液検査:
薬物療法導入前のベースライン評価(肝機能、腎機能、血算など)や、鑑別診断(甲状腺機能など)のために行う。
【7】治療(薬物療法・心理社会的介入)
エビデンスに基づく治療の二本柱は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を主とする薬物療法と、曝露反応妨害法(ERP)を主とする認知行動療法(CBT)である。
薬物療法
第一選択薬:SSRI
- 本邦で保険適用のあるSSRIは、フルボキサミンとパロキセチンである。また、三環系抗うつ薬(TCA)であるクロミプラミンも有効性が高く、保険適用がある。
- SSRIは、うつ病治療よりも高用量かつ長期間の投与が必要となる場合が多い(Fineberg et al., 2018, PMID: 30044234)。十分な効果判定には10〜12週間の継続投与が必要である。
WFSBPガイドラインにおけるSSRIの推奨投与量と本邦での最大量
| 薬剤名 | WFSBP推奨投与量(mg/day) | 本邦での最大量(mg/day) | 本邦でのOCDへの保険適用 |
| エスシタロプラム | 10-20 | 20 | なし |
| パロキセチン | 40-60 | 50 | あり |
| セルトラリン | 50-200 | 100 | なし |
| フルボキサミン | 100-300 | 300 | あり |
| クロミプラミン | 100-250 | 225 | あり |
治療抵抗性OCDへの対応
- SSRIの切り替え:
一つのSSRIに無効または忍容性がない場合、別のSSRIまたはクロミプラミンへの変更を試みる。 - 増強療法(Augmentation):
SSRIに十分な効果が見られない場合、非定型抗精神病薬(アリピプラゾール、リスペリドンなど)の少量併用が有効であるというエビデンスがある(GRADE: 1, Strength: A)(Skapinakis et al., 2014, PMID: 24782312)。 - その他の薬物療法:
ラモトリギン、トピラマートなどの抗てんかん薬や、リルゾールなどのグルタミン酸作動薬が研究されているが、エビデンスはまだ限定的である。
心理社会的介入
曝露反応妨害法(ERP: Exposure and Response Prevention)
- OCDに対する心理療法として最もエビデンスレベルが高い(GRADE: 1, Strength: A)。
- 単独療法としても薬物療法との併用療法としても有効であり、特に強迫行為が顕著な症例に効果的である(Foa et al., 2005, PMID: 15626302)。
- 治療の原理は、古典的な学習理論に基づき、強迫観念によって誘発される不安に対して、強迫行為という回避行動(反応)を妨害し、不安を喚起する刺激(状況)に意図的に身を曝す(曝露)ことで、不安が自然に低減(馴化)し、破局的認知が起こらないことを学習させることにある。
- セッションは通常、週1〜2回、1回90分程度で行われ、セッション間のホームワークが極めて重要である。
治療アルゴリズム(日本不安症学会/日本神経精神薬理学会ガイドライン2025年版に基づく)
- 初期治療:
- 軽症〜中等症:ERP単独 or SSRI単独
- 中等症〜重症:ERPとSSRIの併用
- 第一選択薬に反応不十分(10-12週):
- 用量を最大耐用量まで増量
- それでも不十分なら、別のSSRI or クロミプラミンに変更
- 第二選択薬にも反応不十分:
- 非定型抗精神病薬(アリピプラゾール、リスペリドン)による増強療法
- 治療抵抗性:
- 専門施設へのコンサルテーション
- 神経刺激療法(rTMS、DBS)の検討
入院適応
- 極度の症状により、日常生活が著しく困難で、外来治療の維持が不可能。
- 重篤な抑うつを併発し、自殺リスクが高い。
- 自己ネグレクトや栄養状態の悪化が深刻。
- 外来でのERPが困難で、集中的な行動療法プログラムが必要。
【8】予後・再発予防
- 予後
- OCDは慢性疾患であり、自然寛解はまれである。しかし、適切な治療により、40-60%の患者で症状の有意な改善が見込める。
- 予後不良因子としては、早期発症、症状の重症度、病識の欠如、チックやパーソナリティ障害の併存、治療へのアドヒアランス不良などが挙げられる。
- 再発予防
- 薬物療法で改善した場合、症状安定後も少なくとも1〜2年は同用量で服薬を継続することが推奨される。時期尚早の減薬は高い再発リスクを伴う。
- ERPの効果は、治療終結後も比較的持続することが知られている。治療で身につけたスキルを日常生活で継続して実践することが再発予防に繋がる。ストレスマネジメントも重要である。
【9】最新研究動向(過去5年)と今後の展望(2025年時点)
- 神経刺激療法
- 反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS):
補足運動野(SMA)や背外側前頭前野(DLPFC)をターゲットとしたrTMSが、治療抵抗性OCDに対して有効である可能性が複数のRCTで示唆され、一部の国では承認されている(Carmi et al., 2019, PMID: 31712076)。 - 脳深部刺激療法(DBS):
腹側線条体などをターゲットとしたDBSは、最も重症な治療抵抗性OCDに対する最終手段として、その有効性と安全性が確立されつつある。
- 反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS):
- 神経免疫学
- PANDAS(小児自己免疫性溶連菌関連性精神神経障害)の概念から発展し、感染症や炎症がOCDの病態に関与する可能性が研究されている。マイクログリアの活性化など、神経炎症がCSTC回路の機能異常に関わるという仮説が注目されている。
- デジタルセラピューティクス(DTx)
- スマートフォンアプリなどを介してERPを提供するデジタルセラピューティクスが開発され、医療へのアクセスを改善し、治療効果を高める手段として期待されている。臨床試験も進行中である(Laing et al., 2023, PMID: 37488975)。
- 今後の展望
- OCDの生物学的なサブタイプの同定が進み、個々の患者の病態生理に基づいた個別化医療(Precision Medicine)の実現が期待される。バイオマーカー(脳画像、遺伝子、血液データなど)を用いて、治療反応性を予測し、最適な治療法を選択する試みが続けられるだろう。
【10】国内外ガイドライン比較
| ガイドライン | 第一選択治療 | 第二選択/増強療法 | 特徴 |
| 日本不安症学会/ 日本神経精神薬理学会 (2025) | ・CBT(ERP) ・SSRI ・両者の併用 | ・SSRIの変更 ・クロミプラミン ・非定型抗精神病薬による増強 | 日本の臨床実態に即しており、保険適用のある薬剤を中心に記載。 Shared Decision Makingの重要性を強調。 |
| 米国精神医学会 (APA) (2013 practice guideline) | ・CBT(ERP) ・SSRI ・両者の併用 | ・SSRIの変更 ・クロミプラミン ・非定型抗精神病薬による増強 ・DBS(重度抵抗性) | エビデンスに基づき、治療のステップを詳細に提示。 併存疾患の管理についても言及。 |
| 英国国立医療技術評価機構 (NICE) (2005, updated) | ・CBT(ERP)(低強度から高強度まで段階的) ・症状が重度の場合にSSRIを併用 | ・SSRIの変更/増量 ・クロミプラミン ・非定型抗精神病薬による増強 | CBTの役割を特に重視し、心理療法へのアクセスを優先する「ステップドケアモデル」を提唱。 費用対効果の観点も含む。 |
全体として、CBT(ERP)とSSRIを治療の根幹とする点は世界共通のコンセンサスである。治療法の選択においては、患者の重症度、症状のタイプ、併存疾患、そして患者自身の希望や価値観を考慮した共有意思決定(Shared Decision Making)が不可欠である。
【11】参考文献
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed., text revision. American Psychiatric Publishing.
- 日本精神神経学会 (日本語版用語監修). (2023). DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院.
- 永井 良三 (シリーズ総監修), 笠井 清登 (編集). (2021). 精神科研修ノート第3版. 診断と治療社.
- 井上 令一 (監修). (2022). カプラン臨床精神医学テキスト第3版. MEDSI.
- 松崎 朝樹 (著). (2020). 精神診療プラチナマニュアル第3版. MEDSI.
- (2021). こころの健康が見える第1版. MEDIC MEDIA.
- Carmi, L., et al. (2019). Efficacy and Safety of Deep Transcranial Magnetic Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Prospective Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. American Journal of Psychiatry, 176(11), 931-938. (PMID: 31712076)
- Fineberg, N. A., et al. (2018). Optimal Treatment for OCD (OTO): A randomised controlled feasibility study of the clinical-and cost-effectiveness of cognitive behavioural therapy (CBT), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and their combination in the management of obsessive compulsive disorder. International Clinical Psychopharmacology, 33(6), 334-348. (PMID: 30044234)
- Foa, E. B., et al. (2005). Randomized, placebo-controlled trial of exposure and ritual prevention, clomipramine, and their combination in the treatment of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 162(1), 151-161. (PMID: 15626302)
- Goodman, W. K., et al. (2013). Obsessive-compulsive disorder: advances in diagnosis and treatment. JAMA Psychiatry, 70(7), 748-755. (PMID: 23810265)
- Kawakami, N., et al. (2014). Twelve-month prevalence, severity, and treatment of common mental disorders in communities in Japan: the World Mental Health Japan Survey 2002–2006. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 68(5), 317-329. (PMID: 24321764)
- Koran, L. M. (2000). Obsessive-compulsive disorder. In B. J. Sadock & V. A. Sadock (Eds.), Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry (7th ed., pp. 1533–1552). Lippincott Williams & Wilkins.
- Menzies, L., et al. (2008). Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: the orbitofronto-striatal model revisited. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(3), 525-549. (PMID: 17999395)
- Ruscio, A. M., et al. (2010). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Molecular Psychiatry, 15(1), 53-63. (PMID: 19948259)
- Skapinakis, P., et al. (2014). Augmentation of serotonin reuptake inhibitors (SRIs) with atypical antipsychotics for obsessive-compulsive disorder (OCD): a meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 96(4), 438-446. (PMID: 24782312)
- van Grootheest, D. S., et al. (2005). A review of twin and family studies in obsessive-compulsive disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(35), 12389-12394. (PMID: 15924233)
2




