摂食障害は、食事の量や食べ方を自分でコントロールできなくなり、心と体に深刻な影響が及ぶ病気です。体重や体型への強いこだわりが特徴で、専門的な治療が必要です。
食事と体重への強いこだわりが心身を蝕む病気
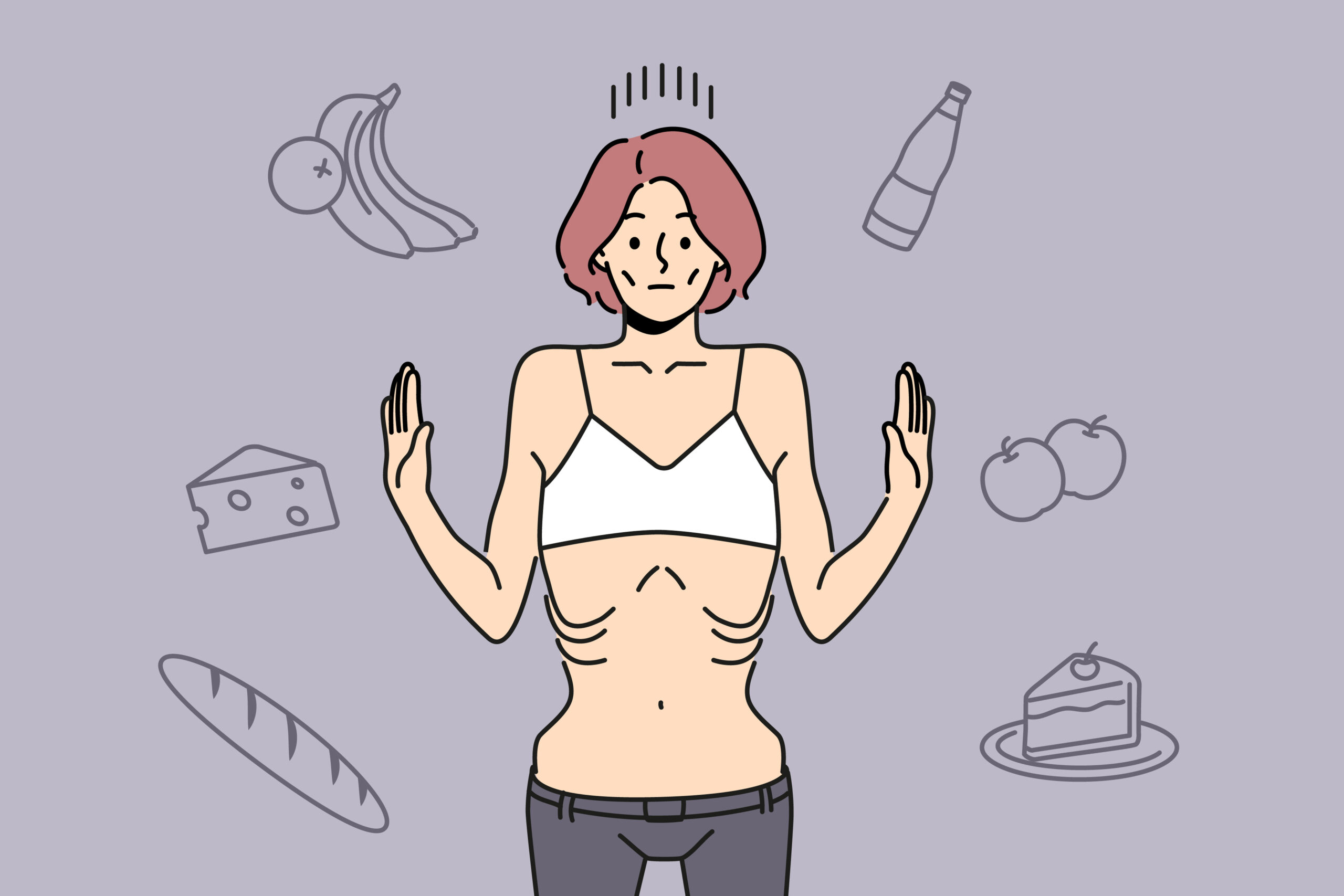
- 極端な食事制限をする
- 隠れて大量に食べる
- 食べた後に自分で吐く
- 下剤や利尿剤の不適切な使用
- 体重や体型に過度にこだわる
- 著しい低体重
- 疲れやすさや気分の落ち込み
- 月経が止まる
【1】疾患概念・定義(DSM-5-TR / ICD-11)
摂食障害は、DSM-5-TRでは「食行動症および摂食症群」、ICD-11では「食行動症または摂食症群」として分類される精神疾患の一群である。食行動の異常が持続し、結果として身体的健康や心理社会的機能に重大な支障をきたすことを特徴とする。
神経性やせ症 (Anorexia Nervosa: AN)
DSM-5-TR (307.1) では、以下の3つの基準を満たす必要がある。
- カロリー摂取の制限により、年齢、性別、発達経緯、身体的健康状態に照らして有意の低体重となる。
- 有意の低体重であるにもかかわらず、体重増加や肥満になることへの強い恐怖、または体重増加を妨げる持続的な行動がある。
- 体重や体型に対する自己評価の障害、自己評価に対する体重・体型の過剰な影響、または現在の低体重の重篤さの否認。
病型として「摂食制限型」と「むちゃ食い・排出型」がある。重症度は成人の場合、BMI (kg/m²) に基づいて分類される(軽度: ≥17, 中等度: 16-16.99, 重度: 15-15.99, 最重度: <15)。
神経性過食症 (Bulimia Nervosa: BN)
DSM-5-TR (307.51) の診断基準は以下の通り。
- 反復するむちゃ食いのエピソード。以下の2つで特徴づけられる。
- 1. 他の人が食べるより明らかに多い食物を、限られた時間内(例:2時間)に食べること。
- 2. エピソード中に食べることをコントロールできないという感覚。
- 体重増加を防ぐための反復する不適切な代償行動(自己誘発性嘔吐、下剤・利尿薬・他の医薬品の乱用、絶食、過剰な運動)。
- むちゃ食いと代償行動が、平均して週に1回以上、3カ月間続いている。
- 自己評価が体型および体重の影響を過度に受けている。 E. 障害が神経性やせ症のエピソード中にのみ起こるものではない。
重症度は、週あたりの不適切な代償行動の頻度で決定される(軽度: 1-3回, 中等度: 4-7回, 重度: 8-13回, 最重度: 14回以上)。
過食性障害 (Binge-Eating Disorder: BED)
DSM-5-TR (307.52) の診断基準は以下の通り。
- 神経性過食症の基準Aと同様の、反復するむちゃ食いのエピソード。
- むちゃ食いのエピソードは、以下のうち3つ(またはそれ以上)を伴う。
- 1. 普段よりずっと速く食べる。
- 2. 不快な満腹感を覚えるまで食べる。
- 3. 空腹を身体的に感じていないときに大量に食べる。
- 4. 大量に食べていることへの恥ずかしさから一人で食べる。
- 5. 食後に自己嫌悪、抑うつ、または強い罪悪感を感じる。
- むちゃ食いに関する著しい苦痛が存在する。
- むちゃ食いが、平均して週に1回以上、3カ月間続いている。
- むちゃ食いは、神経性過食症でみられるような反復する不適切な代償行動を伴わず、神経性やせ症または神経性過食症のエピソード中にのみ起こるものではない。
回避・制限性食物摂取症 (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder: ARFID)
DSM-5-TR (307.59) で定義され、ICD-11 (6B83) でも同様の概念が採用されている。これは従来の「乳幼児期の哺育障害」を拡張した概念である。
- 以下の一つ(またはそれ以上)によって顕在化される、適切な栄養および/またはエネルギーの必要性が持続的に満たされないことに関連した食行動の障害。
- 1. 有意な体重減少(または小児期に期待される体重増加の欠如、または成長曲線を下回ること)。
- 2. 有意な栄養不足。
- 3. 経腸栄養または経口栄養補助食品への依存。
- 4. 心理社会的機能の著しい障害。
- 障害は、食料が入手できないことや、関連する文化的に容認された慣習によってうまく説明されない。
- 食行動の障害は、神経性やせ症または神経性過食症の経過中にのみ起こるものではなく、体重や体型へのこだわりに関する証拠がない。
- 食行動の障害は、併存する医学的疾患や他の精神疾患によってうまく説明されない。それらによって説明される場合でも、その障害は、通常その状態に関連する重症度を超えている。
ARFIDは、食物への関心の欠如、食物の感覚的特性への嫌悪、食物摂取の嫌悪的結果(窒息、嘔吐など)への懸念など、多様な理由で発症する。AN/BNとの最大の鑑別点は、「体重や体型へのこだわりがない」点である (Thomas, J. J. et al., 2017, PMID: 28836435)。
【2】疫学(国内外、有病率、性差、発症年齢)
摂食障害の疫学データは調査対象や診断基準により変動するが、近年のメタ解析等から以下が示されている。
| 疾患 | 生涯有病率 (女性) | 生涯有病率 (男性) | 男女比 (女性:男性) | 好発年齢 |
| 神経性やせ症(AN) | 1.0% – 4.0% | 0.1% – 0.3% | 約 10 : 1 | 10代半ば~後半 |
| 神経性過食症(BN) | 1.0% – 2.0% | 0.1% – 0.5% | 約 10 : 1 | 10代後半~20代前半 |
| 過食性障害(BED) | 2.0% – 3.5% | 0.5% – 2.0% | 約 3 : 2 | 若年成人期~中年期 |
| ARFID | データは限定的だが、一般人口で0.3-5.5%、小児の摂食障害専門外来では5-15%と報告されている。 | 性差はAN/BNほど顕著ではない、あるいは男性にやや多いとの報告もある。 | 小児期~成人期 |
近年の動向として、COVID-19パンデミックが摂食障害の新規発症および既存症状の悪化に影響を与えたことが複数の研究で報告されている (大迫鑑顕ほか, 2024)。社会的孤立、ストレスの増大、生活リズムの乱れなどが要因として挙げられる。
【3】病因・病態生理(神経生物学・心理社会的要因)
摂食障害の病態は、生物学的脆弱性を基盤として、心理的要因、社会文化的要因が相互に影響し合う、多元的なモデルで理解されている。
神経生物学的要因
- 遺伝的要因:
双生児研究から、ANで50-60%、BNで28-83%の高い遺伝率が示唆されている (Thornton, L. M. et al., 2010, PMID: 20516782)。GWAS研究では、ANと代謝系および精神医学的特性(OCD, うつ病など)との遺伝的相関が特定されている (Watson, H. J. et al., 2019, PMID: 31308493)。 - 神経伝達物質:
セロトニン系は気分、衝動性、食欲の調節に関与し、摂食障害の病態生理における役割が示唆されている。特にBNやANむちゃ食い・排出型ではセロトニン機能の低下が、AN摂食制限型ではセロトニン受容体の過剰応答が仮説として提唱されている。ドーパミン系は報酬、動機づけに関与し、食物摂取や運動への異常な反応に関連する可能性が指摘されている。 - 脳機能・構造:
fMRI研究では、摂食障害患者において、報酬系(線条体)、自己認知(楔前部、後部帯状回)、認知制御(前頭前野)を含む神経回路の機能異常が報告されている。特に、AN患者では食物刺激に対して腹側線条体の反応が低下する一方、背側線条体の反応は亢進しており、食物摂取が報酬ではなく不安や習慣的行動として処理されている可能性が示唆される (Frank, G. K. W., 2015, PMID: 26233461)。 - 腸内細菌叢:
近年の研究では、腸内細菌叢の多様性の低下や構成の変化が、AN患者の心理症状(うつ、不安)や体重回復と関連することが示されており、新たな治療標的として注目されている (磯部昌憲, 2024)。
心理社会的要因
- 心理的特性:
完璧主義、強迫性、自己評価の低さ、否定的感情、神経症的傾向などがリスク因子として確立されている。特にANでは不安回避や固執性、BNでは衝動性や感情調節困難が顕著に見られる。 - 発達的要因:
小児期の食習慣の問題、不安障害の既往、被虐待体験(身体的、性的、情緒的)は、後の摂食障害発症の有意なリスク因子である。 - 社会文化的要因:
「痩せの理想化」という西欧文化圏の価値観の内面化が、体型への不満を高め、ダイエット行動を介して発症リスクを増大させることが知られている。SNSの普及は、理想化された身体イメージへの曝露を増加させ、社会的比較を通じてこの影響を増幅させている (Holland, G. & Tiggemann, M., 2016, PMID: 27216472)。
【4】臨床症状・経過(典型例・非典型例)
神経性やせ症 (AN)
典型例では、10代半ばの女性がダイエットを契機に発症し、体重減少が成功体験となり、次第に食事制限がエスカレートする。体重減少に伴い低栄養による身体症状(無月経、徐脈、低体温等)が出現するが、本人は病識に乏しく、治療に抵抗することが多い。経過は多様で、単一エピソードで寛解する例から、寛解と再燃を繰り返す慢性的な経過を辿る例、死に至る例まで様々である。死亡率は全精神疾患の中でも高く、約半数が身体合併症、約20%が自殺による。
神経性過食症 (BN)
10代後半から20代前半に発症することが多い。ANの既往を持つ場合も少なくない。むちゃ食いは強いストレスや否定的感情を契機に生じ、一時的な解放感をもたらすが、直後に強い罪悪感や自己嫌悪に襲われ、代償行動に至るという悪循環を形成する。体重は正常範囲内かやや過体重であることが多く、症状を他者に隠しているため、発見が遅れやすい。慢性化しやすいが、ANよりは予後良好とされる。
回避・制限性食物摂取症 (ARFID)
小児期に発症することが多いが、成人で診断されることもある。発症様式は、①食物への明らかな関心の欠如、②食物の感覚的特性(食感、匂い、見た目)への過敏性、③過去の嫌悪的経験(窒息、嘔吐)への恐怖、の3つに大別される。ANと異なり、体型や体重への恐怖はない。特定の食品群を完全に避けるため、重篤な栄養失調(壊血病やビタミンA欠乏症など)をきたすことがある。
【5】鑑別診断と評価尺度
鑑別診断
- 身体疾患:
- 体重減少や食欲不振をきたす悪性腫瘍、吸収不良症候群、内分泌疾患(甲状腺機能亢進症、Addison病など)、中枢神経系疾患を除外する。
- 精神疾患:
- うつ病:
食欲低下による体重減少が見られるが、ANのような体重・体型へのこだわりはない。 - 強迫症(OCD):
食物へのこだわりが汚染への恐怖などに基づいている場合。 - 身体醜形障害:
体重や全体的な体型ではなく、特定の身体部位への欠陥にとらわれている場合。 - 統合失調症:
妄想(例:食物に毒が入っている)によって食事を拒否している場合。
- うつ病:
評価尺度
- Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q):
摂食障害の認知と行動の重症度を評価する自己記入式質問票。 - Eating Attitudes Test (EAT-26):
摂食障害のリスクをスクリーニングする自己記入式質問票。 - Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder Screen (NIAS):
ARFIDのスクリーニングツール。
【6】検査(心理検査・画像・血液)
| 検査の種類 | 目的 | 主な項目・所見 |
| 血液検査 | 栄養状態、電解質異常、身体合併症の評価 | 全血球計算(汎血球減少) 電解質(低K、低Na、低Cl、代謝性アルカローシス/アシドーシス) 肝機能(AST/ALT上昇) 腎機能(BUN/Cre上昇) 甲状腺機能、血糖 血中アミラーゼ(唾液腺型の上昇) |
| 心電図 (ECG) | 不整脈、徐脈の評価 | 洞性徐脈、QT延長、低K血症に伴うU波・ST低下 |
| 骨密度検査 (DXA) | 骨粗しょう症の評価 | AN患者で有意に骨密度が低下。 若年発症では骨量形成不全が問題となる。 |
| 頭部画像検査 (MRI) | 器質的疾患の除外、脳の変化の評価 | 脳萎縮様所見(pseudoatrophy)。 体重回復に伴い可逆的とされる。 |
| 心理検査 | 認知特性、併存精神疾患の評価 | 知能検査 (WAIS/WISC) 人格検査 (MMPI, YG) 質問紙法 (BDI, STAI) |
【7】治療(薬物療法、心理社会的介入、入院適応)
治療は多職種チーム(医師、心理士、看護師、管理栄養士、ソーシャルワーカー等)による包括的なアプローチが推奨される (NICE guideline [NG69], 2017)。
心理社会的介入
- 神経性やせ症 (AN):
- 思春期・青年期:
家族療法 (Family-Based Treatment; FBT) が第一選択として最も強いエビデンスを有する (GRADE: A)。 - 成人:
ANに特化した認知行動療法 (CBT-AN)、Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for Adults (MANTRA)、Specialist Supportive Clinical Management (SSCM) などが推奨されるが、FBTほどの確立したエビデンスはない。
- 思春期・青年期:
- 神経性過食症 (BN):
- 認知行動療法 (Cognitive Behavioral Therapy for BN; CBT-BN) が第一選択である (GRADE: A)。これはガイデッドセルフヘルプ形式でも有効性が示されている。
- CBT-BNが無効または実施困難な場合、対人関係療法 (IPT) も有効な選択肢である。
- 過食性障害 (BED):
- BNと同様に、CBT (CBT-BED) が第一選択である。IPTも有効である。
- 回避・制限性食物摂取症 (ARFID):
- 確立された治療法はまだないが、不安や恐怖に基づく回避に対しては認知行動療法的なアプローチ (CBT-ARFID) が有望視されている。これには、系統的脱感作や曝露療法が含まれる (Thomas, J. J. et al., 2017, PMID: 28836435)。
薬物療法
- AN:
体重増加を直接促進する有効な薬剤はない。併存するうつ病や強迫症に対してSSRIが使用されることがあるが、低体重状態では効果が限定的であり、副作用のリスク(特にQT延長)に注意が必要である。非定型抗精神病薬(特にオランザピン)が、体重増加への不安や固執性の緩和に有効である可能性が示唆されているが、エビデンスは一貫していない (APA Practice Guideline, 2023)。 - BN:
フルオキセチン (SSRI) が、プラセボと比較してむちゃ食いおよび排出行動を有意に減少させることが示されており、第一選択薬として推奨される (GRADE: A)。通常、うつ病治療よりも高用量(例:60mg/日)が必要となる。 - BED:
BNと同様にSSRIが有効である。また、ADHD治療薬であるリスデキサンフェタミンが、むちゃ食いの頻度を減少させるとして米国FDAに承認されている。
入院適応
入院治療の判断は、身体的および精神医学的リスクに基づいて行われる。APAガイドライン (2023) 等では、以下の基準が示されている。
身体的基準 (Medical Criteria)
- 体重:
BMI < 15 kg/m²、または急速な体重減少(例:3ヶ月で15%以上)。 - 心血管系:
安静時心拍数 < 40 bpm、血圧 < 80/60 mmHg、起立性低血圧(収縮期血圧20mmHg以上の低下、脈拍30bpm以上の上昇)、不整脈、QTc間隔の延長。 - 電解質・代謝異常:
重篤な電解質異常(例:血清K < 3.0 mEq/L)、低血糖、低リン血症(特に再栄養症候群のリスク)。 - その他:
低体温 (< 35.5°C)、脱水、身体合併症による臓器不全の徴候。
精神医学的基準 (Psychiatric Criteria)
- 自殺企図・念慮:
切迫した自殺のリスクがある場合。 - 併存疾患:
重度のうつ病、精神病症状、薬物乱用などが外来での管理を困難にしている場合。 - 治療環境:
外来治療が効果不十分、または治療構造(例:食事管理)が家庭環境では提供できない場合。 - 動機付け:
治療への動機付けが著しく低く、協力が得られない場合。
【8】予後・再発予防(機能予後含む)
摂食障害の予後は様々である。長期的な追跡調査によれば、AN患者の約半数が完全に回復し、約30%が部分的に回復、約20%が慢性的な経過を辿ると報告されている。BNはANより予後良好で、約50-70%が寛解に至る。
予後良好因子としては、若年発症、罹病期間が短いこと、高い治療動機、良好な親子関係などが挙げられる。一方で、重度の低体重、むちゃ食い・排出行動、併存精神疾患(特にパーソナリティ障害)は、予後不良因子とされる。
再発予防には、心理教育、ストレスマネジメント、対人関係スキルのトレーニング、生活リズムの維持が重要である。治療終結後も、定期的なフォローアップや支持的な精神療法が再発リスクを低減する。
【9】最新研究動向(過去5年)と今後の展望
- 神経画像研究の進展:
安静時機能的結合MRI (rs-fMRI) などを用いた大規模な研究(例:ENIGMA-EDコンソーシアム)により、摂食障害の神経回路基盤の解明が進んでいる。これにより、将来的には治療反応性を予測するバイオマーカーの同定が期待される。 - ニューロモジュレーション:
経頭蓋磁気刺激法 (TMS) や深部脳刺激療法 (DBS) など、神経回路に直接介入する治療法の研究が、難治性ANを中心に進められている。特に自己制御や報酬系に関連する脳領域(例:背外側前頭前野)がターゲットとされている (Godier, L. R. & Park, R. J., 2021, PMID: 34139886)。 - 腸内細菌叢-脳-腸相関:
腸内細菌叢が摂食障害の病態に関与するエビデンスが集積しており、プロバイオティクスや糞便微生物移植 (FMT) といった新たな治療アプローチの可能性が探求されている。 - ARFIDの治療法開発:
ARFIDの認知度向上に伴い、CBT-ARFIDや家族療法など、その多様な病態に応じた治療法の開発と有効性の検証が急務となっている。 - デジタルヘルスの活用:
スマートフォンアプリを用いたセルフモニタリングや遠隔での治療介入(テレヘルス)は、治療へのアクセスを向上させ、リアルタイムでの支援を可能にするツールとして期待されている。
今後の展望としては、これらの知見を統合し、個々の患者の生物学的・心理学的特性に基づいた個別化医療 (personalized medicine) を実現することが大きな目標となる。
【10】国内外ガイドライン比較
| ガイドライン | 発行元 | 特徴 |
| APA Practice Guideline (2023) | 米国精神医学会 (American Psychiatric Association) | 最新のエビデンスを網羅的にレビューし、推奨事項を提示。 特に薬物療法や入院適応に関する基準が詳細。 |
| NICE Guideline [NG69] (2017) | 英国国立医療技術評価機構 (National Institute for Health and Care Excellence) | 費用対効果の観点も重視。 心理社会的介入のアルゴリズムが明確に示されており、特に若年者に対する家族療法の位置づけを強調している。 |
| 摂食障害治療ガイドライン (2012) | 日本摂食障害学会 | 日本の医療事情に合わせた内容。 身体管理の基準や地域連携の重要性について言及。 現在、改訂作業が進められている。 |
全体として、心理社会的介入を治療の中心に据える点では共通している。特に若年性ANに対する家族療法の推奨、BN/BEDに対するCBTの推奨は、各ガイドラインで一致している。薬物療法の位置づけは補助的であるが、BNに対するSSRIの有効性は広く認められている。
【11】参考文献
- American Psychiatric Association. (2023). Practice Guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders, Fourth Edition.
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, text revision (DSM-5-TR). (日本精神神経学会 (日本語版用語監修), 『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』, 医学書院)
- Frank, G. K. W. (2015). Anorexia nervosa and the brain. Current Opinion in Psychiatry, 28(6), 469-474. (PMID: 26233461)
- Godier, L. R., & Park, R. J. (2021). Neuromodulation for eating disorders: A systematic review of emerging therapies. European Eating Disorders Review, 29(5), 681-700. (PMID: 34139886)
- Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and eating disorders. Body Image, 17, 100-110. (PMID: 27216472)
- National Institute for Health and Care Excellence. (2017). Eating disorders: recognition and treatment (NG69).
- Thomas, J. J., Lawson, E. A., Miskovic-Subic, E., et al. (2017). Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder: A Three-Dimensional Model of Neurobiology with Implications for Etiology and Treatment. Current Psychiatry Reports, 19(8), 54. (PMID: 28836435)
- Thornton, L. M., Mazzeo, S. E., & Bulik, C. M. (2011). The heritability of eating disorders: a literature review and commentary. Current Psychiatry Reports, 13(4), 406-414. (PMID: 20516782)
- Watson, H. J., Yilmaz, Z., Thornton, L. M., et al. (2019). Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabolic-psychiatric origins for anorexia nervosa. Nature Genetics, 51(8), 1207-1214. (PMID: 31308493)
- World Health Organization. (2022). International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11).
- 磯部昌憲. (2024). ヒトおよびマウスにおける神経性やせ症の病態への腸内細菌叢の関与. JJED, 4(1), 68.
- 大迫鑑顕ほか. (2024). 疫学データから見た摂食障害~COVID-19 パンデミックが摂食障害に与えた影響とその対策~. JJED, 4(1), 45-54.
- 永井良三 (シリーズ総監修), 笠井清登 (編集). (2021). 『精神科研修ノート第3版』. 診断と治療社.
- 井上令一 (監修). (2017). 『カプラン臨床精神医学テキスト第3版』. MEDSI.
- 松崎朝樹 (著). (2020). 『精神診療プラチナマニュアル第3版』. MEDSI.
- (2021). 『こころの健康が見える第1版』. MEDIC MEDIA.
2




